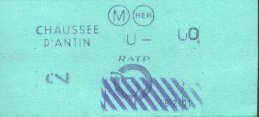アンダーグラウンド(Underground)はロンドンの地下鉄、メトロ(Metro)はパリの地下鉄の呼称である。この両都市にとって、駅も本数も多い地下鉄は人々の流通を支える上で不可欠な存在であり、観光でこの都市を移動するにも、最も便利な乗り物である。
(旅行年月:1993年3月)
ENGLAND: LONDON (Underground)
ピカデリーサーカス駅 チューブの愛称こと、アンダーグラウンド トラファルガー・スクエア一(Trafalgar SQ.)やナショナル・ギャラリー(National Gallery)などロンドン市内を観光し、ホテルへ戻る時に地下鉄を利用した。ビカデリー線(Piccadilly Line)のピカデリー・サーカス(Piccadilly Circus)駅からグロスター・ロード(Gloucester Road)駅までの5駅である。
ピカデリー.サーカスはロンドン歓楽街の中心地であり、日本の渋谷ハチ公広場といったところである。サーカスの中央にはエロスの像が建っているのだが、現在は修理中で見ることができない。その像の周りには、若者が地べたに座りたむろしている。ピカデリー周辺は、世界各国からの観光客でにぎやかな場所であった。
地下鉄の入口には、赤船の丸に青の横棒の入ったマークが掲げてある。誰でも人目で地下鉄の入口を見つけることができる。階段を降りて地下に入った。
地上の明るい世界から地下に入ると、気分が圧迫される。お世辞にもきれいで明るいとは言えない。浮浪者の大きな奇声が聞こえてきた。と言っても人々は大勢歩いており、もちろん特別身に迫る危険はない。新宿駅西口の都庁へ向かう暗い地下の雑踏といったような所である。新宿西口の地下もあまり気分の良い場所ではない。
人波をかきわけ、自動券売機の前にたどり着いた。料金は距離制であり、横に貼ってある駅名表によって値段を見る。「Gloucester Road-90P」と書いてあったので、90ペンスである。ロンドンの通貨単位はイギリス・ボンド(£)で、1ボンドは100ペンス(P)である。当時£1=\185だったので、料金は日本円で170円程度ということになる。初乗りは80P(=150円)であった。
自動券売機にはおつりの出るものと出ないものの2種類ある。釣り銭の出る券売機を使った。金色の縁のある1ポンド硬貨を入れた。が、しばらくすると下の受け取り口に戻ってきてしまった。もうー度入れてみたが、結果は同じ。外国ではよく機械が壊れているから注意せよ、という忠告を聞いたことがあったので、隣の券売機で買うことにした。ところがやはり硬貨は戻ってきてしまった。隣の人の買うところを観察してみると、購入したい金額のボタンを先に押してからコインを入れていた。なるほど、先に料金ボタンを押すのである。90Pのボタンを押すと、前面のディスプレイに「90P」の表示が表われ、コインを入たら、あっけなく切符と10P硬貨が出てきた。
後ろには自動改札機が並んでいた。これから乗る地下鉄はピカデリー線のヒースロー空港(Heathrow Airport)方面である。改札の隣に制服を着た長身の駅員がいたので、とっさに大声で聞いた。
「Excuse me.え-つと、Heathrow Airport !」
これだけを喋った。晋段英語を全く使っていないので、突然だと文を組み立てている余裕がなく、何と聞いていいのか、言葉が浮かんでこない。今考えると、『Which subway …・・・』と聞けばよいと思えるのだが。普通の声では聞こえないほど、まわりは喧操としていた。そしたら、駅員の人は顔を僕の高さに持ってきて、改札内のエスカレーターを指差しながらゆっくりとした口調で、
「0.K.! Heathrow Airport・・…○○○(今思うと、何と言っていたのか思い出せない! そのときの意味ではまつすぐ行ってエスカレーターを降りて、といった感じだった)Tracknumber 4!!」
と、最後は4本の指をたてながら、笑顔で言葉が返ってきた。
「Thank you!」
こちらも笑顔で答えた。単純な僕は、これだけでイギリス人は噂どおり寛大で親切だな、と思った。(実際、旅行中のイギリス人はこちらから尋ねれば親切に応対してくれた。)
自動改札を通り、4番線へ向かうエスカレーターに乗った。ロンドンの地下鉄も日本と同じように色別で路線が表示されているので、案内は非常にわかりやすい。日本と同じようになるのは当たり前で、日本の地下鉄はロンドンを見本にしているのである。ビカデリー線は紫色であった。
イギリスでは、エスカレーターは急ぐ人の為に左側を空けておく、という有名な習慣がある。それを思い出し、右側に寄って下へと降りていった。確かに全員左側をきれいに空けていた。メンテナンスが悪いのか、キーキー金属のきしむ音があちこちで聞こえている。足元にはごみも多少散らばっていた。すると、フルートの高らかな音楽が聞こえてきた。エスカレーターの降り口に笛を吹く、髭を生やしたおじさんが立っていた。体をリスムにのせながら、エスカレーターに乗っている人々を見つめていた。地下なので音は隅々まで響き渡り、それがかえって不気味でもあった。地下鉄構内で芸をして稼いでいるのである。面倒見のいい日本では、即営団や警察によって排除されてしまうに違いない。これも寛大なロンドンらしさなのか。
4番線に着いた。地下鉄を待つ人々が大勢いた。列は作っておらず、ただ漠然と待っているといった感じである。発光ダイオードの電光掲示板には、今度の電車と次の電車の行き先が表示されており、どちらも「Heathrow Airport」と書かれていた。
銀色の地下鉄がやって来た。乗客がどっと降りどっと乗ったので、車内は再び混雑した。なんとか体がくっつかない程度であった。車内は小さく、天井はトンネル断面に合わせて丸くなっており、手を伸ばせば上に届く。前述の通り、トンネル断面は1900年当時のままの12フィート(約3.6m)であり、現在では手狭な感じである。
出入り口のドアも上にいくにしたがって大きく湾曲している。そのため、駅停車中にドア付近に立つと、天井がないのでもっと中に入りたくなるのだが、ドアが閉まると上も閉じてひと安心となる。ドアが閉まる時は、上部にも気を配らないと髪の毛が挟まれることになる。
つり革はなく、その代わり30cm程のばねの付いた鉄の握り棒が、日本の車内のつり革の位置に斜めに取り付けるれている。立ち客はそれを握っていた。
スピード’よ遅かった。都心部だからだろうが、東京の銀座線くらいだろう。駅の案内放送はない。ドアが閉まるときだけボソボソと放送が入る。見逃していると乗り過ごすことになる。あっという間に次の駅、グリーン・パーク(Green Park)に到着した。
ハイドパーク.コーナー(Hyde Park corner),サウス・ケンジントン(South kensington)を過ぎ、下車駅グロスター・ロード(Gloucester RD.)に到着した。
ホームには、列車に乗らず足を伸ばして座っている若者達がいた。このように、ただグループで集まって喋っている光景は欧米では普通であるという。下車した乗客達は、ガラスの入った銀色の大きなドアの前で立ち止まった。地上へはエレベーターに乗って出るようである。2-30人は乗れそうな大きなエレベーターであった。階段を捜してみたが、見当たらない。ないのだろうか。ラッシュ時はどうするのか、密室のエレベータ内で犯罪は起こらないのだろうか、などと心配してしまう。まあ、ロンドンはそれなりに治安が良いので、凶悪犯罪には出くわさないと思うけど……。
地上は明るかった。改札は1階に設けられており、自動改札を出たらそこは道路である。ロンドンの地下鉄は、設備が古いこともあって、奇麗で快適とはいいがたいが、慣れれば使い勝手の良い交通機関であると思う。
オックスフォード駅 地下鉄はもちろん、2階建てバス、国鉄も乗れる1日乗車券





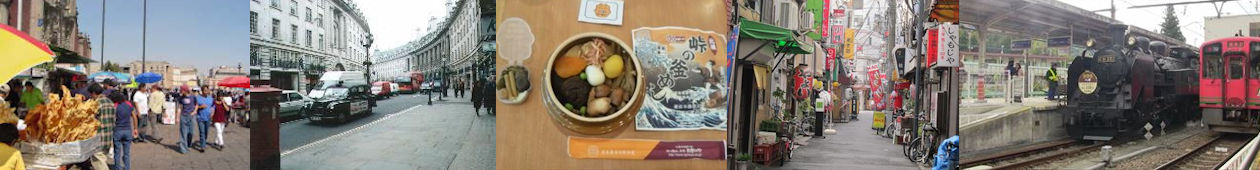
![コヴェントガーデン・カムデンロック[ロンドン散策#2]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/1997/03/covent2.jpg)


![ケンブリッジ・バース・カーディフ[ロンドン散策#3]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/1997/03/cambridge.jpg)




![ケアンズとクランダ鉄道[自然豊かなオーストラリア大陸#1]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/1995/03/FH040034.jpg)














![ウルル(エアーズロック)[自然豊かなオーストラリア大陸#2]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/1995/03/FH000021.jpg)












![シドニーとキャンベラ[自然豊かなオーストラリア大陸#3]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/1995/03/FH010006.jpg)








![香港HongKong[アジアの風景#2]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/1995/03/hong-p11.jpg)







![シンガポールSingapore[アジアの風景#1]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/1995/03/sin-p1.jpg)









![訪欧・ヨーロッパ1[ロンドン編]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/FH0200151.jpg)










![訪欧・ヨーロッパ2[パリ編]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/FH010020.jpg)










![訪欧・ヨーロッパ3[ジュネーブ・ローマ編]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/FH000001.jpg)







![Underground[ロンドン地下鉄の話]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/map.jpg)




![Metro[パリ地下鉄の話]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/map2.jpg)