
冬になると白鳥が訪れる白鳥浜.荒涼とした景観がなんとも美しい.雪の降る冬に訪れてみたい浜である.

白鳥浜を店内から大きなガラス越しに見渡すことができる喫茶店コーヒーショップ「市松」.コーヒーもおいしいが,僕のお薦めはミルクティー.牛乳から入れる本格派ロイヤルミルクティーである.(現在は閉店してしまい,セブンイレブンとなっている)

湿原のような荒涼とした風景が魅力である.
BANCHAN WORLD の福島県内をテーマにしたカテゴリーです.

長浜は,志田浜に次いで観光客には馴染みのある浜である.国道49号沿いに位置し,夏にははくちょう丸やかめ丸の猪苗代湖観光船が発着し,冬になると白鳥が飛来する.

駐車場に車を止めて,ぶらっと浜を散策することが出来る.穏やかな猪苗代湖である.

これが噂のはくちょう丸.隣りにある翁島港の桟橋から発着する.磐梯観光船により4~10月に運航され,大人1000円で35分の翁島めぐりコースを楽しむことが出来る.むかし乗ったときの記憶では,船長の案内がとてもユニーク?(というか,会津のずーずー弁でただがなり声をあげているだけのすごいもの)であったが,今もそうなのかは不明である.一度おためしあれ.

無料駐車場.国道49号線のすぐ脇にある.公衆トイレはあるが,みやげ物屋はないので,おみやげを買うには志田浜がよい.
猪苗代湖は,琵琶湖,霞ヶ浦,サロマ湖に次ぐ,日本第4位の面積を誇る湖である.また,猪苗代湖に流れてくる川は,酸が強いため,酸性湖となっており,そのためプランクトン等が繁殖しにくく,透明度の高い湖でもある.
国道49号(この番号を見ると「49なんて」といつも思う)沿いから湖を眺めることができるが,中でも長浜は,冬になると白鳥が飛来して観光客でにぎわう湖畔である.
一番右の大きな白鳥は「遊覧船」で,翁島周辺をぐるりと35分で遊覧します.船長さんの「がなり声」が響きわたるすごい遊覧船だったが,今はどうなのか・・・?
白鳥とマガモ 冬の動画

志田浜は猪苗代湖の中で最も賑わいのある浜であり,大型観光施設が浜に隣接して建ち並んでいる.国道49号線沿いで大型駐車場も完備されているので,ちょっと立ち寄って猪苗代湖を眺めるのにはとてもよい.

ボートも乗れる志田浜.昔は花火大会も行われていたが,渋滞による緊急車両への影響が出るとのことで,もう20年以上も前だが中止された.高速道路も開通したことだし,なんとか復活してもらいたいものである.

みやげ物屋や店舗が多くある.

天気がよければ,この方角に磐梯山が望める.足こぎボートにも乗ることができる.

国道49号線沿いに立つ「自由の女神」ならぬ,「栄光の女神」! JR磐越西線の臨時の猪苗代湖畔駅前である.

夏の期間のみ,電車が臨時で停車する.
志田浜は国道49号を横断してすぐ目の前にあるが,JR線の車窓からは猪苗代湖はほとんど見ることができない.
◆角川日本地名大事典より◆
耶麻郡猪苗代町上戸の北,小坂山山麓にある猪苗代湖湖岸.磐梯朝日国立公園のうち.すぐ背後に小坂山が迫る浜で,天神浜ほど遠浅ではない.ここより見る緩やかな松林の湖岸線の後ろにそびえる磐梯山は最高に美しい.年中にぎわいをみせるが,夏季は特に水泳やキャンプでにぎわう.

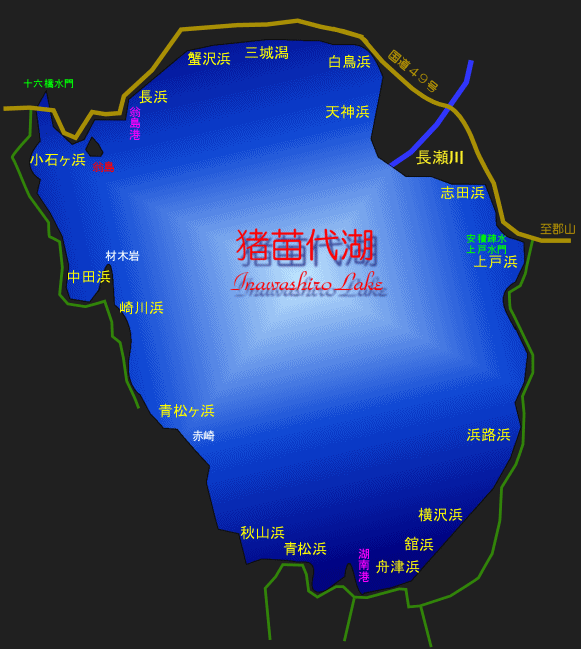
| 志田浜 | 上戸浜 | 浜路浜 | 横沢浜 | 舘浜 |
| 舟津浜 | 青松浜 | 秋山浜 | 青松ヶ浜 | 崎川浜 |
| 中田浜 | 小石ヶ浜 | 長浜 | 蟹沢浜 | 三城潟 |
| 白鳥浜 | 天神浜 | |||
| 安積疎水 上戸水門 |
十六橋水門 | 長瀬川 | 翁島港 | 湖南港 |
猪苗代湖は福島県のほぼ中央に位置し,琵琶湖・霞ヶ浦・サhttps://f-banchan.net/lake_inawashiro_okinajimaport/ロマ湖に次ぐ日本第4位の大きさを誇る大きな湖である.南北約13km,東西約11kmの楕円形の湖盆をなしており,標高は514m,最大水深は約94m,1周は55.3kmである.猪苗代湖の水質(COD)は日本一を達成してたこともあり,酸性の綺麗な湖を誇っている.
◆角川日本地名大事典より◆
耶麻郡猪苗代町・会津若松市・郡山市の境界にあり,わが国第4位の面積をもつ湖.磐梯朝日国立公園のうち.南北14.2km・東西最大9.8kmの卵形の輪郭をもち,水面高度514m,最大深度94.6m・平均深度51.5m,透明度14.5m,湖岸長49km,面積103.9km2である.
湖盆の形をみると湖岸部は緩やかな傾斜をもつ湖棚状を呈し,特に長瀬川~長浜間では深さ2.5m・幅2~3kmの浅い湖棚が続き,湖の中央は,それより急に深くなっているが,水深80m以深は平坦な湖底平原状になっている.湖底から縄文時代の石錘などがみつかっている.
湖の成因は,この湖水の広がる猪苗代盆地の形成過程と深くかかわっており,第四紀の初めの頃,東縁を南北に走る川桁断層の活動による断層角盆地の生成にはじまり,最新世(洪積世)末頃の翁島泥流の堆積,排水口の堰止めと湖水位の上昇(湖面の拡大),排水河川日橋川の下方浸食による湖水位の現高度への低下(現湖水域への縮小)という形成史が明らかにされている.このような地形発達の道筋を証拠づけるものとしては,猪苗代湖の等深線の形状から推定される湖底地形,湖面の急速な上昇を物語る枕水湖岸線と長瀬川三角州の成長,旧高湖面下につくられた湖岸段丘面や湿地などがあげられる.
流入河川として長瀬川が最大で,湖水がpH4~5の弱酸性を示すのは,この河川水のためであり,魚種は少ない.排水口は北西隅の戸ノ口にあり,日橋川となって西流する.
湖水は東部で安積疎水が取水し,郡山盆地の灌漑・発電・工業用水・飲料水に,西部では会津若松市の飲料水・灌漑水・水力発電等に幅広く利用されている.夏は水泳に,冬はハクチョウの飛来する湖として会津の観光地の1つになっている.湖の北西端に唯一の島,翁島がある.
(このページは2005年に掲載したものです)
12月の中頃だというのにこの大雪.このまま寒気が弱まらなく,例年通りの1月2月がやってくるとなると,いったいどれだけの雪の量が降り積もるのか,特に会津地方ではぞっとするような気候が続いている.郡山でも突風と共に雪が降り続き,市内の通りはツルツルに凍り付いて,大渋滞となっていた.東北・磐越自動車道が通行止めになっていることもあって,特に渋滞がひどいのが国道4号・49号線であり,通常は車で15分程度のところが1時間もかかったりしていた.
ところでこんな時,とても重宝する情報はインターネットのライブカメラ画像である.国土交通省や福島県の道路管理者によって管理用に設置された道路カメラの映像をインターネットで24時間静止画像で公開しているもので,雪の状況や道路の渋滞状況がパソコンから見ることができ,「あらら,猪苗代は大雪で大渋滞だよ.こりゃ~,3時間はかかるな」などといったことが瞬時にわかる.ライブカメラは,
国土交通省 http://www.thr.mlit.go.jp/koriyama/
福島県 http://www.pref.fukushima.jp/kenchu/kensetsu/ で見ることができる.
また,NTT東日本で提供している
http://www.ntt-east.co.jp/fukushima/mado/live/index.html もお奨め.
郡山の歴史というと「安積疎水」ははずせない.明治に入って安積疎水の通水による大槻原の開墾を行ったことは全国的な社会科の教科書にも掲載されるほどの大きな出来事である.しかし,そのことに異を唱えて郡山八景ワーキンググループで発行された散策マップがある.それが「郡山八景散策マップ」である.マップの巻頭には,「郡山は,安積疎水で発展したまちと言いますが,実際は有史以来重厚な歴史を持っているまちです.」という言葉から始まっているとおり,安積疎水ができる前から歴史があったんだということを強く訴え,江戸時代の郡山は,奥州街道の大宿場町として歴史遺産が数多くあることをPRしている.郡山八景とは,「弁天の松の雪」「如法寺の晩鐘」「八天狗の糸桜」「愛宕山の秋の月」「八幡森の明け烏」「皿沼の釣舟」「稲荷舘の夜雨」「八丁八橋の駒の跡」となっており,いずれも写真と解説がついており,「へぇ~,こんな歴史遺産があったんだ~」と,小さな街の発見をすることができて面白い.今年(2005年)の10月に駅やホテルなどで無料で配布され,B4判の大きさ,折り畳んで持ち運びができるものとなっている.製作は郡山青年会議所,編集は福島県県中建設事務所のワーキンググループで行った.麓山の福島県合同庁舎案内所前でも配布している.
駅前のビッグアイ最上階23階(外から見て「i」の字の点「・」の部分)には,郡山市の財団法人が運営する「郡山市ふれあい科学館「スペースパーク」」がある.そこには科学に関する展示を行う「展示ゾーン」などの施設とともに,「宇宙劇場」と呼ばれるプラネタリウムが存在している.宇宙劇場の上映時間は45分が基本で,プログラム内容は季節毎に変更するようになっている.入場料が大人400円というのは手軽な値段で大変うれしい.一般番組として宇宙の話を行うもの(12月までのテーマ:「宇宙の果ては?」)や,親と子の天文教室(12月までのテーマ:秋の星とペルセウス座物語),星と音楽の夕べとして各アーチストの曲とともに宇宙に関する映像やプラネタリウムが上映されるもの(過去に,平井堅やクイーン・カーペンターズなどが行われた)も夕方最終回のプログラムに組み込まれている.金曜日に限っては19時からの上映もあるので,仕事帰りにちょっと音楽と星座を見てリラックスをしよう!などといったことも可能である.
今月の「星と音楽の夕べ」のアーチストは中島みゆきであった.金曜日,仕事帰りにちょっと見てみることにした.宇宙劇場内は,映像を映し出すスクリーンである直径23mの傾斜型ドームがあって,座席数は234席となっている.プラネタリウム投影機や全天周映像装置・デジタルプロジェクターなど,最新の設備が設置されている.中島みゆきの「地上の星(プロジェクトXの主題歌)」から始まって,秋の星座が映し出された.今晩見ることのできる星座の解説があって,真っ暗な場内で煌めくような星の映像とともに「空と君のあいだに(ドラマ「家なき子」の主題歌)」「別れうた」「旅人のうた」が流れた.「誕生」の歌のときは,月の誕生について映像が流れ,最後の「ヘッドライト・テールライト(プロジェクトXの挿入歌)」の時は,アポロ13号の月面着陸時の映像が流れ,感動のあっというまの45分間であった.緻密にストーリーを組み立てており,飽きがこなくて見ていて楽しい,聴いていて心安らぐ「星と音楽の夕べ」であった.しかし,入場者が十数名しかおらず,この素晴らしいエンターテイメントにもっと足を運んでもらいたいと思うのは僕だけであろうか.「星と音楽の夕べ」は平日は15:30~,土日祝日(冬季)は17:00~,金曜のみ19:00~も開催される予定となっている.
ところで,クイーンのときは,ディスコ(今はクラブというのか)のようにみんな踊りまくっていたのであろうか? もう一度,平井堅とともに見てみたいと思うのであった.過去の特集も期間限定でアンコールしてもらいたい.
全国のワイドショーで,ゴミを家に持ち込んでいるという男性の話題が連日放送された.それがなんと郡山市の赤木町.それも4軒にもわたってゴミをため込んでいるという.時々こういう報道を見かけるが,どうしてゴミを家の中に積み上げようという心理になるのかちょっと理解に苦しむが,周辺住民からも悪臭がするので撤去して欲しいと郡山市に苦情を言っているようだ.市役所では道路上のものは片づけられるが,家の中のものは撤去できないとのこと.早速,車で赤木町の住宅街の中を走ってみた.4軒もあるので,ぐるぐる走っていれば見つけることができるだろうと思い,うねめ通りの咲田から県合同庁舎に向かう2車線道路に曲がり,ブイチェーン(だったと思うが)の店舗脇の国道4号に抜けれる非常に狭い一方通行の道をしばらく走っていくと,早速ありましたよ,ゴミの入ったスーパーのビニール袋を築堤のように整然と積み上げて塀を造っている木造家屋が(右手側).途中で左に曲がり,またぐるぐると走っていると,今度はがらくたの積んである別の家も発見! そこでは道路脇で整理をしているおじさんがいて,タバコを吸ってこちらを睨んで立っていた. 【ビンゴ!】 恐らくこの人が張本人だと思われる.その脇には郡山市が設置した「不法投棄はやめましょう」の看板が.恐らく,ゴミ屋敷を見に来た人がいっぱいいたと思われる週末であった.
日に日に朝晩の冷え込みが厳しくなり,木々は色づき始めている.国道4号の若葉町交差点から,咲田・西の内・並木・朝日・桑野・亀田と走って希望ヶ丘団地まで,4車線の「うねめ通り」が貫いている.地元の人は,通称「軍用道路」と呼ぶ人もいるが,かつて大槻には陸軍の基地(現在の自衛隊のところか)があって,そこまでの軍用道路としての役割を果たしていたことからこの名がついており,住宅地図を見てみると今でも軍用道路の記載が見受けられる.
そんな「うねめ通り」の西の内・並木(イトーヨーカドー)・朝日町付近の街路樹は色づきはじめている.おそらく「プラタナス」ではないかと思っていたが,よく見ると木の幹の樹皮が白くない.プラタナスは白い大きなカサブタのような樹皮が貼り付いているような感じになるのである.内環状線に植えられている街路樹は,間違いなくプラタナスであるが,うねめ通りの街路樹は似ている別種ではないかと思われる.
プラタナスは,和名では「すずかけのき」と呼ばれ,秋になると真っ黄色に色づき,秋を感じさせる街路樹である.パリのシャンゼリゼ通りにも植えられており,姉妹都市を提携している東京都の街路樹でも多く見ることができる木である.まさに今,並木・朝日町付近では,真っ黄色に色づいたプラタナスが,カサカサと音を立てながら寒風にゆられていた.まもなく,寒い寒い冬がやってくる.そんな,ちょっと寂寥感のある街の風景であった.余談であるが,かなり大きな葉っぱが道路上に舞い落ちており,毎年秋になると落ち葉の片づけが大変そうであるが,先日クレーンにのった作業員が剪定作業を行っていて,内環状線のプラタナスは葉が落ちる前に葉を削ぎ落とされ,丸裸にされていた.落ち葉の苦情が多いのかもしれないが,何か奇妙な光景でもある.
酒飲んだあとのラーメンならぬ「カレー南蛮そば」.陣屋の細いレンガ通りにある「辰美」のカレー南蛮は,「つう」には名の知れている店である.ちょっと綺麗とは言い難い店構えと店内であるが,のれんをくぐるとカレーの香ばしいにおいが鼻に入ってくる.カウンターに椅子がずらりと並べてあり,入ってきたお客のほとんどが「カレー南蛮」を注文する.店先の看板には,「お茶づけ・やきとり・生そば」と書かれていて,ビールや焼き鳥も注文することができるが,やっぱり人気はカレー南蛮なのである.なんといってもつゆがいい.カレー南蛮というと,普通のそばつゆにそばを入れて,申し訳なさそうに上にカレーのソースをかけるだけのカレー南蛮もあるが,ここのそばは「つゆそのもの」が「カレーつゆ」となっていて,味付けが程よくなされている.飲んだあとにはカレー南蛮,これもなかなかいける.
10月に入って,今年度も下半期に突入した.9月30日は上半期の区切りの日とあって,いくつか大きな話題が入ってきた.
まず,交通の話題から.福島と福岡を結ぶ航空路線が来年の3月で休止されることとなった.開港当初から運行している老舗路線であるが,現在の搭乗率は約4割まで下がってしまい,やむなく休止とのことである.運行時間帯が夕方1便のみという不便さもあるが,思うように観光客誘致ができなかったらしい.やっぱりここは,福島空港を野口英世空港にして観光客誘致しか手はない.
郡山・福島と仙台とを結ぶ高速バス競争の火付け役となった富士交通が10月12日をもって運行を取りやめると決定した.富士交通はバス参入の規制緩和を受けて,低価格とサービスを売り物として既設バス会社に対抗して路線を開設したバス会社であり,熾烈な戦いぶりは本コラムのNo.6,No.27,No.49でも取り上げてきたところである.運賃が破格の安さになり,便数も当初の1日6便から大幅に増加していることから,乗客にとってはありがたい競争であったが,軍配は既存バス会社に上がったこととなる.なお,共同運行していた桜交通は,しばらく休止のあと再び仙台線での運行を再開するとしている.
福島県内の民放FM局「ふくしまFM」の本社が10月1日より福島市から郡山市に移転した.ちょうど開局10周年にあたる年に福島県の中心地・郡山に移転したことになる.やはり情報発信は県内どこに行くにも便利で,経済の中心地である郡山市の方がいいということなのだろうか.福島市は仙台までの高速バスの利便性もあって,ますます衰退していっているように感じる.
いわき市に本店を置く,カニピラフで有名なシーフードレストラン「メヒコ」が民事再生法を申請してしまった.営業は続けるそうだが,沖縄県から宮城県まで約20店舗を展開しており,最盛期には売上高約42億円を計上していた.負債は約28億円.なお,メヒコのカニピラフは楽天の通信販売で購入できるのでお試しを.いわきでは鹿島ショッピングセンターのダイエー撤退に続く暗いニュースである.
そんなこんなの上半期であった.
国道4号線を北上し,郡山市から本宮町に入ってすぐ右側にアサヒビールの福島工場がある.1972年(昭和47年)からの操業で,敷地面積約25万m2,年間生産量約7億本(大ビン換算)を誇る国内でも最大級の生産能力を誇る工場である.福島工場からは,東北六県と新潟県・群馬県・栃木県に出荷されている.
ここには,工場に併設されてアサヒビール園があるので,できたてのアサヒビールを飲みながら人気のラム肉のジンギスカンとしゃぶしゃぶを頬張ることができるのであるが,ビール園もさることながら,ビール工場の見学を無料で行うことができるのも魅力のひとつである.原則予約制であるが,混雑していないときは飛び込みで見学を行うこともでき,仕込室・発酵工程・ビン詰工程・缶詰工程・再資源コーナーなどをガイドさんのわかりやすい説明を聞きながら見ることができる.でもなんといってもお楽しみは,最後に出される工場直送の生ビールの試飲(スーパードライと黒ビールから選べる)である.缶ビールのおいしい入れ方が印刷された特注非売品の「カッパえびせん」と「鴨の薫製」のつまみまで出されて,さらにお代わりOK(それなりの大きさのグラス一杯に注がれる)といった太っ腹なサービスで,これで見学無料というのだから,さすがは「アサヒビール」といった感じである.隣のおばちゃんなどは,「うわぁ~,おいし~ぃ! やっぱ,違うわ,これ!」と叫び我を忘れて大はしゃぎ.休みの日になると,大型バスで関東や東北各地から福島県を観光したついでに工場見学とビール園昼食セットでやってくる団体が多いらしく,大勢の人で賑わっており,郡山地方のちょっとした隠れた名所である.
2ヶ月後,案内したガイドさんから1枚の絵はがきが届いた.またお近くにお越しの際はお寄りくださいとのこと.さすがのアサヒビールであった.
郡山から車で1時間ほど南東に走ったところの石川町に母畑温泉がある.母畑温泉は複雑で珍しい岩質のある地質構造を持つ地域であることもあって,アルカリ性単純泉・ラジウム含有泉である放射能泉となっており,神経痛、リューマチ、打身、火傷、切傷に効能があるとされている.その母畑温泉のなかに,ひときわ大きな高級温泉旅館が存在する.その名は「八幡屋」である.
八幡屋は,泊まってみたい温泉宿10選にも選ばれたことがある(何の雑誌かは忘れてしまった!)ほどの名旅館で,一歩建物の中に入ると,ロの字型に宿泊棟が配置された大きな吹き抜けの空洞となっており,ガラス張りのエレベーターが優雅に上下に移動している.(そのエレベーターはドアが閉まると外の景色を見やすくするためにカゴ内のライトが暗くなる芸の細かな演出をしている) なんといっても八幡屋の素晴らしいところは,従業員たちのきめ細やかなおもてなしのサービスで,駐車場のドアまでやってきて荷物を持ってフロントまで案内してくれたり,荷物を持ってもらって部屋まで案内されると自己紹介と館内の説明,そしてお茶を入れてくれたり,宴会時や朝食時も同じ担当のまかないさんが世話をしてくれたりと,きめ細やかなサービスが提供される.
温泉も大きく広々とした浴槽となっており,面白いサウナとして横に寝ころぶラドンサウナ「せせらぎ」を体験することもできる.吹き抜けのホールでは,夜は屋台を並べた夜市が行われ,朝になると舞台の上で琴を優雅に弾いており,なんとも贅沢でくつろぎのある時間を過ごすことができたのであった.
郡山ではリクルート社発行の「ホットペッパー」が発行されている.ホットペッパーは駅やコンビニで入手できる居酒屋やレストランなどの割引クーポン券が印刷されている情報誌であり,毎月月末の金曜日に発行され,値段は「0円」無料となっている.色々な店の紹介の情報誌が無料で手にはいることもあり,結構ちまたでは人気の高い情報誌である.無料となっているカラクリは,掲載している店から広告料ということで収入を得ているためであり,情報誌を見てお店に足を運んでもらえれば,お店側としてはOKということになる.東北地方でホットペッパーが発行されているのは,仙台と郡山の2都市のみであり,そう考えると「郡山って東北第2の都市なんだ!」と感慨深いものがこみ上げてくる.
ホットペッパーが発行されている48都市で見てみると,発行部数が最も多い都市は「銀座・新橋(東京)」の35万部,ついで「大通り・すすきの(札幌)」,「新宿・池袋(東京)」などの30万部となっている.一方,最も少ないのは「長岡(新潟)」の4万部であり,「郡山」は5万1千部となっている.
広告掲載料で比較してみる.最も掲載料の高いのは「大通り・すすきの(札幌)」の6万円(最も枠の小さい1/18ページサイズにおける掲載料の場合.以下同じ)であり,「銀座」や「新宿」の5万円を上回っている.観光客の多く訪れる札幌すすきのを抱える札幌ならではの値段設定なのであろう.そして,最も安いのは,「郡山」と「長岡」の2都市のみで3万2千円となっている.
飲み会の時はホットペッパーを持参して,割引やフリードリンクサービスを受けるとお得感倍増である.ホットペッパーに載っているお店は新規開業のところも多く,新規開業の店は最初のうちは混んでいるが,半年も経つと飽きられて閉店に追い込まれ,また新しいお店が誕生してホットペッパーに掲載され・・・,といった繰り返しの店も多く見られる.読者の約8割が女性であるとのことであり,流行の情報感覚は女性の方が鋭いようである.男性陣は,赤提灯のぶら下がった心安らぐ「ママ」のいる小汚い居酒屋の常連さんの方が心地よいのかもしれない.
なお,ホットペッパーには飲食店の他に,美容室やエステ,スクールなども掲載されている.
郡山仙台間の高速バスの熾烈な戦いについてはNo.27とNo.6でも述べた.その後どうなっているのか,状況をレポートする.
新規参入の富士交通(本社仙台市)が会社更生法を適用してからも高速バスの運行は続けているが,既存バス会社(福島交通・宮城交通・JRバス東北)による本数の増便や回数券の割引の追随攻撃を受けたことにより,乗車客数が伸び悩んでいるようで,新規参入組は当初に比べて本数を激減させており,車内でのお茶のサービス等もなくなっている.料金も往復回数券2,300円で落ち着いてきており,こうなると本数が多い既存3社にお客が流れていくのは当然で,現在では圧倒的に既存3社に軍配が上がっている.仙台駅広瀬通りの宮城交通バス乗り場では,相変わらずハンドマイクを使った案内放送合戦を繰り広げているが,既存3社は3人もの案内係を配置して(もちろんハンドマイク持参),東北各地に発車する高速バスの乗客達をさばいている.新規参入のパートナーである桜交通(本社白河市)も本数を減らしていて,路線がなくなるのも時間の問題であるように思われる.
利用する我々にとっては値下げ競争の結果,仙台に気軽に買い物に行けるようになり,日帰りで充分遊んでくることが可能なので喜ばしい限りであるが,バスが途中でパンクしたり故障して炎上したり,乗務員の過労による居眠り運転などがないよう,安全対策にしわ寄せがこないよう充分にお金を回して欲しいと思うのでありました.
このご時世,少しでもお金を浮かせたい! 東京まで一般道で行くとどうなのか.2人以上の場合,徒歩を除いて最も安く東京に行く方法がこれなのである.郡山市から東京都心までは約250kmあり,食事タイムや休憩時間を入れておおよそ6時間の道中となる.ただひたすら国道4号を南下していくのである.
郡山から須賀川までは4車線(両側)であるが,そこから宇都宮の手前までは白河を除いて2車線の道路となる.ここまでの道のりはバイパスも整備されておらず,スピードも出せずにだらだらと走る感じでとても長く感じられ,那須塩原付近や氏家・矢板付近では大型商店の建ち並ぶ中を走るので,ちょっとした渋滞に巻き込まれる.
宇都宮の手前から4車線の道路となり,新4号バイパスも整備されて小山の南まで信号のほとんどないバイパスが続く.ここでは時速80km(制限速度は60kmですのでお間違いなく.捕まらないギリギリの速度が80kmか?)で快調に飛ばせるので,小山の南まではあっというまに移動することができる.昔は,2車線だったので4車線化の道路整備は着実に進捗していることが伺える.
利根川を渡る手前では再び2車線となるが,用地買収は終わっているようなので,あとは事業が進むのを待つだけであろう.利根川を渡って茨城県にちょっと入るのだが,かつてこの橋を渡るには有料であった.そして,今年オープンしたばかりの道の駅「ごか」(「こが」ではなく「ごか」.古河市ではなく猿島郡五霞町にあるので「ごか」)が左手に現れるので休憩をとるが,郡山東京間の国道4号沿道にある道の駅では唯一のものである.
春日部付近までは2車線であり,バイパスの2車線ではあるがノロノロとなる場合がある.春日部からは4車線となるが建物が建ち並ぶようになり,都会特有の車線の幅が狭い車線となる.僕の場合は途中から右に曲がって,東北自動車道の浦和ICを目差し,国道121号に左折して,鳩ヶ谷・赤羽・王子を走って都心を目差している.
費用は,ガソリン代のみ.燃費はリッター10kmとして,250kmで25リットルのガソリン,1リットル120円とすると片道3,000円となる.ちなみに,今年の夏は2日にわたり,行きと帰りで一般道走行をやったが,次の日はさすがに右肩から背中にかけて筋が張って痛みが残った.さらに,この日から腰痛に悩まされるようになり,長時間運転もほどほどにしないといけない.もう若くない体には,安さの代償にしては大きいものがある.
なお,都心の道路を走る際には,車線が狭いのに加えて,突然右折専用車線になったり,交差点を越えると車線数が変更になっていたりと,道の特性を知らないと予期せぬ事態に遭遇する.慌てずに落ち着いて,左右のサイドミラーを睨みながら安全運転に心がけましょう.
「ビッグアイ」とは郡山駅前にそびえ立つ高層ビルで,地上24階建ての高さ約133mの福島県内で最も高いビルディングである.ビル全体の外観が英子文字の「i」になっている.iの頭の点の部分(20~24階)には展望室とスペースパークと呼ばれる宇宙劇場(プラネタリウム)やふれあい科学館があって,展望室は無料で入ることができる.
この複合ビルには,1~5階にはMOLTI(モルティ)と呼ばれる専門店街,6~7階は土日でも住民票や印鑑証明などが発行できる市役所の市民プラザ(これは便利),8~14階は定時制単位制・通信制単位制の福島県立郡山萌世高校,15~19階はオフィスフロアとなっている.郡山駅西口の再開発事業で行われたのであるが,近年の経済不振によってテナントが思うように集まらずに苦心しているようである.
展望台に登ってみると安積平野が一望できて,緑に囲まれた平野であることが実感できる.かつての郡山駅を再現した鉄道模型のジオラマも展示してある.展望台に行くエレベータは3台あるが,そのうちの1台は直行エレベータでちょっとした細工が施されており,扉が閉まると真っ暗になって足下から赤や黄色のランプがピカピカと光り,宇宙空間を思わせるように「ゴー,ゴー」という効果音が流れてくる.ところが,子供に受けようとしてこの演出を行ったのであろうが,小さい子供は怖がってしまい,「帰りは明るいエレベータで下りるから大丈夫よ」などという光景も.また,女子高生などは冷めたもので,「このピカピカって分けわかんなぁ~い」などと言っている.しかし,このエレベータは全国的にも珍しい演出エレベータなので,みなさん,展望台に行くときは,是非とも一番右側の展望台直行エレベータに乗ってみましょう.
巷で絶大な支持を得ているのが酪王牛乳のカフェオレである.酪王牛乳は福島県酪農協同組合が生産する牛乳のブランドであり,牛乳をはじめ各種乳飲料,ヨーグルト,バターなどを生産している組合である.本部は福島市であるが,工場は郡山市大槻町と会津若松市に存在し,福島県内ではスーパーやコンビニで見かけることのできるポピュラーな牛乳である.郡山市の小学生は大槻工場に社会科見学に行くらしい.なかでも,人気の高い商品が1976(昭和51)年より販売されている「カフェオレ」なのである.
酪王牛乳のカフェオレには2種類ある.生乳50%未満のカフェオレは「ハイ・カフェオレ(1000ml・300ml)」という商品であり,「カフェオレ」よりもよりコーヒー味が強く,こちらは「カフェオレ」とは別商品である.生乳約70%を使用したカフェオレが巷で人気の高い「カフェオレ(500ml・300ml・200ml)」であり,県外に住んでいる人が福島県に戻ってきたときは500mlのカフェオレを買いだめしてしまったり,一度飲んだら他のカフェオレは飲めないという人がいたりと,カフェオレに対する熱い思い入れを語る人は多い.というわけで,早速飲んでみた.この程よいビターな味わいが最高なのであろう.甘すぎず,かといって苦すぎず,一見すると甘ったるいカフェオレを想像してしまうが,このほろ苦さと牛乳のクリーミーさがリピーターを逃さない秘訣の味なのである.

郡山から東京へ行くには,時間の早い新幹線,値段の安い高速バスと利用者のニーズに応じて交通機関を選択することができる.お金がないときは高速バスかな,といった考えがとっさに思いつくが,実はJRの鈍行で乗り換えながら東京に行くのもそんなに時間のかかることではない.新幹線が開業する前の東北本線は,仙台や盛岡・青森などへ向かう特急や急行列車が沢山走っていて,鈍行列車は通過待ち合わせのため時間がかかるものであったが,今では特急はほとんど走っておらず,夕方の寝台特急だって数本なので,普通列車のスピードも速くて思ったよりも時間がかからずに東京まで行くことができる.
郡山駅から東京までは直通列車は走っていないので,黒磯駅と宇都宮駅の2回の乗り換えが必要となるが,平成16年10月の時刻改正によって接続時間がよくなって,数分の待ち合わせで乗り換えができるようになり,さらに宇都宮から東京までの宇都宮線では「快速ラビット」との接続になっているので,よりスピーディに東京まで行けるダイヤになっている.さらに日中は湘南新宿ラインの快速との接続になっているので,新宿や渋谷方面にも行きやすくなっている.平成17年12月のダイヤ改正では,若干接続時間に余裕ができた反面,快速列車との接続が悪くなり,東北本線は各駅停車の接続となることが多くなり,時間も若干かかるようになった.それでも,郡山から東京までの所要時間は,概ね4時間といったところであり,高速バスでは約4時間(郡山・新宿間)なので,時間もほぼ互角といったところである.運賃は,郡山-東京都区内で大人片道3,890円(2日間有効の都区内乗り放題がついた東京自由乗車券だと往復7,200円)なので,高速バスの片道4,000円(往復割引だと7,000円)と互角といったところか.運賃も所要時間も高速バスとあまり変わらないのである.また,宇都宮から東京まではグリーン車が併設されている場合もあり,グリーン料金は事前購入のホリデー(土日)料金で750円(車内購入だと1,000円)なので,東京近郊で混雑しているときはグリーン車を使用してしまう手もある.
鈍行列車は,長距離を乗り通す人が少なくていずれ座れるので,壁際に座ってしまえば足を伸ばしてぐっすり眠っていくことも可能であり,ちょうど1時間程度の乗車ごとに乗り換えがあるので,気分転換を図るのにもちょうどよい.ただ,冬期間の黒磯から東京側の電車は非常に寒い(黒磯から以北の東北本線は逆に暖房が効き過ぎていて熱い!)ので,冬はやめといたほうがよい.また,乗り換え時間が少ないので,もたもたしていると乗り遅れるので,乗換駅では注意が必要である.列車にはトイレもついている(恐らく綺麗とは言えないと思うが・・・)ので心配はない.最近の普通列車は首都圏の通勤電車で見られるロングシートタイプが多くなっているが,黒磯以南では東京側の2両分のみはクロスシート(4人のボックスタイプ)が復活してきているので,のんびり景色を眺めながら行くのも悪くはない.
食べ物の話題を続けてもうひとつ.果物好きな僕としては是非紹介しておきたい.JR郡山駅の駅ビル・エスパル改札口(ビックアイ側の3階にある出口)を出た左手コンコース途中に,果物のフレッシュジュースを販売するフルーツバーAOKIがオープンした.この店は,郡山駅前のアーケード内で青果店を開いている「フルーツショップ青木(フルーツショップ青木のHPではないが,その店をインタビューしたときの様子を紹介している)」が経営している店で,同じくフルーツショップ青木が経営しているフルーツタルト「ル・ヴェルジェ」も併設して店をオープンさせた.青木のフルーツといえば,郡山では高級フルーツの代名詞となっており,「福島版千疋屋」といったところか.最近はフルーツタルトの方が有名にもなっている.
ここのフレッシュジュースは濃縮還元液や食品添加物などをいっさい使わず,甘さもフルーツシュガー(果糖)のみというこだわりの味で,果肉がごろごろとジュースの中に残っているので,キウイジュースなどは口径の大きいストローで飲むようになっている.ソフトクリームやフルーツタルトも売っていて店内には机とイスが置かれているので,その場で食べることも可能である.フレッシュジュースというと,果肉が細かくミキサーで砕かれているものをイメージしてしまうが,ここのは果肉が大きいまま残っているのと,砂糖の不自然な甘さではなくて自然の甘さなので,果物をそのまま食べている感覚で飲むことのできるフレッシュジュースである(僕が飲んだのはキウイジュース).こちらも,モーニングのヨーグルトと併せてお試しあれ.ちなみに,青木のフルーツバーは,県内ではうすい百貨店や郡山モール・郡山ジャスコに,仙台では長町モールに,そして東京のLIVINOZ大泉店・光が丘店などにも出店しているようである.福島県内の本物志向のお店がどんどん全国区になっていくことは嬉しい限りである.
「モーニング」という名前の郡山市安積町に本社(工場)のあるヨーグルト専門店がある.メロンやイチゴなど季節の生のフルーツを混ぜ込んでいるヨーグルトなどを量り売りで販売しており,若い女性をはじめヘルシー志向のブームもあって人気が高く,オシャレな店である.郡山市内在住の女性でモーニングのヨーグルトを知らない人はいないだろう.20年ほど前に一人のお母さんがヨーグルトのデザートを作ったのが始まりで,最初は小さなお店を開いていた.ヨーグルトはすべて手作りで,あだたら高原で育ったホルスタインの牛乳を用いて作られている.現在は郡山市内に8店舗(駅前モルティー,モール,安積町の工場直売など),いわき市に1店舗を展開しているが,関東・首都圏の人から「関東方面では開店しないのですか」といった問い合わせが多いらしく,3月より茨城県つくば市に初の県外店をオープンさせたところである.楽天市場においてWEB通販も開始された.
ヨーグルトはいろいろな種類が売られており,僕のお気に入りは大きな果実とナタデココの入ったイチゴヨーグルトとメロンヨーグルトである.甘すぎず,酸っぱすぎず,フルーツの大きな果肉とヨーグルトそしてナタデココのコリコリ感が程よく混ざっていて非常においしい.プレーンヨーグルトも砂糖入りと砂糖なしがあり,お好みのヨーグルトをショーケースを見ながら選ぶことができ,グラム単位の量り売りで容器に入れて売ってくれる.郡山駅に立ち寄った際は,駅前を出た右手のビックアイ(福島県で一番高い建物)の1階に店舗を開いているので,立ち寄って食べてみることをお勧めする.
ついに桜交通が東京までの格安高速バスを催行することになった.なんと郡山-東京間で片道2000円(福島-東京間は2500円.大人子供同額)である.この高速バスは,運行上は募集型企画旅行取引による主催旅行で,(株)さくら観光が主催するツアー(路線バスではなく貸切バス)ということになる.正確には「高速道路を走行するツアーバス」を略して「高速バス」といったところだろうか.全国的に見ても東京・大阪間や東京・仙台間などでも同じような観光バス専用会社による運行が行われ始めてきている.
申し込みはインターネットか電話申し込みとなってiおり,6月からは1日2往復の体制となった(時刻表などが随時変更しているので,その時の情報を確認したほうがよい).乗車券類などの発券は行っていない.また,バス乗り場もバス停などがあるわけではなく,何の案内板もないので不安になってしまうが,路線バスの扱いではなくツアーバスなので,道路占用許可などを役所に申請しなければならないバス停設置などは行わないと言ったところだろう.取消料は,既存の福島交通やJRバスなどと違って,旅行ツアーの取消料が適用される.前日では40%,当日では50%の手数料が取られるが,もともとの運賃が安いのでたいした額にはならない.既存の高速バスに乗り慣れていると,丁寧な車内案内がなくて不親切だな,のりばが分からなくて不安だな,トイレが付いていないな,などと思ってしまうが,ここは格安であるということを念頭において,乗客自身がしっかりと意識し納得(というか妥協)することが必要であろう.東京駅から郡山駅までは,時刻表では約4時間となっている(途中休憩2回ある)が,東京駅を出てすぐの箱崎ランプから首都高にのってしまうので,すいていれば約3時間30分程度でついてしまう.郡山駅まで直行するが須賀川インターを利用している.
現在のところ,東京では東京駅八重洲口の横断歩道を渡ったところにバス集合場所があるのだが(6月中旬から鍛冶橋駐車場に変更済み),そこには既存バスの千葉方面行きの高速バスのりばがあって,そこの案内係のひとが桜交通などの他社のバスが止まらないように,目を光らせていた.なかなか駐車スペースがなくて路上駐車や交通量の多い現在の場所で乗降させるのは大変だと思われるので,土日には交通量も少なくなる丸の内口のオフィス街のどこかの道路脇に乗降場所を変更したほうがよいのではないかと思った.多少,駅から歩いてもこの格安値段なので乗客も納得するはずである.なにしろ既存の高速バスの約半額,新幹線の約1/4の値段なわけなので.あまり,既存のバス会社や周辺関係者と敵対的関係にならずにこの格安高速バスを続けて欲しいと願うのでありました.なお,既存バス他会社の人に「桜交通の郡山行きのりばはここですか?」などといった質問は避けましょう.トヨタの営業マンに向かって「ホンダのフィットを買いたいのですが」と聞いているのと同じことになるので.のりばはインターネットの地図画面を印刷して,自分のことは自分で理解するようにするほうがよい.格安高速バスはある程度の自覚をして利用すべし!!
(このページは2005年に掲載したものです)
「白河」は,みちのく東北の玄関口として栃木県と接する,福島県中通りの最南に位置している街である.標高が高いため,福島県内でも寒い地域であり,一番南に位置していながら桜の開花が遅い地域でもある.そんな白河でにわかにブームとなっているのが「白河ラーメン」である.喜多方ラーメンの爆発的ヒットに目をつけた,全国各地のご当地ラーメンが次々と名乗りを上げる中で,白河も負けじとラーメンによる町おこしを行っている.今年(H17)で2回目となる「全国ラーメンフェスティバル in白河」の開催の模様とともに,白河ラーメンと白河周辺の見所を紹介したい.



いきなり紹介してしまおう.これが「白河ラーメン」(写真はチャーシュー麺).那須連山からの雪解け水を使用した製麺が旨さのポイントだとか.喜多方ラーメン同様に縮れ麺であるが,喜多方と比べると麺の太さが細い.市内には約90軒のラーメン店があり,観光案内所などではラーメンマップを作っているので,マップ片手に探してみるのもいい.

ちなみにこの店の名物は白河ラーメンの他に,ジャンボオムライスがある.1日限定5食のみ.

店内の壁には有名人やレポーターのサインが沢山貼られている.(この画像の人は有名人ではありません.一般人です.)
◆◆あすなろ食堂◆◆白河旭高校前(旧白河女子高前)

今年(H17)で2回目となる全国ラーメンフェスティバル.地元5店舗を含む全国13店舗のラーメンを,1杯500円で味わうことが出来る.

希望のラーメン店のチケットを買って並ぶ.一般チケットと時間指定チケットがある.どれも500円均一で手数料なしで払戻しも可能.一番並んでいたのは,カップラーメンにもなっている札幌市の「すみれ」だった.

フェスティバル開催時には仙台からの臨時列車も運転される.

地元物産の展示販売も行っていた.

こちらは「そば打ち」の実演.

各ラーメン店舗のブースでラーメンを買ったら,中央のテーブルで食べる.セルフサービス式.

江戸時代の初代藩主・丹羽長重公が完成させた梯郭式の平山城.戊辰の役で焼失した.平成3年に三重櫓,平成6年に前御門が復元された.

白河駅ホームからも見えるが,これは復元された三重櫓であり,小峰城ではない.小峰城は復元されていない.

本丸御殿跡.
小峰城跡地は石碑が置いてあるのみ.

白河市街地

三重櫓の中は,急な階段で登ることが出来る.

白河藩主・松平定信公が1801年に水利開発等のために築造した回遊式自然庭園である.南湖という名は,城の南の湖という意味だという.日本最古の公園であり,日本で最初に周辺整備を行った貯水池としても知られている.

小粒の「南湖だんご」が有名


オシャレな洋菓子店や喫茶店がある.ちょっとしたデートスポット!

ボートにも乗れる.

勿来の関(いわき市),念珠ヶ関(山形県西田川郡)とともに奥州三古関のひとつに数えられている.蝦夷の南下を防ぐ関として五世紀に設置されたが,廃止されてからは芭蕉をはじめとする歌人たちの枕詞としてロマンを誘うようになった.

無料のボランティアガイドが案内をしてくれる.
※白河観光協会発行の「みちのくの玄関・白河百景」パンフレットを参考にして作成しています.
(このページは2003~04年に記載されたものです)
雨の日などはバスに乗って職場に通っている.ここで気になっていることがひとつある.郡山に限らず,福島県内の路線バスに乗ると大抵そうなのであるが,ドアを閉めてバスがバス停を発車する瞬間に,クラクションを「ぷっ!」と鳴らすのである.全国旅行に出かけているが,あまり発車の際にクラクションを鳴らすバスを見たことがない.東京でもクラクションはならさないし,仙台でもならしていないように思う.これは決まりでもあるのであろうか.恐らく,バスが発車するときに周囲に対して警告を発することにより,安全確保と注意喚起を促すためだと思われるが,これだけ車が多く走っている中でクラクションを鳴らされると,周辺の人々(ドライバーも含めて)は発車の合図なのか注意されているのか分からなくなってしまいそうな気がするのである.確かに,昔の映画などを見ると,バスが発車するときには,「ふぁ~ん」とクラクションを鳴らす光景が目に浮かぶが,運行規則か何かに「バスが発車するときはクラクションを鳴らすこと」といったことが記載されているに違いない.そう考えると,福島県内のバスの運転手さんは律儀で真面目であるということが言えるのである.
郡山駅から国道4号にかけて通っている通称「郡山駅前通り」のアーケードが今年度中に立て替えられることになっている.併せて,現在3車線ある車道のうち外側の1車線をなくして歩道を広げる計画となっており,来年になれば見違えるような駅前空間が広がるようになるのである.歩道整備は県において,アーケードの建替えは地元商店街と商工会議所が主体となって事業を進めているが,中心市街地に人を呼び戻すための,郡山の発展のためのハードウエアの整備として,郡山市民を挙げて大いに期待しているところであろう.新聞発表によると,アーケードはシルバーを基調にしたシンプルなつくりで,音響設備などを備え,防犯対策としてテレビカメラを32基設置するという(福島民友より).あとは,ソフト対策であり,人を呼び込むためにいかに魅力ある街並みの空間や賑わいを創出することができるのかである.現在の,消費者金融と夜のネオンの店のみがずらずらと建ち並ぶアーケード街では誰も寄りつかない.道路占用許可も道路を有効に活用できるよう緩和される方向であるとの新聞記事を目にしたが,大道芸人や街中コンサート等のイベントを積極的に行っていったり,魅力ある店舗を誘致し開設しやすくするようにしたり,郡山の知名度アップに貢献している日本一水質の綺麗な猪苗代湖から流れてくる本物の安積疎水の水をアーケードの歩道にせせらぎとして流したりするなど,徹底的にアイデンティティーの確立を行うとともに,街並み空間の楽しさを演出する試みを併せて充実させていければいいのだけどな,と思う今日この頃でした.
4月に入り,JR郡山駅がリニューアルされてオープンした.今まで1階にあった「みどりの窓口」を2階に持っていき,新幹線乗り場のすぐ脇で長距離切符や指定券を購入することができるようになった.
1階には「郡山おみやげ館」という物産館がオープンし,郡山を代表する菓子店舗では「柏屋」「かんのや」「三万石」の御三家の他に「大黒屋」が入店しており,薄皮まんじゅうやゆべし,ままどおるなどを販売している.それ以外にも,会津塗りや会津名産「こづゆ」のレトルトパック,日本酒なども,さらに仙台名産阿倍の笹かまぼこまで置いてある.仙台出張の帰りなどには,郡山駅で土産を買うこともできるのである.
ほかに「FOOD BAZZAR」というショッピングセンターによくあるセルフサービス式の飲食フロアーが出来ていた.クレープやソフトクリーム・各種色付きジュース(とでもいっておこう.こういう類の飲み物は何というのだろうか.アジアンジュースとでもいうのか?)の「デザート王国」,お好み焼きと焼きそばを売るその名も「ふうふう」,石焼きビビンバの「東大門」,尾道ラーメン「岡本屋」,ロコモコとオムライスを売る「LOCOMOCO(ロコモコ)」がテナントとして入っている.ロコモコなんて初耳であるが,ご飯の上にハンバーグと目玉焼きとレタス等をのっけて特性のソースをかけた丼のことで,ハワイが発祥の地の食べ物だそうである.びっくりドンキーのエッグバーグデッシュのライスの上に具がのっているような感じである.客層は,学校帰りの高校生が多い.地方都市で駅を多く利用するのは,相対的に車を持たない学生達が多くなるということなのだろう.フードバザー内のインテリアは「和」の雰囲気で統一されているが,広い空間なので一人でちょこんと食事をするにはだだっ広すぎてちょっと落ち着かない感じである.ソファー席も用意されている.
おばあちゃんの民話茶屋も2階待合室の奥に健在であった.また,なめこそばが一部ちまたのファンで有名な(?)立ち食いそばやも,同じ場所で健在である.さらに,S-PALに向かう2階コンコースには,リラクゼーションサロン「カジュアル」の整体マッサージもオープンした.店名がローカルチックで気に入っていた「福豆屋食堂」はなくなっていた.さらに,1階にあったスパゲティ屋ではモーニングトーストセットをやっていてそこのバナナジュースがおいしかったのであるが,モーニングセットがピザトーストに変更になってしまいバナナジュースもなくなってしまった.残念!である.
郡山と会津を結ぶ国道49号線.中通りと会津地方の境には中山峠があり,中山トンネルで両地方は結ばれている.ところが,このトンネルは凍結による事故が毎年起こっており,数年前には正面衝突による死亡事故まで起こっている.寒さの一番厳しい2月のとある日,この日は強い冬型の気圧配置で,会津地方は気温が低い上に猛烈な風による吹雪が舞い上がっていた.猪苗代から磐梯熱海に向かう国道49号を走っていたが,中山トンネルの手前は,大きな風力発電が1基置かれていることからも分かるように,非常に風の強い区間となっている.防雪柵が立っているにもかかわらずこの日も視界はゼロに近く,ノロノロの渋滞が続いていた.さらに渋滞は続いており,中山トンネルに入っても渋滞が収まらない.トンネル内で事故があったようで,パトカーによる事故処理が行われていた.凍結スリップによる正面衝突のようである.国道を管理する国土交通省も凍結を防止するための「凍結防止剤」をまいているのであろうが,なかなか四六時中凍結を防止することは無理なのだろう.
そんなことを思っていたトンネル内で,ふと車の窓を開けてみた.手を出してみるとすごい強風である.つまり,猪苗代から郡山方面に向かって風が吹き抜けていくのである.車の温度計を見てみたら「マイナス4度」に.つまり,中山トンネルは冬になると強風の吹き抜ける冷凍庫になっているのである.これでは,いくら凍結防止剤をまいても,すぐに路面が凍るわけである.車は一度滑り出すと,どうにもこうにもハンドルが効かなくなって,対向車線にはみ出して正面衝突するといった事故パターンなのであろう.中山トンネルをを通るときには,徐行して注意しながら通過しましょう.
無性に納豆が食べたくなるときがある.外で納豆を食べようとすると,吉野家の牛丼で朝定・納豆定食を食べるということがすぐ思い浮かぶが,郡山市に本社のあるラーメンチェーン店「幸楽苑」の栄町店(国道4号沿い図景町の手前)では24時間営業をしており,朝定食をやっている.ここの納豆定食は304円と,吉野家に比べても安いのであるが,出てくる納豆がちょっと気に入ってしまった.
まず,小粒納豆であること.吉野家では大粒のいかにも「マメ・マメ」とした納豆なのであるが,こちらは食べやすい小粒である.次に,プラスチックの容器の底面にボツボツがついていること.これは,かき混ぜれるときに混ざりやすいようにするといった細かなアイデアが盛り込まれている容器なのである.そして,地元製造業者の納豆を使っていること.郡山市富久山町久保田にある郡山食品団地内にある「久米商店」というところで造られているもので,地産地消が図られているのである.ちなみに,吉野家の納豆は,茨城だか栃木だかの納豆であったように思う.
是非一度,幸楽苑の納豆定食を召し上がれ.朝定は早朝4時から午前11時までである.
いやー寒い!郡山は雪の量もそれほど多くないし,気温も会津に比べれば暖かいのであるが,なんといっても風が強い.これだけは耐え難いものがある.雪が積もっていて風の強くない会津の方がよっぽど暖かく感じるのである.台風並みの強い風が吹くときもあって,「なんでこんなに強い風が吹くの?」といつもぶつぶつ言いながら,マフラーを巻いて郡山の街を歩いている.早く春が来ないかな,と待ち遠しい限りである.あんまり今回は中身がないが,とにかく寒いので記してみました.
日本でも一大ブームを呼び起こした「冬のソナタ」の主人公,ぺ・ヨンジュン(ヨン様)がお忍び旅行で福島空港に現れた.先日,成田空港から来日したときは,ファンでごったがえしていたが,今回は,首都圏から最も近い地方空港で,こっそりと日本入りを目指したようである.このニュースは地もとNHK福島放送局が福島県内だけでニュースと報じたところから知れ渡ったのであるが,ヨン様が福島空港に来るという話が空港関係者に伝えられたのは当日の朝のようで,周辺関係者も大変驚いていたという.ヨン様は,アシアナ航空156便で12時20分頃に到着し,茶色っぽい帽子とサングラスにコート姿で現れ,1階の手荷物受取所南側の非常口から待機していた白いワゴン車に乗って東京方面に向かったとされている.同じ飛行機には約150人の日本人客も乗っていたというが,「近くの人がヨン様が乗っているよ,と教えてくれたので分かった.最初は幻影を見ているのではないかと思った.帽子をかぶり新聞で顔を隠して,カーテンで仕切られたファーストクラスにのっていたので近づけなかった.見に行きたいという気持ちを必死にこらえてた」と話していた(毎日新聞福島版より).
福島空港とソウル仁川空港には,週3便の定期便が飛んでいるが,福島空港発は日・火・金曜日となっている.昨日も,ヨン様が帰国するために福島に現れるのではないかということで,マスコミ数社が空港内で待機していたという.空港にはワイドショーなどのレポーターがやってきて,どこからヨン様が出て行ったか,姿はどうだったかなどと取材を行っていったとのことである.ひょんなことで,全国に有名となった福島空港であるが,ヨン様効果は我がHPにも影響を及ぼし,ヨン様が訪れた日の「福島空港から行く韓国ソウルへ」「福島空港航空時刻表リンク」へのアクセス数が約200ヒットも増えた.ヨン様,様々である.地元紙である福島民報では1面トップで報道し,福島県内ではちょっとしたヨン様ブームが巻き起こっている.
郡山には映画館が固まっているエリアがある.通称「テアトル映画村」と呼ばれているが,郡山テアトルという映画館の建物が3棟集まって建っており,合計で8つのスクリーンが集まるエリアである.外見は一昔前のボーリング場兼映画館といった感じで,決して今風のオシャレな外観ではない.上映映画も全国上映の映画のみで,いわゆるミニシアター系の「単館映画」は上映されていない.可もなく不可もなくといった感じの普通の映画館である.ただ,割引が多くあってよい.
毎月1日は「サービスデー」で1,000円(小・中学生・2歳以上800円),毎週月曜日は「メンズデー」で男性1,000円,毎週水曜日は「学生サービスデー」で学生証提示1,000円,毎週金曜日は「レディースデー」で女性1,000円,午後7時以降に上映される「レイトショー」は1,000円均一,どちらかが50歳以上の夫婦は「夫婦50割引」でペア2,000円(要証明)となっている.特に,レイトショー割引はありがたく,夜の上映は全て1000円というのだから,仕事帰りにちょいと映画を見るのにとてもいい.駐車場を利用する人は300円割引となっているが,重複しての割引は不可能であろう.通常の大人料金は1,800円である.
ちなみに,福島県内でミニシアター系の上映をやっている映画館は,福島市の福島フォーラムのみである.僕もわざわざフォーラムまで見に行ったこともあるが,是非,郡山市でもミニシアター系の上映をしていただきたいと思う,単館ムービーファンの僕でした.
猪苗代湖は会津地方に存在するのであるが,湖の南側である「湖南」地区は郡山市に属しており,猪苗代湖は郡山市にも接している.郡山市民へのアンケート調査でも,猪苗代湖は最も誇りに思うもののひとつに挙げられており,福島県を代表する財産である.さて,先日猪苗代湖の水質保全対策についての講演を聴く機会があって,猪苗代湖の現状について興味深いことを知ることができた.
猪苗代湖は日本第4位の面積を誇る淡水湖で,日本最大の酸性湖となっている.猪苗代湖が酸性なのは,硫酸酸性の強い長瀬川(裏磐梯から流れてくるときの長瀬川は中性であるが,途中で安達太良山系から流れて合流する酸川が酸性である)が流入しているためで,このことが,魚やプランクトンが棲みにくい環境をつくりだし,結果として,水質や透明度は日本でもトップクラスの綺麗な湖となっている.湖沼の汚れを表す指標であるCODは毎年0.5mg/Lで推移し,現在も汚くなる傾向にはなっておらず,全国一の清澄な水質となっている.透明度は例年7~9mで推移していたものが平成14年度から上昇(つまり透明度が増している)していて,平成16年度は12.9mとなっている.アオコ等の富栄養化の元凶となる栄養塩(窒素やリン)の量も環境基準を大きく下回る量で,増加傾向も見られない.(いずれの測定も湖心による)
ところが,水質結果でひとつだけ懸念されることある.それは,PH(ペーハー)が平成8年度まではPH5前後の酸性で推移していたものが,徐々に上昇してきて,平成16年度はPH6.1となり中性化が進行している結果となっていることである.しかし,この中性化の原因がいまだに特定できていない.調査の結果,流入河川の水質にも変化が起こっていないし,平成8年に開通した磐越自動車道に冬期間まかれる凍結防止剤(塩化カルシウム・塩化ナトリウム)との因果関係も確認できなかった.今もって,猪苗代湖の中性化は謎に包まれているのである.
中性化が進むと,いままでの猪苗代湖の水環境が変化し,生態系の変化が予想される.僕も初めて知ったことなのだが,猪苗代湖の水の中では,長瀬川から流入した鉄やアルミニウムを含む酸性の水が,猪苗代湖内の有機物(有機リンや有機窒素など)と結合してフロック(濁りの固まりのような泥)を形成し,そのフロックが湖底に沈降していっているのだそうで,この中和反応によって猪苗代湖の水質は非常に良好になっているとのことである.ロボットカメラで湖底を眺めたら,3cm程度に積もった茶褐色のフロック(泥)が確認されている.そのため水面から2~30m程度以下の水深では,このフロックの影響で逆に濁度(濁り)が非常に大きくなっているとのことである.このまま中性化が進行すると,この中和反応による水質浄化が行われなくなり,長瀬川の流入水の影響が遠くて及ばない湖南地方などで,有機物による富栄養化が起こって水質が悪化することが懸念されている.
また,植生については,絶滅危惧種に指定されているアサザや,栄養塩を吸収するヨシなどは増殖している傾向にあると言っていた.水質改善という点ではいいことなのだが,増殖している背景には,成長に必要な栄養塩類が多く流入しているからであると予想されており,つまり,猪苗代湖に流入する水質に富栄養化の原因となる栄養塩が多く入り込むようになっているのではないかとのことであった.また,ヨシは栄養塩を吸収して水質の浄化は行うが,吸収された栄養塩はヨシの中に蓄積されていくということで,この蓄積が猪苗代湖の土に影響を与えないのか心配であるとの専門家の指摘があった.
猪苗代湖が綺麗で美しく,澄んだ水であることの背景には,強い酸性であるということが挙げられる(農業を行う側としては貧栄養の水なので敬遠される水質である.安積疎水の受益者は低温で貧栄養水なので大変だろう.)が,これは過去から受け継がれている猪苗代湖の財産なので,酸性を維持できるような対策を行って綺麗な猪苗代湖を維持していくべきであろう.
2004年11月1日より新千円札が発行された.肖像は野口英世.福島県が生んだ偉人である.福島県といっても広いのであるが,生まれは猪苗代町で,その後青春時代を会津若松市で過ごし,黄熱病研究のため外国に渡航したのである.地元福島の夕方のニュースは野口英世のニュースで占められており,新札発行に寄せる期待の大きさが伺える.ところで,諸外国の空港ではその国で活躍した著名人を空港名にすることが多い.例えば,パリのシャルルドゴール空港,ローマのレオナルドダビンチ空港,ニューヨークのジョンエフケネディ空港といった具合に.イギリスのリバプール空港はジョンレノン空港に改名している.日本でもこれに習って,坂本龍馬の高知空港では「高知龍馬空港」と改名しており,時刻表などの公の印刷物にも「高知龍馬」の文字が記載されている.
ここで,いっそのこと,福島空港も「福島野口英世空港」に改名したらどうだろうかとの意見が出されている.恐らく,東日本以外の人は野口英世が福島県出身だということを知っている人は少ないと思う.こうすれば観光客の増加によって,伸び悩んでいる福島空港の利活用にも多いに役立つのではないか.福島県民200万人を相手にするのではなく,日本総国民1億人を相手にPRをするのである.福島空港の存在している場所が,中通りの須賀川市・玉川村なので,野口英世とは関係ない土地だとの意見が,県内から出そうであるが,ここは広い視野に立って,会津の野口英世ではなく,福島県の野口英世という位置づけで考えたいものである.むしろ頑固な会津人から,福島空港は会津ではないので命名されては困る!などといった意見が出そうでもあるが,地元の猪苗代町の町議会では,「福島Dr野口英世空港」へ改名することへの意見書を提出し,地元住民の運動の盛り上がりを起こそうとしている.野口英世は世界の野口なので,成田野口英世空港にしてもいいくらいなのである.
薄皮まんじゅう,ゆべしを紹介したら,ままどおるも紹介して欲しいとの依頼があった.こちらも郡山では有名なお菓子である.郡山市に本社のある三万石の代表するお菓子で,ミルクとバターを使ったまろやかな味わいで,洋菓子のような和菓子!といった感じである.「ままどおる」とはスペイン語でお乳を飲む人々という意味だそうで,昭和42年に発売されてからの人気商品となっている.ホコホコとした感触で,この舌触りはなんと表現してよいのか,パンケーキの生地の中にクリームあんこが入った感じといったところか?

郡山にも行列が出来る店ができた.駅前から国道4号線まで延びる駅前大通りのアーケード内に,全国展開するチェーン店の「ボンジュール神戸」という京都市に本社のあるパン屋さんが8月中旬にオープンしたのであるが,連日1個130円のメロンパンを求めるお客で行列ができているのである.休日には大行列となり,車の中からもその様子がよくわかる.このメロンパンは焼きたての無添加であることが売りで,口コミで市民の間に広がったといい,今では1人10個までの限定販売も行っている.まだ食べたことがないので,今度食べてみようと思う.この話題は新聞にも掲載されていたので,郡山で一般市民が行列を作っているという光景は,よっぽど珍しいのではないかと思う.
「忽然とネオンが浮かび上がる不思議な街」,朝日町の飲屋街はこんなイメージである.どうしてこの場所にこのような飲屋街が形成されているのか.郡山市役所と郡山郵便局と内環状線に囲まれた地区に,非常に不思議な空間が広がっている.駅からは遠いし,しかも,ゴチャゴチャとした路地に色々な形の建物が建っている飲屋街ではなく,5軒が1棟となっている長方形のアパートのような建物が,3~4棟程度ならんで建っており,入り口には同じようなネオンがつけられて,飲み屋やスナック・パブなどがずらりと並んでいるのである.歴史的に形成された街ではなく,あたかもとってつけたようにスナック街が形成されたような,「スナックのニュータウン」みたいな空間なのである.まったく同じような建物なので,どの店がどの名前なのか覚えづらい.夜に歩くと,「何なんだこの空間は?」と思わせる.一説には,市役所の裏だから飲屋街が形成されたんだ,という意見もあるが,真相を知りたい飲屋街であった.
そしてその後,タクシーの運転手さんに聞いてみた.すると,駅前よりも地価が安いために飲屋街が移ってきたといい,飲み代も安く済むのだということであった.
新規参入の富士交通の参加によって,仙台郡山間の高速バスの競争が激化していることはNo.6で紹介した.その後,熾烈な競争は留まることがなく,各社次々と戦略を打ち出している.新規参入組は仙台市に本社をおく富士交通のみであったが,福島県白河市に本社をおく桜交通が加り便数も増便され,新規参入2社あわせて1日14往復の運行となった.基本の片道運賃は1800円と変わりがないが,2枚綴りの回数券は既設運行3社(福島交通,宮城交通,JRバス東北)が2600円から2400円の同額に値下げすると,新規参入組はそれまでの2400円から2300円にまたまた値下げして差別化を図っている.さらに,既設3社組はいままで1時間に1本程度だった便数を倍増して約30分間隔とし,1日24往復の運行とした.そして,2004年6月19日より回数券の値段をさらに100円さげて,新規参入と同額の2300円に値下げすることを決定した.こうなってくるとイタチごっこで,どこまで値段が下がってくるのだろうか.片道1800円なのに対し,往復だと2300円なのだから,破格の割引率である.いつかは,片道1800円,往復1700円という時代がくるのだろうか?
お互いの熾烈な競争は随所に見ることができる.
仙台駅ののりばは宮城交通の待合所のとなりに,新規参入組のバス停がある.新規参入組には待合室がない(郡山にはある)のだが,宮城交通の待合所入り口には,「この待合室は下記のバス会社をご利用する方の待合室です.」と書かれた看板がわざわざ掲げられており,もちろん宮城交通と共同運行を行っている会社名のみが書かれている.待合室のガラスには,福島・郡山線の回数券がさらに値下げすることが大きく宣伝されている.
既設3社(宮城交通)のバス本数も多くなっていることから,2台が同時に止まれるように補助バス停が設けられた.その位置が,新規参入組が置いているバス停といままでの既設3社が利用していたバス停との間で,新規参入組のバス停にほど近い位置に置かれた.つまり,新規参入組のバスが止まっている場所に割り込ませるように補助バス停を設けたのである.新規参入組のバスが止まっているときは,この補助バス停にバスを止めることはできないが,新規参入組のバスが発車するとすかさず既設会社はバスを前に移動させて補助バス停を使うようにしている.でも,補助バス停の置かれている位置は,宮城交通の待合室の正面なので,先にバス停を置いた新規参入組の方が優位なのか,宮城交通の待合室は以前からあって,その前の位置なので補助バス停を置いてもいいではないかという理屈の方が優位なのか.こうなってくると,隣の家との境界争いみたいな話になってくる.
土曜日,買い物客が帰る時間帯である19時のバスに乗ったが,新規参入組は12名程度,既設会社組は6名程度であった.今は,往復で100円の料金差があってお茶が出される新規参入組の方が軍配が上がっていたようだが,いずれにせよ5社合わせて1日に38往復も走っているのだから,どう考えても供給過剰である.既設大手3社も,もう利益などは関係なく,会社のメンツにかけて意地になって競争しているようにも見える.利用する方としては,安くてガラガラのバスに乗れるのでありがたい.この競争どこまで続いていくのだろうか.ちなみに,一番最初に運行されたのは2000年3月15日で当時はたった1日6往復であった.
ところが,2004年8月,富士交通は会社更生法を適用し,事実上の倒産となってしまった.高速バスは続行するようであるが.
駅前から延びるさくら通りを走っていき,坂を上った虎丸町に「ホテルハマツ」が建っている.郡山随一の高級ホテルで,かつては東京のアメリカ大使館隣に建っているホテルオークラの系列に加盟していた.もともとは,昭和28(1953)年に郡山で濱津衣装店として貸衣装を行っていたのが始まりで,冠婚葬祭業として成長していき,会津平安閣やはまつ典礼などをオープンさせていった.ホテルハマツは平成3年(1991)年に開業した比較的新しいホテルであるが,ふくしま国体開催時の秋篠宮殿下の来館をはじめ,皇太子殿下および妃殿下,常陸宮殿下及び妃殿下などの皇族方も利用したことのある気品あるホテルとなっている.ところが,バブル崩壊の波はこのホテルにも押し寄せ,ホテルハマツを経営する「ホテルはまつ」が120億円の負債を抱えて民事再生法の適用を昨年の夏(2003年8月)に受けた.産業再生機構の支援を受けたうすい百貨店もそうであるが,高級感を目指した大きな施設が相次いで破産していることは残念である.地方都市においては,高級派よりも庶民派の施設の方が生き残れるのかもしれないが,地域の文化レベルの向上を図る上では重要な施設である.
ちなみに,1泊の宿泊料金は約15,000円~.インペリアルスイートルーム(124.8m2)として1泊1室231,000円(2人まで可)の部屋もある.平日昼には1,050円のランチタイムを実施しており,ちょっとした料理が手頃な値段!?で食べることができる.しかし,奥様方の来店が多いこと,多いこと! クリスマスシーズンになると,正面には大きな電飾ツリーが飾られ,恒例の「中森明菜ディナーショー」が行われている.(2004年は美川憲一ショーであった.)
堂前町におにぎりや団子の専門店「たけや」がある.ここのおにぎりはお勧めである.梅,たらこ,味ご飯,きのこ,わかめ,いなりずしなど,手作りおにぎりがショーウィンドーに並べられ,さらにお総菜や団子なども売っている.値段も110円程度とコンビニとさほど変わりなく,ご飯の味もよい.包装もなかなか凝っていて,日本昔話にでてくる握り飯を竹の笹でくるんだような包装紙におにぎりが詰められて,左右から重ねるようにフタをして,ぺらぺらの紙で包んでくれる.透明なプラスチック製のパックと違い,なかなか食欲をそそる包装なのである.土日の昼時になると,一方通行の道路には車がびっしり止められて行列ができる程で,店内のおばちゃんは忙しそうに客をさばいている.場所は,国道4号線の消防署前から裁判所方面に入っていったところの,如法寺前にある.ちなみに,うすい百貨店のB1階にも出店しているが,包装がプラスチックのパックであり,本店で造った商品を運んでくるようなので,できたての味があじわえず,販売の回転率が良い本店で買う方がよい.また,県道郡山湖南線から静団地に入ったところに姉妹店「さくら」が営業している.
厳しい冬もやっと過ぎ去り,ようやく桜がほころぶ季節となった.今,郡山市では桜が満開で,あちこちでピンク色の桜が咲き誇っている.不思議なことに福島県の中通り・会津では,桜前線は南下していく.一番早く桜が咲くのは,一番北に位置する「福島市」で(福島県内で最も早いのは「いわき」だが・・),その後に「郡山市」,さらに時期が遅れて一番南の「白河市」と咲いていく.白河と同じくらいの時期に会津若松市が満開となり,その後に,南会津の田島町,猪苗代湖のある猪苗代町へと移っていく.これは,桜の咲くための条件である気温が密接に関係しており,暖かくなる順番に桜が咲いていっている.福島市の海抜は66m,郡山市は海抜245m,白河市は361mなのである.南に行くに従って,標高が高くなっているのである.
このため,冬も南の方が寒い傾向にあり,仙台から東京に出張に行くビジネスマンが,仙台では全く雪がなかったのに,新幹線に乗って車窓を眺めていると,南に向かっているにもかかわらず,段々と白い雪景色と変わっていき,栃木県の那須を過ぎると,また雪が無くなってくるといった不思議な風景がよく見られる.ちなみに,会津若松市の海抜は218m,南会津の田島町は海抜550m,日本第4位の湖である猪苗代湖は海抜514mのところにある.
冬も最も厳しい季節になってきた.福島=雪の多く降る所というイメージがあるが,実際大雪が降るのは会津地方で,中通りでは思ったほどは雪が積もらない地域であり,春先にドカッと降る程度のようである(といっても今年初めて住むので実際のところは判らないが・・・).
ところが先日,郡山市で35cmの積雪があり,街中大混乱に陥った.道路は大渋滞,バスはこないしタクシーはつかまらない.完全な交通マヒ状態になったのである.郡山でこれだけの雪が降ると,もうお手上げ状態である.除雪も慣れていない地域なので,会津地方のように綺麗でスムーズな除雪作業が完了せず,ボコボコになった圧雪がいつまでも道路上に残ってしまう結果となってしまう.特にひどいのが,日陰の路地裏の通りであり,ボコボコでツルツルになった氷(雪がいつのまにか踏み固まって氷になっている)が路面に残ってしまい,車のハンドルが思うように効かず左右に振られながら超徐行で走っている.このときばかりは4WDでよかったな,と思ってしまう.4駆でないと前輪がスリップして発進できなかったり,車の尻が振られてクルリとまわったりと,思った通りに車が動いてくれないのである.
すでに雪が降って4日間が経過したが,未だに日陰部の道路の雪は解けず,道路は大渋滞となっている今日この頃であった・・・.
冬将軍の到来である.寒波によって会津では大雪となった週末であったが,郡山でも雪となり道路は圧雪シャーベット状となっている.駐車場なども雪と水でビショビショであり,車から降りた人々は足早に店へと走っていく.会津では,大雪になるとたいていは「長靴」を履いて買い物などに出かけるのであるが,郡山では大雪でも99%の人が普通の靴を履いていた.確かに,長靴は見た目も格好も悪い.東京でも雪が降ったからと言って長靴を履いて街を歩いている人など皆無であり,長靴は「ダサイ」の代名詞なのである.僕は今日,CDを買いに「TUTAYA」に長靴を履いていったら,誰も長靴なんて履いている人がいないではないか.でも,声を大にして言いたい.大雪には長靴が最適である!長靴に勝るものはない!スノトレということも考えられるが,やっぱりビショビショの雪と氷と逃げ場の失っている水が溜まっている駐車場を歩くには,「長靴」が最高なのである.
クリスマスシーズンを控え,あちこちでイルミネーションが見られるようになった.そんな中で,車を運転していて特にイルミネーションが目につく地区がある.それは,国道4号線の郡山駅から須賀川方面に走って図景町までの三菱電機の工場がある「本町」や「栄町」付近である.お互いのビルが競い合っているように,それぞれのビルでツリー型の電飾にしたり,入口の屋根に電飾を飾っていたりしている.まさに,イルミネーションストリートである.郡山の冬は初めてであるが,これほどまでに街中がイルミネーションに包まれているとは思わなかった.気温が低下し,寒い冬がやって来ているが,ちょっと心がホッとするイルミネーションであった.
(このページは2003~04年に記載されたものです)

福島県郡山市に「並木」と「西ノ内」と呼ばれる町名がある.
そこには隠れたお店がいくつかあります.
そんな街の表情をどうぞ.
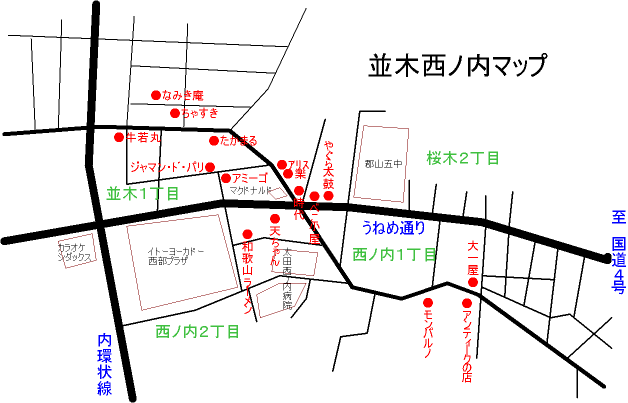


ウナギ屋さんなのであるが,ボリュームのあるランチには定評がある.でも,なんといってもお勧めは,火曜日と日曜日にしかやっていない朝定食である.朝7時から10時までなのであるが,たった500円でこのボリュームは凄い.コーヒーまでつく.サバのみそ煮がなんともいい.(現在は菜根に移転)


崖線を利用してせせらぎを整備したのが「せせらぎこみち」である.郡山市内に点在しているのであるが,ちょっとした散歩コースであり,なかなか面白い.冬になると凍結して危険とのことから,閉鎖される.

やっぱり西ノ内といえば,太田綜合病院西ノ内病院である.郡山の民間病院では一番大きな病院であり,救急治療も行っている.大病院ゆえにちょっとした風邪では行きづらい病院であるが,朝7時30分の受付開始時には,長蛇の列ができて受付が開始される.朝8時頃は,看護婦さんや病院で働く人々が大勢外を歩いている.

こぢんまりとやっている洋菓子屋であるが,巷ではちょっとした店らしい.シュークリームやプリンがお勧めであるが,フルーツゼリーもはずせない.誕生日には外の黒板に「○○くん」などと名前が書かれている.
最近,外壁の色が塗り替えられた.品のある色合いになっているので,現地でのお楽しみ・・・.(現在は閉店)

居酒屋&ラーメン屋といった変わった店.昼にはランチタイムとしてラーメンだけをやっている.ここのラーメンは,「秋田比内地鶏らあめん」として,あっさり鶏ガラのラーメンがだされる.夜には家庭的な料理がだされる.洋菓子屋アリスの隣りの隣りあたり.


郡山でも数少ないフランス料理店.味には定評がある.企画ものの料理コースを手頃な値段で提供しているので,ちょっとフランス料理が食べたくなったら,訪れてみるとよい.

最近店内を改装をして,店名もメキシコ料理にスペイン料理が加わって,ラテン系の料理を出す店になった.味付けはどちらかというと日本風にアレンジしてあるようだが,料理やお皿など,なかなか凝ったものが出される.タコスやパエリヤなど,メキシコ&スペインの料理が,雰囲気の良い店内で食べることができる.ビールも現地風を真似て,瓶の中にライムをいれて,そのままラッパ飲みをする.若者の客が多く,デートコースにはぴったりである.お勧めの店である.(現在は閉店)

外からは麺を打つところが見れる手打ち麺の店.しかも竹で麺を打っているようで,独特の縮れ麺は歯ごたえがよい.ボリュームのある餃子もお勧め.

ここも気になるお店.掘っ立て小屋風の外観だが,夜になると結構人が入っている.中にはいると,決してきれいとは言えない昔ながらの焼肉屋といった感じの雰囲気.特にホルモン関係が安くてうまい.換気扇排気口が道路に向かっているため,外気循環にして車に乗っていると,プーンと焼き肉の香りが車内にまで漂ってくる.

住宅街の中にある,その名も「なみき庵」.会津北西部のそば粉を使用し,そば粉100%の味が楽しめる.そばの香りがもう少し味わえるといいのかなと思うが,一品料理には檜枝岐で出されるそば粉のお菓子「はっとう」などもメニューにあるので,そばだけで物足りない場合は注文するとよい.

べこ小屋などと面白いネーミングであるが,店の中にはいると狭い空間がよりお酒を美味しくさせてくれる.お酒だけのお店ではなく,定食もあり,ランチタイムなどはボリューム満点の定食が食べられる.焼き魚定食を頼んだら,あじの開きが2枚もでてきた.


べこ小屋の隣りにある居酒屋.平日のお昼はランチ定食もやっている.備長炭火焼による伊達鶏の串焼きや天ぷら,刺身,ふぐ鍋などジャンルは広いが,なんといっても名物はちゃんこ鍋.時津風部屋より伝授された特性スープで煮込まれたちゃんこを,スリたてのごまと一緒に食べる.また味わってみたいちゃんこ鍋である.


夜は居酒屋・昼は定食が食べられる.どちらかというと日本酒や焼酎が似合うような店である.刺身は活きが良く,天ぷらはサクサクに揚げられており,素材の良さと味には太鼓判が押せる.冬にはあんこう鍋もある.

焼き鳥ツーには有名な「天ちゃん」である.本店は,郡山駅前のアーケードの裏当たりの薄暗いビルの1階にあり,こちらは西の内店であるが,店内の雰囲気は本店同様,おやじ好みのヌードポスターの貼られたいかにも焼き鳥屋といったものである.カウンター席とテーブル席があるが,いつも満席.焼き鳥は大きくて大変うまい.軟骨もお勧め.そして,レバ刺し.ここのレバ刺しを食べたら,やみつきになる.モツ煮・海老の塩焼きも人気メニュー.ちなみに,焼き鳥は原則5本で1皿となっているが,頼めば2~3本でも焼いてくれる.基本的に愛想のいい方ではない.電話でお土産予約も受け付けてくれる.

なんでこんなところに,というような住宅街の中にある.お茶とコーヒーを売る店であるが,コーヒー焙煎実演を見ることができ,喫茶もできるらしい.

モンパルノ,フランス風の名前である.西ノ内街道にあるパン屋さんで,毎日焼きたてを売っている.朝8時から夜7時までの営業で,昔ながらのパン屋でもなければ,いま流行の欧風パンを売っているわけでもなく,でもフランスパンの焼きたては人気があるらしい.おばあちゃんがレジを売っている.(現在は閉店)

チェーン店の喜多方ラーメン店.夜遅くまで営業している.辛口のごまミソラーメンがおすすめ. 火災により全焼.現在は空き地になっている.(現在は閉店)

未だに何を売っている店なのか不明!!??
器を扱っている店なのか??
現在は,店名が変わって,雑貨を売る店になっている.
(このページは2003年に記載されたものです)
郡山駅の2階・新幹線改札口付近に「おばあちゃんの民話茶屋」というコーナーがある.ここでは毎日,県内各地からの語り部さんが来て,地元の民話を聞かせてくれるという,一風変わった施設である.上演時間は11時,13時,15時の3回あり,無料で出されるお茶を飲みながら,椅子に座って昔話を聞くことができるのである.さらに,店内では民芸品の販売も行っている.コンコースでは,もんぺ(?)のような服をきた人が呼び込みを行っており,平日の昼間でも年配の方などが,話に聞き入っている.運営は,NPO(特定非営利活動法人)である「語りと方言の会」が行っており,福島の文化・伝統を伝える施設として,なかなかユニークなものである.お時間がある時に,寄ってみてくなんしょ!!
郡山市街地の中に温泉がある.うねめ通りの福島トヨタのディーラーから入ったところの並木3丁目に「並木温泉」がある.ここに温泉施設ができたのは1985年頃だといい,当時は小さい浴槽がある小さな温泉施設であった.2000年に現代風に建て直して今の「並木温泉・ゆの郷」となった.入浴料は500円.この安さで温泉に入れるのだからたまらない.タオルなどを持ってこなくても,プラス200円でレンタルのタオルセット(大小2つのタオルが入っている)が用意されているので,突然温泉に入りにきても何の問題もない.泉質はナトリウム硫酸塩泉で,効能は高血圧,動脈硬化,腰痛,皮膚病などとなっており,透き通った無色透明の湯です。温泉は,薄めたりしていないので,湯上がりには温泉の成分が体に染みついて「ぽっかぽか」となる.サウナも付いているので,サウナ好きにもたまらない.食堂も付いているので,お腹がすいているときも大丈夫である.もちろんビン牛乳も売っている.ちなみに回数券も販売されているが,5000円で11枚綴りなのはいいのだが有効期限が1ヶ月しかないので,毎日入るくらいじゃないと回数券は使えない.
西ノ内の西部自動車学校跡地に「西部ブラザ」がある.第1期工事分として平成元年にイトーヨーカドーをキーテナントとしたビルが完成し,第2期工事分として平成12年にケーズデンキやスーパースポーツゼビオなどをテナントとしたビルが完成した.これらのビルは高架の空中歩道で結ばれている.そのケーズデンキの入る1階の奥の方に,ちょっと面白い「ビレッジ・ヴァンガード」という店がある.
この店はエキサイティング・ブックストアーとして全国展開している本屋(本社:名古屋)なのであるが,一歩店に入った感じでは本屋という雰囲気よりは,混沌としたカオス状態の雑貨といった方が似合っている.確かに商品は「本」が一番多いのであるが,それ以外に,菓子,CD,ライター,グッズ,おもちゃ,ポスター写真など,有りとあらゆる物が並べられており,見ていて楽しい.
それも,非常にマニアックな奥の深い雑貨が並べられており,建築都市の部門では「コルビジェを歩こう」という本があったり,お菓子ではキムチ焼きそばやドクターペッパー,懐かしのスプライトやカナダのジンジャーエール,ビンのコーラ,アメリカの年代物のジュークボックス,郡山出身のロック歌手のCD,物珍しいインテリア商品,ドクタースランプあられちゃんの漫画,旅のコーナーでは香港の九龍(カオルン)城の写真集があったりと,各分野マニアックでその筋の世界のことをよく知っている人にとっては,興味のそそる品揃えをしていると感じる.見ているだけでも飽きない店である.
ちなみに,郡山ではこの他に駅前のアティー(前西武百貨店)5Fに店を出している.
郡山市にも「熱海」と呼ばれる地名がある.本場,静岡県の熱海と同じく温泉が湧き出る温泉街で,こちらの熱海は頭に「磐梯」がついて「磐梯熱海温泉」となっている.泉質は単純泉,単純硫化水素泉で,胃腸病,皮膚病,リューマチ,婦人病,神経性諸疾患に効能がある.ここに,郡山市観光振興公社が運営する複合温泉施設「ユラックス熱海」がある.日帰り温泉入浴施設の他に,レストランや会議室,3000名収容の大ホール,温水プールにスケート場,トレーニングルームなどが備わる施設である.入浴料は,1回400円(休憩室利用の場合は1日1000円)と破格の安さで,さすがは公共施設のなせる技である.タオルなどは付かない.露天風呂やサウナもついており,風呂場も広々としている.値段の安さもあって,休みの日は家族連れで賑わっており,休憩室を利用して1日がかりで温泉にやってゴロゴロする団体も多い.
男女の入口が別れるところでの,小さな娘1人,息子1人と父母の家族の一コマ・・・・
父 「こっち(男湯)に来るか・・・・」
子 「こっち(女湯)に行く」
母 「ほら,お父さんから誘いが来ているわよ!」
子 「やだ!」
父 「じゃぁ,お母さん大変だけどよろしくー(笑顔).」
母 「(苦笑い)」
お父さんは子供達と一緒に入りたいけれども,面倒を見るのが面倒くさいので一人ゆっくり入れることに成功(でも,内心寂しい思いをしているのかもしれない).お母さんも,お父さんに預けたかったのだが,子供達と一緒に入ることになった.ユラックス熱海の休日には,このような光景がよく見られる.
郡山駅の東京寄り新幹線高架下に駅ビルのショッピング街「ピボット(Pivot)」がある.この中には17店舗のテナントが入っており,パン屋や総菜屋,食料品,飲食店などがあって,駅前において食料品などの買い物ができる場所となっている.この中でお気に入りの店がいくつかある.
まず,輸入食品を扱っている「ジュピター」.ここでは,世界各国の輸入食料品を扱っており,さながら外国のスーパーで買い物をしている感じになる.手に入れにくい輸入食品はここにくれば大抵揃うのではないか.コーヒーや紅茶を始め,各種のチーズ,パスタ,タイなどのエスニック食品,中華材料,香辛料など豊富に品揃えがある.ベルギー王室御用達のゴディバのチョコレートが人気商品だとか.買う物がなくても,なんとなくふらっと立ち寄ってしまう店である.
次に立ち寄るのが一番奥にある「食品館」.一見するとワンフロワーでスーパーのように品物が並べられているのであるが,野菜・果物屋,肉屋,魚屋の3店の販売区画が厳密に区切られており,それぞれの品物は,それぞれのレジに持っていって精算しなければならない(現在は共同になった).つまりキャベツと鶏肉を買いたいときは,まずキャベツを青果のレジで精算し,そのあと鶏肉を持って肉屋のレジで精算しなければならない.最初はちょっととまどったが,魚屋の鮮魚・刺身などは色つやもよく鮮度の良い商品が並べられ,肉の種類も豊富で量り売りが多い.ここの魚屋「北辰」は,活きが良くて新鮮なことで主婦の間でも評判が高く,はるばる遠くから買い付けに来る客も多いとか.寿司が好きなので,よく魚屋で寿司を買うのだが,面白い商品として「貝づくし(480円)」というのがあって,「ホタテ貝」「赤貝」「ホッキ貝」「トリ貝」「ロコ貝」「ミル貝」の6つの貝だけが入っているセットがある.「貝好き」にはたまらない商品である.
郡山だけの話題ではなく福島県全体の話であるが,2003年10月より福島県の主要なセブンイレブンとイトーヨーカドーにアイワイバンク銀行のATMが設置されるようになり,東邦銀行とアイワイバンクとの間で提携を結んだことにより,コンビニで24時間お金が下ろせるようになった.東京などでは既に導入されていたが,東北では初めてであるとのこと.アイワイバンクは郵便貯金とも提携を結んでいるので,郵便局のキャッシュカードでもお金を下ろすことができ,非常に便利になった.手数料は,東邦銀行のカードでも郵便局のカードでも,アイワイバンクのATMを使用していることになるので,他行で出し入れするときの手数料が適用される.平日の日中は105円,それ以外は210円となる.ただし,東邦銀行のカードは来年の1月まで手数料割引(105円引き)を行っているので,今のところ平日昼間は手数料がかからないようになっている.ただ,ちりも積もれば山となる,手数料は以外とバカにならない.郡山郵便局では平日は23時まで手数料無料でお金が下ろせるし,土曜日は21時まで,日曜日でも19時までやっているので,多少手間がかかっても銀行や郵便局でお金を出し入れする方が面倒くさいけれども得ではある.
郡山駅の新幹線改札口を入ってすぐのところに伯養軒NREが営業する立ち食いソバ屋がある.まぁ,どこにでもある店構えであるが,ここのお気に入りメニューとして「なめこそば」がある.なめこと言うと,みそ汁にいれる小さいネバネバしたなめこを連想するが,ここのなめこは大きな傘をもつ直径2cm位のなめこがたっぷり入ったご当地そばといったところである.これが,あっさりしていてきのこファンにはたまらない.新幹線までの時間にちょっと余裕があるときなど,軽く腹ごしらえをするのにはちょうどよい.380円である.ちなみにこの店は新幹線の構内と,2階の自由通路の両方にカウンターがあるので,新幹線の切符を買わなくても2階コンコースに行けば,誰でも食べることができる.なお,「きのこそば」というのもあるので,お間違えないように.きのこそばでは,色々なキノコが入っているそばがでてきます.
東京に行くのに新幹線は大変便利である.なにしろ郡山から東京駅まで約1時間30分で到着してしまうのだから,移動時間としてはちょうどよい時間である.しかし,ビジネスで交通費がでるならともかく,運賃が高いのがちょっとネックである.大人「普通運賃+特急券指定席」で片道7970円,往復15,940円もかかってしまうのである.しかし,これを少しでも安くする方法がある.それは大宮駅を利用することなのである.
新幹線の特急料金は距離200kmを境に料金が変わるようになっている.郡山-東京間は226.7km,郡山-大宮間は196.4kmであり,それぞれ指定席特急料金は,東京駅までが4,080円,大宮駅までが3,030円となる.つまり,大宮駅で下車すると,片道1,050円,往復では2,100円も安く済ませることができるのである.これを利用すれば,往復13,840円で新幹線に乗ることができる.時間的な視点からも比較をしてみると,実は大宮・東京駅間は騒音問題による周辺住民との協定により,最高時速が110kmに押さられているため,思ったよりも時間がかかり,26分の乗車時間となる.一方,東北本線や高崎線の在来線を利用した場合の乗車時間は,上野・大宮駅間でなんと25分なのである.つまり,東京から大宮までは在来線でもさほど時間が変わらないのであり,大宮駅で新幹線を下車して,在来線に乗り換えて東京に向かった方が,大変お得になるのである.新宿や渋谷方面に向かうのであれば,大宮で埼京線に乗り換えれば,快速で30分程度で池袋まで行くことができる.
さらにお得な方法として,指定席のついた新幹線特急回数券のばら売りを利用する方法がある.これは,6枚綴りで売られている回数券を金券ショップなどでバラで購入するのである.これを利用すると大宮駅までの切符では,片道約5,800円(往復11,600円・金券ショップによって値段が違う)で購入することができる.ただし,回数券を利用する場合は大宮駅までのきっぷなので,都内の下車駅では精算することになる.しかし,ここでもお得な方法があって,大宮から先の東京方面では「特定区間運賃」が設定されているため,通常の運賃計算表ではなく,さらに安い運賃計算表を用いて計算される.そうなると,とおしで郡山から東京都内までの切符を買うよりも,大宮でわざわざ一旦下車して都内までの切符を買い直した方が,実は安くなることが多いのである.ちなみに,大宮駅から東京駅までの片道運賃は540円(往復1080円)となる.大宮駅までの回数券バラ売りを使用して東京駅で大宮・東京駅間を精算をした場合は,往復12,680円となるのだから,回数券のばら売りを利用して下車駅で大宮駅からの運賃を精算する方法が,一番安いということになる.ばら売りの回数券が買えなくても,自由席の特急券で大宮駅乗り換えを利用すれば,指定席回数券のばら売りとそれほど差はなくなるので,突然の旅行の時でも自由席で大宮駅乗り換えの方法はお得である.
| 乗車券 | 特急券 | 運賃 | 備考 | |
| 郡山-東京(普通乗車券) | 郡山-東京(指定席) | 往復 15,940円 |
||
| 郡山-東京(普通乗車券) | 郡山-大宮(指定席) | 往復 13,840円 |
||
| ◎ | 郡山-大宮(回数券) +大宮・東京間の普通運賃 |
郡山-大宮(指定席回数券) | 往復 12,680円 |
下車駅で精算のこと 金券ショップで5,800円で購入の場合 |
| 郡山-東京(普通乗車券) | 郡山-東京(自由席) | 往復 14,920円 |
||
| 郡山-東京(普通乗車券) | 郡山-大宮(自由席) | 往復 12,820円 |
うすい百貨店は郡山を代表する地元百貨店である.創業は江戸時代の寛文2(1662)年の物産問屋が前進で,1967年に地元デパートを買収してうすい百貨店を設立したものである.当時は大変な賑わいだったというが,郊外への大型店の出店により客足は減少していた.そこで,1999年に駅前再開発事業に合わせて全面リニューアルし,地上11階建て地下1階の売り場面積31,500m2の東北最大級の売り場面積をもつデパートに生まれ変わったのだが,長引く景気低迷も影響し売り上げが伸び悩んでおり,産業再生機構の支援が決定した.
福島県の消費文化の向上には,うすい百貨店の存在は欠かせない.なにしろ高級ブランドである「ルイ・ヴィトン」や「ティファニー」,「シャネル」,「クリスチャンディオール」などの店舗が入り,地下の食品売り場では「京都鼓月」や「自由が丘ポエムドメリー」,「赤坂トップス」など全国の銘菓が並べられている.地下では,いわきの「メヒコ」も出店しており,あの名物「かにピラフ」を買うこともできる.
個人的によく足を運ぶのが9階の「八重洲ブックセンター」.ちょっとした本を東京で買うときは,神田神保町などに足を運んで探してみるが,最後には東京駅八重洲口南口の八重洲ブックセンター本店で買うことが多い.というのも,この本屋は本の分類による陳列が非常によくまとめられており,目的の本をわかりやすく並べてあり見つけやすい.これは店員の「目利き」によるところが大きいと思われる.郡山店の場合は,本店ほど整然と並べられていなかったが,専門書も含めて本の種類の多さでは郡山でも最大級の方であるように思う.(その後平成16年12月の大塚家具の出店と同時期に,八重洲ブックセンターの専門書などのコーナーは無くなってしまい,売り場面積が半分くらいになってしまった.普通の本屋と変わらなくなってしまった.場所も10階に移動.)
うすい百貨店は,是非再建計画による再生を乗り切ってもらいたいデパートである.
「お帰りなさい,故郷へ」のCMでおなじみの柏屋である.「かんのやのゆべし」を紹介したからには,「柏屋の薄皮饅頭」を紹介しないわけにはいかない.「かんのや」が東の横綱だったら,「柏屋」は西の横綱と言ったところか.柏屋と言えば「薄皮饅頭」である.
柏屋(本社:郡山市)の薄皮饅頭は嘉永5(1852)年に,柏屋の初代である本名善兵衛 が、奥州街道の宿場町として賑わった郡山で薄皮茶屋を創業したのが始まりである.以来150年にわたり少しずつ味を変えながら,市民に愛されている銘菓なのである.
個人的には「あんこ」よりも「皮」の方が好きなので,「薄皮」などと聞くとゾッとするのであるが,あんこが大好きな饅頭ファンにとっては,大変うれしいウスカワである.「こしあん」と「つぶあん」の2種類があり,好みのあんこを選ぶことができる.写真左が「こしあん」で,写真右が「つぶあん」である.郡山駅や市内のイトーヨーカドー系のスーパーでは大抵販売している.

中通りは新幹線が縦断して走っている.北海道・岩手に次いで,日本第3位の面積を誇る福島県は,「会津・中通り・浜通り」と3地方に分けられている.県内に転勤になったときに,中通り地方圏内は新幹線が通っているおかげで自宅から新幹線通勤を行うことができる地域なのであるが,結構平日の朝や夕方にホームに行くと,かなりの数のサラリーマン達が自由席乗り場に列をなしており,こんなに新幹線を利用している人が多いのかと驚いてしまう.今は,2階建てのMAXが主体となっているので,座れないことはないそうだが,最も利用客が多いと思われる「郡山から福島まで」はたったの15分という早さ.寝ている暇もないほどの乗車時間である.
この「15分」という時間であるが,飲み会などで酒を飲んだあとに乗る場合は,気を付けなければならないのだという.つい,うとうとと寝てしまうと「OUT!」 気がつくと仙台だったり,気がつくと宇都宮だったりと,ひどい人の場合は大宮だった,なんてこともあるらしい.乗り越しの経験は誰でもあると思うが,新幹線の場合,乗り越しによる移動距離の度合いが桁外れになってしまい,戻るにも料金がかなりお高くつくという欠点がある.通勤電車で2~3駅といった次元とは話が違うのである.
郡山・福島間の新幹線通勤定期代は52,450円(H15.8現在)となっている.今は東北本線の在来線よりも,新幹線のほうが本数が多く便利になっており,最終も23時頃着まで走っている.
最近東京進出を果たしたラーメンチェーン店の「幸楽苑」であるが,本社は郡山市に存在する.福島県で数少ない東証1部に上場を果たしている企業である.福島県民にとっては「会津っぽ」という店名のほうが馴染み深いのであるが,低価格な品揃え(中華そば390円)とバランスのとれた味が大ヒットし,平日はビジネス客で週末は家族連れでいつも混雑しているラーメンチェーン店である.もともとの創業は,城下町「会津若松市」に味よし食堂として昭和29年に開業したのが始まりで,その後事業を拡大するために会津若松に工場を建設していったが,徐々に工場や本部を郡山市田村町へシフトし,現在に至っている.北は秋田県,南は静岡県まで展開しており,最近関東地方への進出を果たした.
全国展開をするにあたって「会津っぽ」という名前をやめて,「幸楽苑」という店名を全面に出すようにしている.会津若松生まれで会津ファンの僕としては,会津で創業したラーメン店なのだから「会津っぽ」という店名を残して事業展開して欲しかったが,麺の太さは会津で食されているものとはちょっと変えており,日本国万民に愛されるように中太の麺(いわゆる東京の人にとっては普通の麺)となっている.そういう意味では会津ラーメンとは言えないラーメンが今は出されているのかと思うが,多加水熟成麺という製造法は同じである.会津ラーメンは,ご存じ「喜多方ラーメン」と同じく太い縮れ麺で,あの太麺を食べないと僕なんかはラーメンを食べた気がしないのであるが,地元の商店街(特に若松の方)では「会津ラーメン」と「喜多方ラーメン」は違うんだ!と頑固に主張している人もいる.会津で食されているラーメンは喜多方ラーメンと一緒であると思う.ただ,昔の幸楽苑の味を知る40歳代以上の方がこの「会津っぽ」のラーメンを食べると,「そのまま昔の味を再現していて懐かしい」と言う声が聞かれる.
なにはともあれ,会津若松で生まれた幸楽苑のラーメンが,いまや東日本にチェーン展開される大きなラーメン店に変貌し,福島県を代表する大企業に成長しているのであった.(幸楽苑ホームページ)
郡山駅前アーケード商店街の一角(駅から見ると中程を右に曲がった一番奥)に「パチンコ名古屋」という地区が存在する.その名の通りパチンコ屋が何軒か並んでいたためにこのような名前が付けられているのだが,近年の郊外型パチンコ店の登場により,ちょっと客足はいまひとつとなっている.アーケード入り口の上部には,「ナゴヤビル御案内・パチンコ名古屋」という看板が掛かっているが,パチンコが駅前にしかなかった時代の往年の賑わいを連想させる風景である.その中の1件に「名古屋ホール」というパチンコ屋があるが,この店は今は設置されていない機種の台を1台ずつ「ずらずら」と並べてあり,その数も2シマにも3シマにもわたっていて,半端ではない様々な懐かしい台が置いてある.すべて現金機で打つようになっており,これまた懐かしの500円や100円玉をいれて玉を自分で手ですくって台に流し込む方式で,台の上には回転数などを示す情報板などはついておらず,呼び出し用のボタントランプだけがついている店である.消して換金率は高くなく,1箱だして3500円程度であるが,かつてのなつかしの台を打ちたいならお勧めのお店である.
福島県で「ゆべし」といえば,三角形の形をした茶色いものを連想する.ゆべしとは,漢字で書くと「柚餅子」となり,味噌・米粉・うどん粉・砂糖・クルミなどをまぜ,柚の実の汁を加えてこねて蒸した菓子のこと(広辞苑より)であるとのことなので,全国各地いろいろな形の柚餅子があってもおかしくない.
このかんのや(本社:郡山市)の柚餅子は歴史が古く,300年以上も昔の江戸時代,三春において戦闘にいく兵士の食料としてつくられたのが始まりで,故事にならって鶴の形をイメージして三角形になっているとのことである.それ以来,かんのやの代表的なお菓子として,現在でも有名になっているのである.姉妹品として,うめあんのゆべし,くろごまゆべし,くるみゆべしなどがある.東京では,三越と伊勢丹などでしか手に入らないお菓子である.

東北の大都市・仙台へ向けて,郡山駅からも高速バスが走っている.福島交通・JRバス東北・宮城交通の3社の共同運行によって運行されていたが,バス事業の自由化に伴って昨年(2002年)の秋に観光バス事業だけをやっていた仙台市の富士交通が参入することになった.高速バスは旅客収入が安定して入ることから,バス会社でもドル箱路線となっているところが多い.ところが,運輸業界というのは駅前乗り入れに関して既得権が幅を利かせていて,富士交通が郡山駅ターミナルに乗り入れたい旨を申し込んだところ,既設の3社から「No」を突きつけられ,駅前ターミナルへの乗り入れが実現しなかった.そこで,富士交通だけが郡山駅ターミナルから離れたアーケードの延びる通り沿いにバス停を設けて運行する羽目になった.
そこで,後発の富士交通は,衛星放送テレビを放映し,バスガイドを乗務させ,お茶のサービスを行うといったサービスをすることとし,運賃も既設会社よりも安く設定してスタートさせた.運賃については,既設3社も値下げを行って対抗処置を施し,現在は片道の運賃については同額となっている.郡山仙台間の高速バスは既設3社も新規参入の富士交通も,どちらも1時間に1本程度の割合で運行されているのであるが,仙台駅の乗り場は既設3社も駅前ターミナルから発車しておらず,仙台駅では富士交通も既設3社の隣にバス停を置くことができた.これを最大限に利用して過激な営業戦略を行っており,なんと面白いことに富士交通のバスは発車時間を,既設3社の10分前に発車するように設定したのである.発車前にはきれいな(!?)バスガイドがハンドマイクを使って,「富士交通の郡山行き高速バスはこちらです」と,既設3社のバス停に並んでいる客に向かって案内し,乗客を呼び込むというすごさ.これでは,既設3社も黙っていられまい.
運賃は片道1800円で,これは両者とも同じ料金なのであるが,既設3社は3枚綴りの共通回数券を販売(片道1枚あたり1500円)としているが,富士交通は回数券を発行せずに往復割引(往復で2600円,つまり片道あたり1300円)で対抗している.既設3社が3枚綴りとしている点はミソで,これは富士交通に軍配を上げる枚数であるように感じる.つまりたいてい高速バスは往復で使用することが多いと思われ,3枚だと最後の1枚が余ってしまうことと,余った1枚を次に使用したときは,また帰りの便に乗ることが予想され,「帰りは回数券も切れたしお茶のでる富士交通に乗ってみようかな?」と思わせてしまうのではないか.(平成16年1月現在,既存3社の3枚綴りの回数券は2枚綴りに変更され,さらに片道1枚あたり1300円に値下げされた.これに伴って,新規参入2社は回数券の片道1枚あたりの値段を更にさげて,1200円としている)
まぁ,なにはともあれ運賃が安くなることは大歓迎であり,これからも大いに安くなって欲しいと願うところである.ちなみに富士交通は,福島・仙台間にも高速バスを展開しており,こちらはJR東日本の電車も巻き込んで,JRでは快速電車の増発や普通運賃よりも安い往復割引切符を発行するなどし,競争が激化過熱している.
今でも郡山のことをこのように呼ぶ人は多い.かつての郡山は暴力団による発砲事件が多く発生しており,治安があまりよくなかった.犯罪統計などを見て比較しているわけではないので実際のところはわからないが,人口30万人の都市であることを考えると,人口比では発砲事件発生率は高いのかもしれない.かつて,歩道に落ちている拳銃を通学中の小学生が拾ったとか,暴力団同士の抗争事件が多発していたとか,昭和3~40年代の頃からこのように呼ばれている.
最近は発砲事件も昔ほどではないらしく,郡山以外でも全国的に不可解な凶悪事件が多発していることもあって,東北のシカゴという印象は薄れつつあるが,このように呼ばれるのも都市活動が盛んである郡山を端的に表現しているように感じる.また,別の意味合いとして,商業活動が盛んなために「東北のシカゴ」と呼ばれるようになったという褒められる意味の解釈をしている人もいるようだが,これは間違いで,本来は事件の多い都市であるという汚名の代名詞なのである.
ところで,アメリカのシカゴとはどういうイメージの都市なのか.かつてのシカゴは,アンタッチャブルという映画に出てくるギャングのボス・アルカポネが1930年代の街を闊歩するマフィアの都市というイメージがつきまとっていたのかもしれないが,シカゴ=犯罪都市という図式があったのは間違いないようである.「東北のシカゴ」とは,シカゴにとってもいい迷惑な代名詞ではある.
でも,「東北のシカゴ」などと言われると,どことなく格好良く聞こえてしまうのは不思議である.郡山出身の人が「郡山は東北のシカゴだぜ!」などと言うと,平和な地域が多い福島県の中でも経済都市No.1を自負する「気合い」が感じられ,まんざらでもない様子である.
郡山からも各方面へ高速バスが運行している.中通り地方は福島交通というバス会社がバス事業を展開しており,各方面へ路線を運行させている.東京方面にも高速バスが走っており,「あぶくま号」という名称がつけられている.郡山は東北新幹線が走っているので,東京までの移動時間では勝負にはならない.新幹線に乗ってしまえば東京駅まで1時間30分程度でついてしまうのである.やはり勝負は値段の安さであり,JRの普通運賃程度で東京まで行けてしまうことが魅力であろう.新幹線では東京駅まで片道7480円(自由席)であるが,高速バスでは往復割引を使って7500円となっている.
郡山駅始発のバスもあるが,福島駅が始発となって二本松を経由し郡山駅にやってくる便もある.福島駅から乗車すると新宿駅まで約5時間20分もかかるので,福島駅から乗車する人は少ないようである.時間と体力があって金欠ぎみのときに高速バスを利用するように感じる.いわき東京線ほど本数が多くないのは,この乗車時間の違いによるものであると思われ,郡山駅から新宿駅までも約4時間かかるので,値段は高いが時間が短い新幹線を利用する乗客は多い.いわきの場合は,JRの特急スーパーひたちの時間とバスの時間がこれほどまで差が大きくなく,かつ乗車時間が3時間程度であり,さらに充実したパークアンドライドを行っているため,東京便の利用客が大きく伸びているように感じる.
郡山駅を出発すると須賀川に停まってから高速自動車道に乗り,高速自動車道上にある白河の西郷バスストップに停車して新宿駅新南口に向かう.東京では,JR京浜東北線の王子駅に停まり,明治通りを通って池袋駅東口の三越裏に停まってから新宿駅新南口(高島屋の下)に向かう.新宿駅周辺の大渋滞はすごいようなので,手前の王子や池袋で下車するほうが賢明である.
ちなみにこの「あぶくま号」は全席指定となっているが,席の配置は原則的に男性と女性が一緒にならないよう販売されている.いつも隣りに座っているのが「あぶらっこいおじさんばっかりだ」という理由はここにある.なお,販売の状況により例外もあるのでご注意を.
中通りで地元の方(特に40代以上)と話をしていると,会話の途中や語尾に聞き慣れない「間投詞」が入ることがある.同じ福島県内である「会津」や「いわき」でも聞くことはないその言葉とは,「はぁ」と「ばい」である.
これだけだと何のことやらさっぱり解らないと思う.
「はぁ」という言葉は「さー」とか「○○ね,」というのと同じ意味合いで使われているらしく,例えば,
「北海道に行ったらさー,熊に出会ってびっくりした」
などというときは,
「北海道に行ったらはぁー,熊に出会ってびっくりした」
など使われたりする.この「はぁ」は語気を強めて話をすることが多く,聞き慣れないうちは,突然「はぁ」などと言葉が入るのでなんだろうか,と思ったりしたものだった.
そして「ばい」.これは会話の語尾に付けられる言葉で,
「昨日,駅前のパチンコ屋に行ったでしょ」
などというときは,
「昨日,駅前のパチンコ屋に行ったばい」
などと語尾に付けられる.どちらも中通り,特に郡山近辺で聞かれる言葉のようである.
郡山が本格的に発展したのは明治に入ってからである.大槻原(現開成山)一体の開拓を行うにあたってかんがい用水が必要であり,そこで日本第4位の広さを誇る「猪苗代湖」から奥羽山脈を超えて水を引き,開拓を行ったのが始まりである.安積疎水については,郡山の歴史を語る上では外せないものであり,また後日のコラムで説明することとしたいが,その開拓が国の直轄事業として認められることが決まると,明治11(1878)年より九州の旧久留米藩士から入植が始まり,松山藩や土佐藩,岡山藩や鳥取藩など全9藩,約2000人が郡山に移ってきたのである.九州の人の街頭インタビューをテレビで見ていると,訛りが似ていると感じるのはここにルーツがある.
江戸時代に最も反映していたのは会津若松であるが,ご存じのように幕末の悲劇によって「賊軍」の汚名を着せられて,会津は解体されてしまい,会津は明治になってからそのまま繁栄を受け継ぐことが難しくなっていた.東北の大動脈は奥州街道(東北本線)となり,交通の利便性もあって,郡山は様々な地域から人が集まってきて,どんどんと発展していったのである.つまり,郡山の歴史は北海道と同じであり,入植者のフロンティアスピリットによって形成されてきた街なのである.
あまり個性や特徴のない「郡山」との印象を受けるのは,入植によって新しく作られた街であることから起因しているのであろうと感じる.歴史の重厚さがある「会津」とは対照的である.そのようなことから,郡山に住む人々はあまり土着的なベタッとした感覚はもっておらず,物事の考え方に都会的センスを持っている.福島県は,歴史の重みがある「会津」,海の広がる「いわき」,そしてフロンティアスピリットの街「郡山」と,都市のコンテクストを考える上でも,非常に興味深い三者三様の街が集まっている県なのである.
郡山は福島県の経済の中心地である.県庁所在地は福島であるが,福島市よりも郡山市のほうが経済的には大きい.「福島市」が官庁街のワシントンなら,「郡山市」は商業の中心地ニューヨークといったところだろうか.人口は約30万人,東北新幹線が通り,南北に東北自動車道,東西に磐越自動車道が走る,交通の要所でもある.一見,地味で特徴のない「郡山」(実際,福島県では会津の個性が強く,全国的にも会津のほうが知名度が高い)のように思えるのだが,福島随一の都会とあって,商業やサービス業は充実している.これから,郡山の見聞録をシリーズで掲載します.お楽しみに・・・・
(このページは2003年に記載されたものです)
(このページは2002年~03年3月に掲載したものです)
毎年夏の終わりに三崎公園野外音楽堂で恒例のフェスティバルが開催されている.県内外のアマチュアバンドがあつまって演奏を行う「ミュージックカーニバル」である.1989年ジャズフェスティバルと題して行われたのが最初で,今年で13回目となり,当初7組だった出演バンドも20を数えるまでに成長した.なんといっても,普段はサラリーマンや自営業を営なみながら音楽をこよなく愛する人々が年に1日だけ演奏できるイベントとあって,ステージと会場との間に高い壁がなく,お互い一体となって踊りながら音楽を楽しむこともできる.いわき地方の音楽文化の育成に大きく貢献しているイベントである.会場内では,やきとりやビールも販売しているので,太陽の降り注ぐ会場で,ビールを飲みながら,日頃の成果を堪能するのも悪くはない.
先日襲った台風21号.戦後最大級とのふれこみで,天気予報でも警戒を伝えていたが,午後9時頃までは平穏な天候で本当に台風が来ているのだろうか,程度のものであった.このままちょっと雨と風が強くなって過ぎ去っていくだろうと思っていた.ところが,午後10時頃になると,突然突風が吹くようになり,雨足が強くなってきた.それが段々と更に強くなり,鉄筋コンクリートのこの建物が壊れるのではないかと思うくらい,突風が続いていった.外を見ると,発泡スチロールやダンボールなどのゴミが空を舞い,雨が波打っていた.隣の塀の柵が倒れた.すると,電気が消えた.と思ったらすぐついた.また消えた.またついた.これがしばらく繰り返されたあと,ついに電気はつかなくなり停電となる.
風による轟音と雨音が真っ暗な中で響く.身の危険を感じてしまう.懐中電灯とラジオを付けて,外を眺めた.部屋の中を暗くすると,外はよく見えるようになる.火花がスパークして空が明るくなる.電線が切れているのだろうか.海に浮かぶ船はライトを照らしている.すさまじい風と雨である.すると,ぴたりと風と雨が止んだ.台風の目に入ったらしい.本当にぴたりと止まった.そしてしばらくするとまた風が吹き出した・・・・.いっこうに電気がつく気配がないので,そのまま寝ることにした.
翌日,信号機は曲がり,店先の看板が落ち,ビニールのひさしは破れ,柵は倒れている.最大瞬間風速は48.1mであった.道路上にはどこから飛んできたのかコンクリート片の崩れた残骸のようなものが落ちており,ドラム缶がゴロゴロと転がっている.久々の台風らしい台風であった.おかげで,車は潮だらけ.葉っぱやワカメがこびりつき,空から海水が降ってきたのであった.
メヒカリとはいわき市の魚として認定された深海魚である.詳しくはNo.37の項目で記しているが,この「目光」にかけて,いわき市民総ぐるみ・秋の交通安全運動「目光り大作戦」が実施されている.その内容は,「昼夜を問わずライト点灯の目光り運転を実施しよう」というものである.トラック業界ではかねてよりライトを点灯しながら運転していたようであるが,ライトを点灯しながら運転すると昼間の事故が減少したという報告を受けて,いわき中央・常磐地区交通安全協議会・安全運転管理者協会・事業主会・警察署によって,いわき市全域でライト点灯の運動を展開しているものである.
効果として,①相手に自車の存在を早く知らせることができる,②カーブミラー内の車は確認しやすい,③遠くにいても早く気がつく,ことが挙げられている.ただし,その運動を行っていく上での対策として,①対向右折車が道を譲ってくれたと勘違いする,②消し忘れと思われパッシングされる,③降車時にライトを切るのを忘れることなどが挙げられている.
市内では,率先して官公庁や事業所においてライトをつけて走っており,ライトをつけて走る車をポツポツ見かけるようになった.しかし,9割方はライトをつけて走ってはいない.交差点では「ライトを点灯して走行」などと書かれたプラカードを持って,市民に浸透させようと広報活動を行っている.初めのうちはよくパッシングされたが,今はライトをつけていてもパッシングされることはなくなった.職務上の運転としてライトをつけることには抵抗を感じないが,個人の運転時にはバッテリーが消耗しそうで,何だかつける気はならない.どこまで,浸透していくのか,今後に注目である.
年末も近づき,3連休には大混雑する高速バスである.安さが魅力の高速バスだが,最近はJRも休みの日に限って2日間有効の「週末東京フリー切符」というものを発売し,巻き返しを図っている.このJRのフリー切符はなかなか優れもので,スーパーひたちの往復指定席特急券と東京近郊乗り放題のフリー切符がセットになったもので,往復7500円で販売(前日まで購入)されている.高速バスよりは高いが,JRを使って都内で乗り降りする場合や電車のゆったりした空間と時間の早さを考えれば,妥当な値段である.通常の特急指定席では往復12000円程度するので,JRも高速バスを意識した相当の割引を行っていることになる.ただし,これは期間限定で2002年11月30日までとなっているが,かつては冬の期間(12月~3月)のみで販売していたものを,今年から夏まで延期したという経緯があり,今回もおそらく期間が延期されて発売されることと思う.
さて,2001年の4月より増便され,いわき発の最終が20時,東京発の最終が22時となった(2003年5月よりさらに3往復増便となり,30分おきの時間帯が増えた).さらに.金曜日のいわきから東京行きの夕方便はいつも満席で,20時発ができたことにより金曜日の乗りこぼしはなくなった.金曜日のいわき20時発のバスは,初めのうちはガラガラで半分も乗っていなかったのであるが,最近はだんだんと知れ渡ったのか,満席とはならないが結構混雑するようになっている.東京22時発の最終は,ナイターやお芝居,コンサートなどを見終わった後でも乗れるとあって,休みの日には満席となる.どうしても乗りきれないときは補助椅子にも乗客を乗せている.いわき着は午前1時であるが,1泊するよりは帰ったほうが安上がりとなるので,利用客が多いのであろう.
ちなみに,休日の東京駅15時30分以降のバスは,たいてい混雑して満席となる.そのため,2台に増便しているのであるが,2台増便は19時までとなっている.19時発になると,いわき到着が22時頃となるため,連休などの混雑時を除いては,半数くらいしか乗車しておらず,結構穴場の時間である.19時30分以降になると1台運行となっていることが多く,結構混んでいて満席に近い状態となっている.19時発は「狙い目」である.
上矢田交差点とは,いわき市を南北に貫く国道6号と,福島県を東西に結ぶ国道49号がT字型に交わる交差点である.つまり国道49号の起点なのであるが,国道の幹線であることもあって大型車が多く通行する交通量の多い交差点となっており,平面交差の信号機による交通制御であるため,この交差点が引き金となって朝夕のラッシュ時などは大渋滞を引き起こしている交差点なのである.そこで国土交通省によって立体化工事が進められており,今年(2002年)の12月17日に供用開始予定として,急ピッチで工事が進められている.この立体化が完成すると,高速のジャンクションのようになって(一般国道でこのようなジャンクション型の立体化が行われるのは福島県初だという),信号機のないスムーズな分岐と合流ができるようになり,渋滞が大幅に解消されると予想される.現場には「12月供用(予定)」とデカデカと書かれた看板が掲げられ(「予定」と入っているところがミソであるが),もうじきあのノロノロの慢性的な渋滞から解放される日が近づいているのである.
国道49号から国道6号に向かう場合,地形的な方角は左側が四倉・原町方面で,右側が日立・東京方面なのであるが,スペースや構造上の問題もあってか,新しい立体化後には右車線が四倉・原町方面となり,左車線が日立・東京方面となるような車線構成となる.日立・東京方面の場合,左車線で陸橋になっていったん左にふってから,右に大きくカーブながら原町方面の車線と国道6号をオーバークロスして合流するようになる.つまり,地理的な方向と逆の車線を走らないと,目的に向かうことができないのである.初めのうちは戸惑うドライバーが多いような気がする.東京方面に行こうと思っている人が,右側が東京だろうと思って右車線をスピードを出して走っていたら,実は左車線が東京方面であることに気づき,急に車線変更をして事故を起こす・・・・.最悪の場合,周辺の景色は単調な山林なので,間違って走っていることに気がつかず,四倉まで行ってから気がつくといった事態もありえるかもしれない.(余談だが,北陸道から新潟に向かうとき,長岡ジャンクションが同じような構造で,越後湯沢・高崎方面と新津・新潟方面が地理的方向と逆車線の分岐となっていて,間違いが多い)
国道バイパス交差点の完成のときには,看板をよく見て間違いないように走行しましょう.国土交通省磐城国道工事事務所のホームページには詳しい情報が掲載されています.
クリスマスシーズンも近づき,街のあちこちでイルミネーションが見られるようになった.小名浜港の2号埠頭にあるアクアマリンふくしま水族館では,駐車場前にある7本の街路樹に電飾を取り付けられて,幻想的なイルミネーションを点灯してクリスマスムードを盛り上げている.さらに街路樹以外にも,アクアマリン館内1階のエントランスホール天井や,ラッコやトドなどがいる天井の柱にも電飾を三角形に配し,外からももガラス張りの館内がチカチカ光るように演出されている.港湾道路(市民の間では「産業道路」と呼ばれている)を大剣から三崎方面に走っていると,右側にきれいに点灯したイルミネーションを見ることができ,殺伐とした港湾の風景に心の灯火を与えている.ただし,商業施設がほとんどないアクアマリンパークなため,せっかくイルミネーションが点灯し,さらに日頃からライトアップもされているにもかかわらず,人の気配がまるでない.あまりにも「ひとけ」がなくて,ちょっと歩くには不気味ささえ感じてしまう.是非とも,デートのできる洒落たバーやレストラン,ショッピングモールなどが欲しい小名浜港である.イルミネーションは12月25日まで点灯している.
国際線の飛行機に乗ると,前方の大画面には映画やニュースの合間に,GISを利用した世界地図に今まで飛んできた航路の軌跡と,現在の航空機の位置及び方向が示されるようになっている.地図は全世界の大陸が載っている縮尺の小さい地図から,主な地名まで明記された縮尺の大きい地図へと,交互に表示されていくのであるが,日本列島の上空を飛んでいるときに,ふと日本地図を眺めていると,「仙台(Sendai)」,「東京(Tokyo)」の二つの点の他に,どういうわけか「磐城(Iwaki)」のポイントが掲載されているのである.仙台と東京の真ん中あたりでちょうどよかったからなのか,とにかく「いわき」の名称が日本を発着する国際線の中で,世界中の人々の目に止まっているのである.しかも,ひらがなで「いわき」と表記されずに,「磐城」と表現されているところなど,どうも日本の地理に詳しくない人がシステムを構築したのではないかと思えるのであるが,漢字で表記されているほうがなんか「渋い」!! アメリカ大陸から太平洋路線で日本に向かうと,ちょうど磐城あたりから高度を落としていく.矢祭あたりには航空管制用の信号基地があるらしいので,航空関係者の間では,「磐城」は位置を把握する上で重要なポイントにでもなっているのだろうか?
知る人ぞ知る昔ながらのパン屋さんである.小名浜の本町通りを江名方面へ走っていき,旧東邦銀行の隣(小名浜駅のバス停付近)にあるのが飯塚パン屋である.店に入ると「プーン」と焼きたてのパンの香りがして,奥の方ではパン作りに忙しそうに動くおばちゃんたちがいる.なんといっても手作りのパンは,昔ながらのガラスのショーケースに,ひとつひとつ丁寧にラップに巻かれておかれており,夕方でもお客さんが並んで購入するほどの人気ぶりである.これが,結構うまい! メロンパンなんて,パンの中にメロンのソースが入っていて,なんとも言えないおいしさ.あんぱん,うぐいすぱん,チョコレートパン,カツサンド,食パン・・・・,いろいろなパンを売っている.スーパーのような画一的で無味乾燥とした感じではなく,見ただけでもひとつひとつが「手作り」という風に感じ取れるパンで,実際,食べてみても手作りの味で美味しい.なお,1日おいてしまうと固くなってしまうのも特徴である.是非,ご試食を.
なお,もう一度繰り返すが,飯塚のパンは昔ながらのパン屋であある.「クロワッサン」というパンはコッペパンに赤いハムが挟んであるパンだったりする.都会的なセンスの「ブレッド」を好む人には向いていないパン屋である.
小名浜の商業中心地は寂れてしまった・・・.それを最も感じ取れるのが小名浜ショッピングセンター跡地である.かつて小名浜には二つのショッピングセンターがあって,今はつぶれてしまって閉鎖されている「小名浜ショッピングセンター」と,現在は「タウンモール・リスポ」と呼ばれている専門店街が入る「名店街」と二つの大きな商業施設があった.休日となると大勢の買い物客で賑わっていた.この二つのショッピングセンターは,昭和40年代の中頃には既にオープンしていたといい,噴水のある中庭や透明な展望エレベーター,イベントを行えるスペースなどを備え持ち,当時としては画期的な大型ショッピングセンターであったに違いない.商業センターの先駆けとして,先見性をもった施設であったはずである.今でも,タウンモール・リスポを歩いていると,ちょっと圧迫される空間の中に,ショッピングセンターのエッセンスを「ぎゅっ」と詰め込んでいる感じを味わうことができ,旅好きの僕としてはちょっと興味のそそる空間である.東京・青山にある「ベルコモンズ」というショッピングビルも,昭和40年代頃に出来たのであろうと思われるが,やはりこのような圧迫感のある空間を持つ商業デパートである.
今は,鹿島に近代的で空間の広々としたきれいなショッピングセンター「エブリア(専門店街)」と「ダイエー」がオープンし,大きな駐車場も兼ね備えていることから,たくさんの買い物客で賑わっている.小名浜ショッピングセンターに入居していた商店も,この新しい鹿島ショッピングセンターに移転した店主が多かったため,閉鎖を余儀なくされたとのことである.これも,時代の流れである.でも,ちょっとした買い物をするのなら,タウンモール・リスポも結構便利である.いつ行っても空いていて,駐車場にもすぐ車をとめられる.僕は,お茶っ葉「宇治」を買うときにリスポの「高木園」(実は鹿島SPにも高木園はあって,ソフトクリームが人気となっている)に行っている.高木園ではお茶を買うと,お茶1杯がサービスで出される.ちょっとした楽しみである.やっぱり日本人は,ジャパニーズ・ティー(日本茶)である.
No.68で飯塚のパン屋を紹介したが,そことは全く正反対といってもいい雰囲気のパン屋が「ブレッドガーデン」である.場所は,ヨークベニマル小名浜店の裏手の道路を泉駅方面にちょっといったところに「ちょこん」とあるお店で,フランスパンやクルミ入りの欧風田舎パンなど焼きたてのパンを売っている.毎日焼くパンの種類が違うので,お店に置いてあるパンの種類と焼き上がり時間のカレンダーを持って帰ってチェックする必要がある.このパン屋さんは,都会的な味を好む人には定評があり,いままで東京でパンを購入していたというこだわりの人が,ここのパン屋なら東京の一流の味と同じだといって買っていくとのこと.
実際食べてみると,なかなか不思議な形のパンと,香ばしいパンの焼けた外皮の味と,もちもちとした食感がたまらなく,繰り返し足を運びたくなる味である.しかし,そんな人気店ゆえ,売れきれるのも早く,午後3時頃いってみると,ケースの中にはほとんどパンがなく,本当に営業しているのかと疑いたくなるようなディスプレイになってしまう.焼き上がり時間は午前中が多いので,恐らく昼前は行列ができているに違いない.聞いた話であるが,ここのご主人は面白い方で,「俺の焼いたパンは日本一うまい!」,とパンにかける情熱はすごい人らしい.ここに来たら,菓子パンのような小さなパンではなく,フランスパンやクルミの入った大きいパンを1斤買っていくことをお勧めする.
3年間にわたり連載を続けてきたこのコーナーも,今回が最終回となってしまいました.郡山へ引越すことになり,4月からは郡山での生活になります.「いわき・小名浜」らしい出来事,住んでみないとわからないこと,いわきの情報を少しでも多くの方に知ってもらいたくて,情報を発信しました.まだまだ,お伝えしたいことは沢山あるのですが,時間切れです.
また,このコーナーには色々な方からメールや励ましをいただくことが多く,大変励みになっていました.ご訪問してくださった方々に改めて感謝いたします.今度は「郡山見聞録」なるものを発行しようと考えておりますので,他ページ共々,今後ともよろしくお願いします.
「いわき小名浜」よ,ありがとう・・・・・.
(このページは2002年~03年3月に掲載したものです)
(このページは2001~02年に掲載したものです)
海の近くに住んでいて,奇妙な経験をした.台風や低気圧が近づいていて海が大時化の時,海のしぶきが霧状になってあたりを包み込む.そして,地鳴りのような「ゴー,ゴー」という音が不気味に響き渡るのである.初めのうちは,空の方から響いてくるので,飛行機でもとんでいるのかなと思ったが,荒々としぶきあがる波のうねりの音なのである.滝が落ちるときの音が空に響くので,夜になるとよりいっそう不気味に感じる.まさに,海が鳴いているのである.
「大黒様の宝くじ」として全国の宝くじファンから人気のあった大黒屋百貨店1階の宝くじ売り場.デパートの倒産によって宝くじ売り場も閉鎖されたのであるが,大黒屋デパートの屋上にあった守護神でもある大国魂神社を分社してもらい,平1丁目再開発ビルの1階に売り場が設けられることになった.運営は「平1丁目都市開発」が行い,2002年4月のビルオープンまでは仮設の売り場で販売され,ビル完成後はビル内に移転する.
初日の販売日は9月27日である.
もともと再開発ビルに宝くじ売り場を設ける予定はなかったが,時間が経たないうちにあの大黒様の宝くじ売り場をなんとかしたい,とのことで関係機関と相談の上,4月のオープンを待たずに仮設売り場まで設けてオープンさせることになった.年末ジャンボに穴をあけたくない,という思惑があったのだろう.しかし,仮設の売り場を新聞で見る限り,以前と比べるとやはりお粗末な感じは否めなく,本当に大黒様の御利益があるのかな,ちゃんとお客さんが来てくれるのかな,と思ってしまうのであるが,これは今年の年末ジャンボで1等賞を2本以上だして実績を作る以外にないであろう.実際売り場に行ってみるとどうなのであろうか?近々行ってみようと思う.
いわき民報の新聞には「いわき市のシンボルであり文化だった「大黒様の宝くじ」・・・」と記してある.宝くじ売り場が「いわき市の文化だ」と断言しているところがすごい.石田純一の「不倫は文化だ」に匹敵する名言のような気がする.JRAの福島競馬場を持つ,さすがはギャンブル立県うつくしま,っていった感じである.
いわきに吉牛が上陸したことは,No.35で述べたところである.さらに国道4号の草野付近にも1件オープンし,次第に吉牛勢力が浸透してきている次第である.その吉牛の評判なのであるが,「小名浜の吉牛はまずい! 味が薄い!」といった意見が大勢を占めている.この話は小名浜のどこにいっても聞かれることであり,いわき市民の口には合わない味なのかなと思ってしまう.吉牛の味付けは,おそらく全国統一で,地方地方で味が変わることはないと思われ,事実僕が食べたときはそれほど東京の吉牛と味が変わっているとは感じられなかった.
小名浜でレストランを経営している人が言っていた.「レストランをオープンさせるとき,その地方で「好まれる味」というのがあり,東京で成功した味でもいわきでは流行らない味ということがある,その地域の実情を考えて店を出さなければいけない.いわきでは味の濃い煮魚やしょうゆをたっぷりつけた刺身などが食されてきたところなので,どうも味付けは濃いめの方が好まれるらしい」,と
そうなると,味付けの濃い牛丼が好まれるのも理解できるが,もうひとつの要因として開店当初は大行列ができるほどの繁盛ぶりで,牛丼の肉や汁を次から次へと出さなければならない状態であり,ということは,普段は鍋に入れて暖めておくのである程度水分が蒸発されて,中身が濃くなっているのであるが,その蒸発する時間がなく,結果として薄味と感じられる牛丼が供されていったのではないか.
小名浜でうまい寿司屋は・・と聞くと必ず返ってくる言葉が「松喜鮨(まつきずし)」である.小名浜の中心地の細い路地の中に店があり,いつもにぎわっている鮨屋である.休日にもランチタイムメニューをやっていて,800円でにぎりやちらし,鉄火丼,いくら丼,あなご丼,うな丼などが食べられ,さらにサラダ・かに汁・小鉢がつくのでお得である.ランチのスタンプカードもやっている.ランチ以外でも,新鮮な魚介類を提供してくれるのであるが,なかでもワニの唐揚げやうみぶどうなどといった珍しい一品も出してくれる.特上にぎりは3000円でランチタイムにもかかわらずこれを食べていくお客さんも多い.店員さんたちも夏場をのぞいてはネクタイを着用して鮨を握っており,愛想はないが人間味のあるお寿司屋さんが松喜鮨のプライドとして感じられる.カウンター席のイスには,すべて白のシーツがかけられているのも,松喜鮨ならではといった感じである.ちなみに回転寿司でうまい店は鹿島街道沿い東警察署小名浜寄りにある「源洋丸」,刺身定食のうまい店は源洋丸の隣にある海鮮レストラン「和千荘」であると僕は思う.
いわき小名浜見聞録や小名浜観光情報で殿方が待ちわびていた情報,それが「夜の小名浜」の話題ではないだろうか?
福島県で「夜は小名浜で豪遊だ!」などと言えば,それは必ずソープランド街での湯遊びのことをさす.いわきで酒飲みや宴会で泊まりにきた殿方たちは,1次会で宴が終わったあとに「ちょっと行って来るか」などと言ってタクシーを呼びつけ街に繰り出したりする.小名浜は各地からの船が停泊して発展していった港街だからなのか,福島県で随一の風俗街が形成されていて,約20件ほどの個室付き特殊浴場(都市計画の専門用語ではこう呼ぶ)街がネオンをキラキラさせながら密集して建ち並んでいる.
小名浜には「いわき特殊浴場協会」なるものがあって,新宿歌舞伎町などのようにぼったくり店というのは存在しないようなので,安心して遊ぶことができる.料金は60分16,000円.これはどの店でも共通しているようで,協会で設定されている値段なのであろう.朝9時位から深夜23時50分までの営業が多く,金土日曜日や給料日後などは混雑して2時間待ちもざらなので事前予約をしてくる客が多いという.どのお店が評判なのか?それは小名浜で酒を飲んだときにまわりの客や店員さんから情報を得るか,タクシーの運ちゃんに聞いてみるなどして情報を手に入れましょう.若い子がいる店と,おばさんが出てくる店といろいろあるようなので,情報収集は欠かせない.小名浜の街を走っていて,「小名浜配湯株式会社」なる看板を目にすることがあるが,この会社はまさしくお風呂にお湯を提供している会社なのであった.工場で出た排熱を利用してお湯を供給しているということである.
相変わらず好調のいわき東京線の高速バスである.連休初日の朝の便は4台も増便されていたのであるが,アメリカテロ事件の影響もあってか,国内旅行が復活しているようであり,首都高に入ったとたん大渋滞に巻き込まれ,綾瀬駅到着が1時間も遅れてしまった.首都高の渋滞は葛西まで20kmも続いていたということから,東京ディズニーシーへの行楽渋滞のように思う.
さて,綾瀬駅で降りる場合と東京駅まで行く場合とでは運賃に200円の差がある.この料金設定は非常に良心的だと思うのだが,回数券の場合,綾瀬駅までと東京駅までとを別々に購入しておけばいけないのか,といえばそうではない.回数券は4枚綴りで無期限なので,綾瀬駅までの回数券(表示を正確に言うならば「綾瀬駅から○○円と書かれた回数券」)を使って東京駅からも乗車することが可能で,そのときは乗車時に運転手さんに差額200円を払えばOKなのである.だから,東京に今後も行く予定があるのであれば,割引率の高い回数券を買った方が絶対にお得である.
東京からいわきまでの便は電話予約ができないので,いわきの窓口で予約するか,当日東京駅の窓口で便指定をしなければならない.といっても,連休最終日などの午後の便は混雑し,すぐ次の便には乗ることができず,2~3時間後の便からしか空いていないことがよくある.その時は「キャンセル待ち」をすることができる.窓口でキャンセル待ちの番号札を持ってのりばの先頭で待っていると,空席がある場合に限り,番号順に乗せてもらえる.ただし,キャンセル待ちの時はあとの便の予約をすることができない.つまり,予約していた便より早いバスに乗りたいが満席だったという場合にキャンセル待ちをするためにはあとの便の予約を解除してからキャンセル待ちをすることになる.この辺は「かけ」になるが,予約便が1~2時間後くらいであれば,予約便に乗った方が確実である.たいてい,キャンセル待ちで3~4名乗ることができる.
そして,キャンセル待ちの乗客がすべて乗ったあとにも空席がある場合には,「繰り上げ乗車」といってあとの便の予約をしている客でも乗せてもらえることができる.ちなみに,今までキャンセル待ちを何回かやったとこがあるが,次の便に乗れなかったということはなかった.キャンセル待ちをする客はそう多くはない.
最近は最新型のきれいなバスも投入されるようになっている.そして,常磐交通でも2003年5月より,塗装も新たに新型のバスが投入されるようになった.
福島県は地震保険の等級が一番低い県であり,地震が少ない地域であると言われている.しかし,それは大きな地震という意味であると思われ,事実,いわきに住んでみると,小さな地震がかなり多いことに気づく.福島県の中でも太平洋側のいわき特有の現象なのかもしれないが,震度1~2,ときには3以上の地震が頻発している.震源地は宮城県沖や福島県沖といったものが多く,海のすぐそばに住んでいる僕にとって,地震が起こる度に津波が襲ってこないか不安になったりする.まぁ,地震が多いということは,エネルギーの放出がされているということなので,逆に大きな地震の心配がない地域であるということの証なのかもしれないが・・・.
旧大黒屋デパートの脇に「新川公園」というグリーンベルトがある.ここにある街路樹は,毎年クリスマスシーズンになるとイルミネーションが施され,ムードあふれる公園となっていた.ところが,このイルミネーションは大黒屋デパートの協賛によって電飾の設置と電気代が支払われていたということであり,今年はこのイルミネーションが見れないものと思われていた.ところが,周辺商店街や住民からのボランティアによる募金などによって1本だけイルミネーションが復活したのである.かつては年末ジャンボ宝くじを求める人たちの行列ができ,賑やかな新川公園であったが,今年は人出がさっぱりだとか.イルミネーションだけでも復活させたいという思いが,1本の光り輝くクリスマスツリーとなったのであった.
常磐道湯本インターから小名浜方面に走ったところにある交差点を曲がって,ぐんぐん山道を登っていくと湯ノ岳となる.湯ノ岳は標高593.6mの山なのであるが,ここからの眺めは「素晴らしい」の一言.いわきにこんなに眺望のすぐれた場所があったということに驚きを覚え,もっと早くからこの場所を知っていればと後悔してしまうほど,眼下に広がるいわき市の景色が素晴らしい場所である.煙突からモクモクと煙があがる小名浜の工場地帯があり,その背後には紺碧の太平洋が広がり,いわきの特徴でもある丘陵地の地形が波を打ち,植田の常磐共同火力の大きな煙突が見える.頂上にある展望台からは,いわき市の中心地「平」のビル群が眼下に眺められ,夜になると夜景がとてもきれいでデートスポットとなっている.車で簡単に行くことが出来るので,是非とも一度は足を運んでみるべきポイントである.ただし,冬はカーブなどで路面が凍結しているので要注意であるが,冬の空気の澄んでいるときの方が景色は最高であろう.
福島県は大きく分けて3つの地域に分けられている.新潟県境の越後山脈と奥羽山脈に挟まれている地域が「会津」と呼ばれ,白虎隊や鶴ケ城・喜多方ラーメン・猪苗代湖・スキー場・檜枝岐や尾瀬も会津地方となり,福島県の中では最も全国的に知名度の高い地域である.次に,奥羽山脈と阿武隈高地に挟まれている地域が「中通り」と呼ばれ,県庁所在地の福島・経済商業都市の郡山・最近ラーメンが脚光を浴びている白河と,福島県の動脈となっている地域である.そして,阿武隈高地から太平洋にかけてが「浜通り」と呼ばれている地域であり,野馬追いの相馬・Jビレッジの楢葉・塩屋崎やアクアマリンふくしま水族館のあるいわき市が該当する.
福島県の面積は北海道,岩手県に次いで日本第3位,東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の合計面積をよりも若干広いという広大な県であり,三者三様,文化も違えば気候も全く異なっている.
冬の気候について,会津では毎日毎日雪が降り続き,気温の低い日が続いているのであるが,高速道路で太平洋側の浜通り(いわき)にくると「どっ,ぴかーん」といった晴天の広がる温暖で穏やかな気候となる.いわきでは山沿いを除いては雪が滅多に降らず,スタッドレスタイヤに履き替えない人も多いという.同じ県内でこの差は何なのか?と時々思うが,ラジオやテレビで「中通りや会津では大雪で交通がストップしています」などと放送されていても,いわきでは晴天が広がる別世界といったところである.四季の変化は乏しいが,雪がないのは非常に暮らしやすい.
楢葉・広野町に「Jビレッジ」というサッカー場とクラブハウスを備えた日本最高レベルのサッカーナショナルトレーニングセンターがある.1997年に福島県・日本サッカー協会Jリーグ・東京電力のパートナーシップにより設立されたものである.東京電力が関係しているのは,太平洋沿いに設置されている原子力発電所の見返りとしての施設であるからで,原発がなければこの地にこのような素晴らしい施設は誕生していないと思う.
そんな「Jビレッジ」に,今年の夏開催される日韓共催ワールドカップに参加するアルゼンチンのチームがキャンプ地となることが決定した.アルゼンチンといえば最強チームのひとつ.そんなチームがJビレッジにやってくることは,福島県内ではちょっとしたニュースとなっており,チームサポートや地域交流・ボランティア活動など,全面的に応援する態勢を整えている.アルゼンチン代表が訪れるのは5月とのこと.地元としては,日本のみならずアルゼンチンも応援したくなるのが心情であろう.
FMいわき・SEAWAVEに「いわき小名浜方言講座」という番組がある.タイトル名からして,年輩のおじいちゃんやおばあちゃんが出てきて,いわき地方に伝わる方言を,その言葉の歴史や意味合いを訥々と語る面白みのない番組かと想像してしまう.ところがどっこい,これほどユーモア溢れるおかしな番組はない.パーソナリティーは声の若い!?男性2人で,いわき地方で普段使われる方言を毎日1語ずつ取り上げていく.言葉の意味を伝えることに加え,中学校の時に「This is a pen.」などとレクチャーしたように,その言葉を混ぜたフレーズを繰り返して読み返し(これを聞くとどうしても「くすっ」と笑ってしまうのは僕だけではないだろう.というのも例文の中身がふざけていて面白い.),そして更にそのフレーズの英語訳も読み上げるといった,いわき小名浜の方言と英語を学べる一石二鳥の教養番組なのである.
例えば,「こけにする」という方言,意味は「馬鹿にする」ということであるが,レクチャーする例文は,
「あんにゃろ いづも おれのごど こけにすんだ」
訳文「あの人はいつも私を馬鹿にします」
英文「He always makes fun of me.」
となり,もう一人のパーソナリティーがまじめな声でこれをレクチャーするのである.
また,別の例文は,
「おめー はなし ごっちゃにすんな」
訳文「あなた話をおかしくしないでください」
英文「Are you fallowing me?」
さらにもう一つ.
「おめーの はなぐら うっちぇしくって ねむちぇー」
訳文「あなたのイビキがうるさくて眠れませんでした。」
英文「I couldn’t sleep because of your noise.」
放送時間は,平日7:20 15:50(再) 土曜9:30 16:30(再) となっている.この番組は聞かないとおもしろさが分かりません.
・・・と,この項目を載せたとたん,平成14年3月30日をもって,番組が終了してしまった・・・.是非,同じ内容の再放送をしてもらいたいものである.(恐らく方言のネタがなくなったものと思われるが・・)
四倉の国道6号沿いに温泉娯楽施設・太平洋健康センターがある.健康センターは日本全国どこにでもあるので,ご存じの方も多いと思うが,ここの健康センターも,大浴場あり,サウナあり,マッサージあり,足裏壺マッサージあり,食堂あり,仮眠室あり,演歌ショーあり,とありふれた健康センターである.しかし,立地している場所がすごい.目の前が海,建物からは「海」しか見えないのである.大きなガラスに向かってイスにもたれならが,小さくなったカーフェリー(太陽のマークが入っているので,ブルーハイウェイラインのサンフラワー号であろう)を眺め,また,時化のときは大荒れになった灰色の波しぶきをみながら自然のすごさを感じることのできる,ダイナミックな景観を味うことのできる健康センターである.
それ故に人気が高く,日曜や連休などは大混雑となる.2階にはゲームコーナーがあって,パチンコやパチスロも置いてある.100円で60発できるのであるが,本物のパチンコよりも甘い釘でよく回る.大当たりするとメダルが1枚でてきて,3枚でてくると入泉券(1250円の金券としても使える)と交換できる.つまり確率変動が続けば次回もただにすることができる.しかし,世の中そう甘くはない.入泉料は2100円なので,2100円以上投資したら赤字なのである.運が良ければ黒字だが,大抵は赤字である.ただ,前まではすごく爆発する壊れた台(だと思う)があっていつも10連チャン以上出る台が1台だけあったのであるが,いまは通常の台に戻されてしまった.
全身マッサージは人気が高く,休日は1~2時間待ちとなるので,早めに予約をいれて入浴後に程良くあたたまってから受けるとよい.やはり部分マッサージではなく40分以上の全身マッサージがおすすめである.あっという間に時間が過ぎてしまう.
深夜0時を過ぎると,深夜料金が加算され,翌朝まで泊まっていくことができる.健康センターの魅力は安い料金で1泊できるところにあるが,加算料金は1050円なので,3150円(税込)で1泊できることになる(8時30分チェックアウト).仮眠室や休憩室,なかには廊下で寝ている人もいるが,他人のいびきさえ気にならなければ,さほど眠れないことはない.ただ,冬や夏は空調をとめないので喉がやられることがある.いわきは日の出を拝むことができるので,晴れていれば水平線から登る太陽を見ることができる.(先日泊まったが,残念ながら曇りだった.)
ちなみに,勿来(勿来海岸隣り)にも来年あたり,太平洋健康センターがオープンする.北茨城や日立から日帰りの観光客がやってくること間違いなしであろう.いわきには泉と植田の中間あたりの国道6号沿いにもう1件「いわき健康センター」が存在するが,こちらは温泉ではないが,マッサージがカイロプラクティック療法を用いたちょっと痛い(僕はちょっとどころではなかったが)マッサージを味わうことができる.
四倉の健康センターに行く場合は,ローソンのコンビニにおいてある端末機・ロッピーで画面操作をすると,JTBを通じて発行されている割引された入泉券を買うことができる.2100円が1650円になるのでローソンで買っていくことをお勧めする.
ただでさえ細かい「いわき市のゴミ分別」が,平成14年6月からさらに細かく分別されることになった.既にNo.2の項でいわき市のゴミ分別について記載してあるとおり,現在は8分類にゴミを分別をして出さなければならない.台所のゴミ置き場には,種類ごとのビニール袋が置かれていて,どの袋が何のゴミだったかごちゃごちゃになってしまう状況である.
さらに追加された分別とは,今までは「燃えるゴミ」で一括して出しておけば良かったものを,
①「プラ」マークのついている「リサイクルするプラスチック」 →新たに2週に1回回収
②「紙」マークのついている「紙箱・紙袋・包装紙」 →古紙類として一緒に出す
③その他の燃えるゴミ(従来の燃えるゴミ) →週2回回収
に分けなければならなくなった.またまた,さらにゴミ分別用のビニール袋が増えそうな事態である.「リサイクルするプラスチック」とは,カップラーメンのカップやサンドイッチを包んでいるビニール袋,卵の透明なケース,シャンプーの殻,ペットボトルに巻かれている包装フィルムなどである.ただし,惣菜等で汚れたラップやマヨネーズや汚れの落ちにくいマーガリンのついたプラスチック類は,その他の燃えるゴミに出してくださいとのこと.台所のゴミ置き場は,さらに置き場面積が増えること間違いなしである.この市民の分別の成果を,きちっと反映したリサイクルをやっていただきたいものである.
いわき市から郡山,会津若松市を経て新潟市まで,福島県を横断するように結んでいる磐越自動車道であるが,常磐道とのジャンクションから分岐して最初のインターチェンジが「いわき三和インター」である.いわき市の中心部から最も近いインターは,好間にある「いわき中央インター」なのであるが,いわきから郡山・福島・会津若松方面に高速で向かおうとする人は,中央インターでは乗らず,中央インターから三和インターまで国道49号で走っていき高速にのっかる.というのも,中央インターから磐越道に向かおうとすると,一旦常磐道を東京方面に向けて走った後,ジャンクションにて分岐し,再び三和インターで国道49号とぶつかるといった三角形のルートをとるため,ショートカットして直線で走る国道49号を走っても時間が変わらないからなのである.若干であるが,高速料金も節約できる.いわきから郡山方面へ向かう高速バスは,中央インターから乗って律儀にぐるりと迂回して磐越道を走っていくルートをとっている.郡山方面からいわき市の中心部へ向かおうとしている方,三和インターで降りた方がお得であるのでお忘れなく・・・.
熱い夏がやってきた.いわきでは数々の夏祭りが行われる.
2002年
7月20日 第2回おなはま海遊祭 アクアマリンパーク
7月26日 いわきおどり勿来大会 植田街商店街
7月27日 四倉ねぶたといわきおどりの夕べ 四倉街商店街
7月28日 ゆもと温泉大江戸宿場まつり 湯本温泉
8月 2日 はないちもんめ/いわきおどり常磐大会 湯本駅前
いわきおどり小名浜大会 鹿島街道岡小名
8月 3日 はないちもんめ/金魚つかみ大会 湯本駅前
第2回おなはま海遊祭 アクアマリンパーク
第41回いわき小名浜ミュウ花火(15000発) 小名浜港アクアマリンパーク
8月 4日 第2回おなはま海遊祭 アクアマリンパーク
8月 6日~8日 平七夕まつり 平商店街
8月 9日 いわきおどり いわき駅前通り
8月14日~15日 いわき回転櫓盆踊大会 内郷駅前
特に,いわき小名浜の花火大会は15000発もの花火が打ち上げられ,尺玉の連続打ち上げには圧倒される.いわきおどりは「どんわっせ!」の掛け声と共に,いわき市民が踊り歩くもので,職場や学校などでチームを結成し,毎年夏の恒例行事となっている.各地区で予選大会が行われて,最後のいわき駅前で行われる「いわきおどり」で祭りの頂点に達する.皆さんお誘い合わせの上,いわきの熱い夏をご堪能ください.
2002年の夏がやってきた.今年の海開きは7月17日(水).薄磯海岸をメイン開場として海開きが行われる予定である.8月18日までの33日間の海水浴である.例年海水浴客は減少しており,おととしから海水浴期間を1週間短くしたこともあって,昨年は曇りの日が多かったため約43万人の人出となり,平成になってからは最低の人数であった.今年は台風が襲来しているが,なんだか暑くなりそうな気配があるので(なんの根拠もない!),東北の湘南と言われるいわき市内10海水浴場に人出が多くなることを期待したい.
さて,海岸沿いには,簡保や国民年金などの温泉付き保養宿泊施設が存在する.この温泉は,海岸沿いということもあって,塩化物泉のしょっぱい温泉が湧き出ている.
これが「くせもの」なのである.
海水浴で日焼けをした体でお風呂にはいると,ひりひりと痛む.これが,塩化物泉の温泉となれば,火に油を注ぐのと同じことで,痛みの極みを経験することができる.日焼けした体を塩で揉んでいるようなものである.海水浴と温泉はマッチしない.肌によいアルカリ性の温泉が出ていればいいのであるが,海岸沿いでは期待できない泉質であろう.気の利いた宿泊施設では,温泉の風呂とジャグジー付きの普通のお湯の風呂の2種類があるからいいが,塩化物泉の湯船しかないお風呂では,シャワーのみといったところであろう.
いわきおどり小名浜大会の祭りにいってきた.いわきおどりは昭和56年,いわき市制施行15周年を記念してつくられたものであり,それまであった,小名浜天狗おどり,常磐やっぺ踊り,じゃんがら念仏おどり,常磐炭坑節などの踊りを継承しつつ,市民が気軽に参加できる踊りを創作しようとつくられたものであるという.札幌で開催されている「よさこいソーラン祭り」と同じで,学校や企業などの市民グループが参加して踊るという市民参加型のお祭りであり,いわきの夏の風物詩として定着している.
いわきおどりは,勿来,四倉,常磐,小名浜の各地方で大会が開催され,平で行われるいわきおどりで頂点に達するのであるが,その小名浜大会にいってみたのである.この時期になると,各職場や学校ではいわきおどりへの準備を行うようになり,「もうじき,いわきおどりがやってくるな」などといった会話が繰り広げられ(かつて東京線の高速バスの車内で,いわきおどりについて話しをしているひともいた!),各チームお揃いはっぴなどを用意して参加する.美容組合ではパーマのカツラをかぶって踊り,病院では看護婦さんがナースの格好で踊る.踊り方は基本形があるのだが,自由に振り付けを行ってよく,チームによってさまざまな踊りを見ることができる.
30分踊り続けて,15分の休憩を挟む.これを3回繰り返すので,体力がかなり消耗する.でも,非日常の祭りパワーは,人々を踊りの虜と変えてしまう.各チームの最後尾には,水分補給のための飲み物を運ぶ人がついており,かなりハードであることが伺える.こうして,いわきの夏が過ぎてゆくのである.小名浜では,次の日に15,000発の花火大会が開催され,その次の日には港祭りが開催される.祭りが目白押しの小名浜であった.
当サイト内にいわきおどり小名浜大会の模様を掲載しております.是非,ご覧ください.
夏祭りが続く小名浜港には,各地から大勢の人々がやってきている.年間100万人を越える観光客が小名浜港にやってくるといい,いわき市ではNo.1の観光客入り込み数を記録するまでになっている.1・2号埠頭では,いわき・ら・ら・ミュウやアクアマリンふくしま(ふくしま海洋科学館)がオープンし,その1・2号埠頭はアクアマリンパークというウッドデッキのオープンスペースで散策できるようになっており,週末や休日には家族連れやグループで大変賑わっている.小名浜でも「小名浜まちづくり市民会議」を発足させ,街全体のまちづくりをどのように行っていくか議論を重ねているところであり,小名浜の将来ビジョンを創っていく機運が高まっているところである.
そんな小名浜港の未来について,個人的に語ってみたい.このことを実現するためには,地元の合意形成や開発制度の問題,資金調達や開発手法など困難なステップをクリアーしていかなければならないが,人々はユートピアに向かって活動をおこなっているのであり,そんな実現不可能な勝手気ままなユートピア(夢物語)だと思って,読んでいただければと思う.
ら・ら・ミュウ(1号埠頭)とアクアマリン(2号埠頭)との間には,ウッドデッキのアクアマリンパークが整備され人々が回遊する素晴らしいオープンスペースがつくられている.しかし,その後背地には倉庫群が存在している.その倉庫は物流の拠点として使用されているのであろうが,その倉庫群にレストランや喫茶店,アウトレットモールなどの商業施設を展開すれば,人々は絶対に立ち寄ること間違いなしである.現在は,ここを訪れた観光客がただぶらぶら歩いているだけの状態で,この人々を取り込めないのは非常に「もったいない」のである.なんらかの融資や補助制度を確立して小名浜の街中の個人商店の人が移転して店を開けるようにし,是非ともあの無味乾燥とした倉庫街を「商業地」として賑わいのある空間にできないものだろうか.
小名浜駅から港湾道路を横切って,アクアマリンふくしまのある2号埠頭に向かって,貨物線が1本走っている.港湾道路を車で走ると,信号機式の踏切なので一旦停止をせず,突っ走ることができ,この線路に貨物が走ることはあるのだろうか,と疑問に思いながらも,車でいつも通過する.この貨物線は,かつて2・3号埠頭で資材や石炭などを積み上げていたときに,小名浜駅まで運ぶための引き込み線だったと思われ,ということは小名浜港における工業生産活動として機能していた「歴史的遺産」なのである.これを活用しない手はない! 小名浜駅付近に大型の駐車場をつくり,そこから「ら・ら・みゅう」や「アクアマリン」に行く人のために,夢のあるトロッコ列車を走らせるのである.車内では,かつてのこの線路の役割を案内すれば,日本の生産活動・工業についての社会科見学ともなって,一石二鳥なのである.駐車場は小名浜の街中と港との中間あたりになるので,街中に行く人にとっても便利となり,また港にやってきた人をトロッコ列車に乗せて街中に引き込ませる交通手段を確保することにもなり,小名浜街全体の向上にも寄与する.もちろん街中の魅力向上策を練らねばならないが・・・.
最近のウォーターフロント開発には「観覧車」が切っても切れない関係である.「お台場」も「葛西臨海公園」も「みなとみらい21(横浜)」もどこにも日本最大級の観覧車がついている.まぁ,小名浜にも観覧車といった画一的な施設をつくりましょうとは言わないが,アミューズメント施設があってもいい.日本初の海上ジェットコースターをつくるとか・・・.つまり,若者をターゲットにした「遊び場」が必要である.さらに,遊び場だけではなく,世界会議や展示が行えるようなコンベンションホール(ビッグサイトや幕張メッセのようなコンベンションセンター)をつくるべきである.ここでは世界一流の劇やショー・コンサートを行えるようにもし,芸術文化の発信基地としての役割を担うのである.
これだけの再開発を行ってくると,バスよりも輸送密度の高いアクセス交通機関が必要となってくる.そこで,かつて泉駅から小名浜駅まで走っていた鉄道を復活させたり,今,環境の面や乗降のしやすさなどユニバーサルデザインといった視点からも世界的に再注目をされている路面電車(ライトレール)を鹿島街道沿いの平から小名浜にかけて敷設し,自動車だけに頼らないいわき市内の交通網の確立を行って行ければ最高である.
そして近年,倉庫群の一部改装が行われて,徐々に小名浜港の魅力アップが推進されている.
小名浜には「小名浜グリーン劇場」という映画館が1軒だけある.タウンモールリスポと呼ばれる専門店街(かつての小名浜ショッピングセンター隣)から東へ道路2本行ったところにあるのだが,この映画館がすごい! かつての小名浜の繁栄を物語る施設なのであろうが,とにかくすごい! 上映は,土休祝日のみであり,上映作品も一月遅れといった内容で,中に入ると湿気からくるカビの臭いが鼻を突き,ドアを開けるとジメジメした空気が漂うばかりか,汚れたカバーの掛かる傷ついた緑色のイスが並んでいる.体がかゆくなってきた.地方の昔からある映画館ではよくある光景なのであるが,シネコンなどが建設される昨今,天国と地獄の差がある.そして,お客がいないかと思いきや,7~8人位居るのである! 車の運転できない小中学生のグループと招待券できているらしいおばちゃん達.まぁ,僕もその一人なので,物好きな奴と言われればそれまでだが,とにかくすごい映画館である.今夏の上映作品は5月中旬に公開された「ナースのお仕事・ザ・ムービー」.人間とは不思議なもので,5分もするとカビの臭いが気にならなくなり,こんなものかと体が慣れてきた.
ちなみに「グリーン劇場」は1階なのであるが,同じ建物の2階は「ローズ劇場」というのがある.その名からもピンとくるとおり,成人のピンク映画館である.正確には,小名浜の映画館は2軒あるということになる.左の窓口で買うと「ナースのお仕事」,右の窓口で買うと「成人映画」,愛想よく販売するおばちゃんは同じ人である.
(このページは2001~02年に掲載したものです)


いわきおどりは昭和56年,いわき市制施行15周年を記念してつくられたものである.
それまであった,小名浜天狗おどり,常磐やっぺ踊り,じゃんがら念仏おどり,常磐炭坑節などの踊りを継承しつつ,市民が気軽に参加できる踊りを創作しようとつくられたものである.
札幌のよさこいソーラン祭りと同じで,学校や企業などの市民グループが参加して踊り狂うというお祭りであり,いわきの夏の風物詩として定着している.
いわきおどりは,勿来,四倉,常磐,小名浜の各地方で大会が開催され,平で行われるいわきおどりで頂点に達する.踊り方は自由であるが基本形があって,各参加グループが少しずつ手を加えてアレンジをしているので,踊りを見比べてみるのも面白い.30分踊り続けて,15分の休憩を挟む.これを3回繰り返すので,体力がかなり消耗する.でも,非日常の祭りパワーは,人々を踊りの虜と変えてしまう.
2002年の小名浜大会の模様をどうぞ.

右にいって,左にいって・・・

信用金庫のグループ

看護婦さんも踊ります

グループの最後には,水分補給のための飲み物を運ぶ人がいる.踊り続けているので「暑い!熱い!」

塩を製塩している会社では,小名浜産の塩を振る舞っている


踊りの音楽は,生演奏により行われている

焼き鳥とビールは欠かせない

小名浜大会は,小名浜支所~岡自動車間の鹿島街道で行われる
アクアマリンふくしまでは,魚と海と水辺を体験するために,いろいろな体験学習やイベント,ツアーが用意されている.その中のひとつに,「バックヤードツアー」というツアーがあって,普段は見ることのできない水族館の裏側へ案内され,水族館の仕組みや機能など,興味深い内容を聞くことができる.約50分のこのツアーは,是非1度,ご参加されることをお勧めします.新たな水族館の側面を知ることができるはずです.1日に3~4回行われており,1回の定員が30名程度と少ないため,申し込み開始と同時に締めきりとなる人気ツアーである.ツアー開始時刻の30分前から3階のオセアニックガレリアで受付が開始されるので,時間を確認して受付を済ませましょう!
そんなバックヤードツアーをちょっとだけご覧ください.
是非,バックヤードツアーに参加され,自分の目でご覧になるとまた違った発見があるかと思います.

参加者には「参加証」が配られる

「潮目の大水槽の上」と「福島の森」
天井がガラス張りなので植物が育つ.資材を運搬するためのクレーンも取り付けられている.

熱帯サンゴ礁の水槽の上部.岩は擬岩であるという.本物では重すぎて建物が潰れてしまうとか・・・

みんなでぞろぞろと「裏道」を歩きます!

水槽の水をきれいにする浄化装置

パネルを使って浄化の仕組みを説明する

餌を調合する部屋

動物の病気などを調べる部屋.理科の実験室のようだ.小型のレントゲンもある.

レントゲンで撮影した写真.針の刺さったウミネコ.

ホルマリン室では剥製にさわることができる
病気等の調査のためホルマリンで保存する
(このページは2001年に掲載したものです)
総じていわきのラーメンはあまりこれといって特徴がないが,植田の地獄ラーメンというと,ちょっとした話題になるラーメンである.ラーメン屋の看板には,どこにも地獄ラーメンの文字はない.正式には「らーめんランド」という店名である.
その店は,国道6号の泉から植田方面に走っていったところの小浜町あたりにバイパス店,旧6号である県道いわき上三坂小野線の植田中心地の手前に植田店がある.そのメニューのなかに「地獄ラーメン」という激辛ラーメンがあって,辛さに応じて1丁目から順になんと100丁目まである.値段も辛さに応じて高くなっていく.メニューには「1丁目から順にチャレンジしてください」と書かれており,更に30分以内に全てたいらげると,店内に貼られる証明書とデザートが付くという得点がある.地元では,「植田の地獄ラーメンにいる」というだけでどのラーメン屋なのか通じてしまう.
また,チャーシュー麺を頼むと,大きな4枚のチャーシューがドンブリから飛び出し,まるで巨大な花びらのようにチャーシューが咲いている. 100丁目をたいらげた人の証明書が貼ってあったので,超激辛ラーメンを制覇した人がいるのは確かなようである.
No.15でFMいわきのコミュニティーFMについて述べたが,さらにアイデアが面白い番組を紹介する.
朝,7時55分から「パパにエールを」をいうタイトルで,いわき市内の各幼稚園児が3人ほどでてきて,「パパ,アクアマリンに連れていってくれてどうもありがと.吉田一郎.」「おとーさん,車の運転に気を付けて,頑張ってね.田中知子.」「お父さん,今度デズニーランドに連れていってください.佐藤幸子.」などと,通勤途中のお父さんに向かってエールを送るという番組ある.これを聞いてると,なんだかほっとしてしまう.
昼の12時35分位から10分程度,小学校のお昼の放送がそのままFMで流される「こちら小学生放送局」という番組がある.小学校の校歌が流れ,リクエスト曲と学校での出来事などが放送される.出身校の放送が流れると,懐かしさのあまり目が潤むんではなかろうか.
また,お昼にはガラガラ声のレポーターとアクアマリンふくしまの職員が紹介する番組も流される.
夕方5時45分位からは,常交インフォメーションと題して,東京の話題や情報を紹介し,明日,あさっての高速バス東京行きの予約状況を伝えてくれる.
その他,いわき小名浜方言講座やいわき弁丸出しのクマクマタイムなど,面白番組盛りだくさんの「SEA WAVE」である.
いわきでは氷点下になることは珍しいらしく,いわき市(平野部に限る)から東京方面へ向かうだけの場合,スタッドレスタイヤをはかないで冬を過ごすことが可能であるという.僕の場合,会津方面へ向かうことがあるので,12月中旬にスタッドレスにはきかえたが,まわりで冬タイヤに交換した人は少ない.交換したのは「福島」ナンバーの車がほとんどである.それだけ,福島県の他地域から比較すると暖かいのである.道路の街路樹に亜熱帯地方に生えている「シュロ」が植わっているのは,まさしく東北の湘南をイメージした南国いわきを象徴している街路樹である.(いくら暖かいとはいえ,いわきの緯度は高く,冬は東京以上に寒いと思うのだが・・・)
いわき人にとって,「メヒコ」レストランを知らない人はいないだろう.メニューもさることながら,レストラン内の演出が面白い.なかでも,鹿島(鹿島街道沿い・平と小名浜の中間地点)にある,水族館,フラミンゴ館,モンキー館の3店はユニークである.その名の通り,レストラン内が動物園・水族館のようになっており,水族館店では店内が暗くなって大きな巨大水槽(本当にでかい)の中を泳ぐ魚や亀を眺めながら食事をとることができ,モンキー館では「キャッキャ」はしる猿を見ながら食事ができる.
メニューは,カニ,ロブスター,ステーキが主なものとなっており,なかでも「カニピラフ」は,殻つきのカニがピラフの上にのっかってくるという豪快さ.このカニピラフ,味付けの方はシンプルで殻付きのカニとご飯をバターで炒めたいう感じであり,さらに,メニューの写真では茹でたカニをそのままのっけてあるような感じであるが,実際はカニの殻ごとご飯と炒めているので,カニ殻にご飯つぶがくっついていて,殻を割って食べるときに手もべとべとになるというちょっと食べづらいものとなっている.しかし,最初はバターで炒めただけの素朴なピラフかと思っていたが,食べ方によって味わいが変わることに気づいた.初めは殻付きのカニは,殻を割ってそのまま身を食べていてライスはそのまま別に食べていたのであるが,実は,このカニの身はほぐしてピラフと混ぜて食べると,塩気の利いたカニの身がパターライスと程良くマッチして,絶妙な味に変わるのであった.このカニピラフは人気メニューのひとつであり,この素朴で豪快なピラフは是非食べてみることをお勧めする.お土産も販売している.
そのほかに,ロブスターを注文すると,調理方法を焼くか蒸すか,選択することができる.ビーフシチューも美味しそうで,これもいけるのではないか.カニに飽きたらウニピラフもいけるとの情報も耳にした.
食後のデザートで,カボチャのプリンと生オレンジジュースを飲めば,後味もよくなって,ご満悦!といったところである.
現在では,リニューアルされて「スパ・リゾート・ハワイアンズ」という名称になっているが,「常磐ハワイアンセンター」と言えば,「あぁー,あそこね」,と誰もが思い浮かぶテーマパークである.石炭から石油へのエネルギー転換の波は,炭坑の街・いわきを直撃した.次々と閉山される炭坑によって寂れる一方のいわき地方の産業を,なんとかしようと開業したのが,常磐ハワイアンセンターなのである.
常磐(じょうばん)地方は湯本温泉でも知られるとおり,硫黄泉質の温泉がわき出る地域であった.炭坑にとってはやっかいな噴出物であった温泉を逆手にとって,大きな屋内プール(温泉熱を利用して年中熱帯である)を作り,ハワイのフラダンスショー(ポリネシアンショー)を行って,あたかもハワイに行った気分になれるテーマパークを昭和41年に作ったのである.昭和41年といえばまだ海外旅行が自由化される前のことであり,当時としては画期的なテーマパークであって,さらに,従業員は(フラダンスを踊る人も)全て炭坑で働いていた人々を雇用しているということもあり,それ故にマスコミにも取り上げられて,全国的に名の知れたテーマパークとなった.いわき市における観光客入込数はずっとトップであった.(アクアマリンふくしまの開館により,小名浜港のららみゅうがトップになったらしい)
「この前,ハワイに行って来た」
「えっ,本当?」
「本当だよ,常磐ハワイアンセンター・・・」
といった会話をよく耳にしたものである.福島県内では腰をフリフリしてヒラヒラの腰ひもを付けたフラダンス踊りのCMがかつて(もう20年も前になるか)流れていたのであるが,そのポリネシアンショーは現在も健在で,炎をぶんぶん振り回すアトラクションとともにハワイアンズの目玉として人気が高い.1日2回,13:30と20:10から行われている.
-----
映画「フラガール」 涙がでます.感動のストーリー.
常磐ハワイアンセンターにおけるフラガール(フラダンスを踊る女性)の誕生物語を映画化したもの.
平成18年9月23日よりロードショー開始.
いわき市は炭坑の街だった.福島県富岡町からいわき市を経て,茨城県日立市付近までに広がる炭田は常磐炭田と呼ばれ,本州では最大,日本でも北海道の石狩,九州の筑豊に次ぐ大規模な炭田であった.ところが,石炭から石油へのエネルギー革命により,次第に閉山に追い込まれ,昭和51年の西部炭鉱の閉山を最後として,125年に及ぶ炭鉱の歴史に幕を下ろしたのであった.
その炭鉱について展示をしている資料館が,湯本駅前のかつて炭鉱の街が広がっていた跡地に存在する「いわき市石炭・化石館」である.
化石館という名が付け加えられているとおり,炭鉱のみの展示ではなく,恐竜や化石などの太古の世界の展示も行われている(1階入口部).しかし,やっぱり興味をそそるのは,炭鉱についての資料館である.石炭の利用方法や,採炭道具,常磐炭坑の歴史などの展示を2階で見学したあと,あたかも地下600mの坑底まで入坑するような感覚に陥るエレベータで1階に降りると(このエレベーターは登りは普通のスピードであがって行くが,下るときは超スローに動いてスピーカーからガタガタ音が聞こえ,ガラスの外にランプがチカチカ光り,あたかも坑内のエレベーターに乗っているように演出されている),薄暗い坑内が再現されており,実際の坑道の枠が各工法によって忠実に再現されている.そして,黒いダイヤと呼ばれる石炭を採炭する状況が,古い時代から現代に至るまで,実に12場面について,人形と効果音・音声案内によってこちらも忠実に再現されている.昔はふんどし一丁で,女性も下半身のみの服装で採炭を行っており,湿気が多く温泉が吹き出す常磐炭坑では,水風呂につかりながら採炭していたということであり,採炭現場は過酷で危険な労働であったことを伺い知ることができる.全国(石狩・筑豊も含む)で100人もの人々が命を落としていた(昭和40年くらいまでの話である)ということからも危険な仕事であったことが理解できる.また,昭和10年頃における炭坑の街で暮らす人々の様子も再現されており,炭坑の街の独特の雰囲気を感じ取ることができる.
いわき市の小学校では,遠足や社会科見学で必ず訪れるところなので,いわき市で育った人にとっては「あんなところ,おもしろくねぇー」などと言ってわざわざ見に行くことはないような資料館であるが,炭坑の歴史・ひいてはいわき市の歴史を知る上では非常に面白い資料館である.
これは「街づくり」を考える上で,いわき市を市民に知ってもらい,また勉強してもらうために,市企画調整課で行っている勉強会である.何故に「宇宙」塾と名付けられたかというと,「宙」とは時間の流れ,「宇」とは空間の広がりを表し,いわきという地域を時間の流れと空間の広がりの中でじっくり考えてもらいたいとの思いを「宇宙」という文字で表現しているとのことである.
平成2年度から毎年大きなテーマを設定して開催されており,日曜日の午前中に2時間程度,各テーマの専門家や著名活動人等の講演を聴講するというもので,全11回,9月頃から2月まで,2・3週間に1回の割合で開催されている.会費は無料であるが,年度ごとに塾生の募集を行っており,基本的に塾生のみの聴講となる.皆勤賞には賞状が渡される.
参加者は,年配の方が多いが,中には若い世代の人もぽつぽつと見かけることもでき,どの参加者も街づくりに関心をもつ人々であることには間違いない.市民の自己啓発や文化の向上,街づくりを考えるきっかけをつくる上で,このような市民講座は大変素晴らしく,なによりも無料で色々な立場の人の話を聞けるというのはお得であり,時代の流れ・情報をキャッチするのにはうってつけである.講師の中には,芸術家や設計士などといった話すことを職業としていない人も招かれている.会場は,いわき市内に点在するテーマにそった公共施設が使われており,たとえば障害者や年配の方にも配慮した街づくりを行っていかなければならないという思想であるユニバーサルデザインについての講演の場合は,健康増進施設いわきゆったり館の研修室を利用する,といった具合である.
鹿島ショッピングセンター(鹿島SC)については,No.19で紹介したが,その中にダイエーのスーパー・ハイパーマートがある.そのレジの仕方がちょっと変わっている.レジに向かってベルトコンベアーのようなものがあり,買い物客は手押しカートに入れた商品やかごの中身をベルトの上に乗せて,前の客の商品との区切りをつけるため,白いプラスチックの区切りの棒を置く.そのとき,ビニールの買い物袋が必要ない人は,その旨が書かれたカードを取って商品の上にのっけておく.袋がいらない人にはポイントが与えられ,20個たまると100円引きの商品券がもらえる.商品のレジが打ち終わると,ベルトコンベアーは少しずつレジの方向に動いていき,商品も同時に動いていく.
この後も変わっている.レジの打たれた商品は,かごに入れられるのではなく,丸い棒がいくつも並べられた滑り台のような上をなめらかに滑っていき,お客は自分が購入した全ての商品のレジが打ち終わらないうちに,次々と流れてきた商品をビニール袋に入れる.つまり,時間の短縮が図られるのである.袋を詰めるためのレーンは2つあるので,前の客が入れ終わっていないときは,電車のポイントのようなレバーを変えて,前がつまらないようになっている.
「変わっている」と表現したが,外国ではこの方式の方がよく見かける.パリやロンドンでも見たし,シンガポールでもそうであった.
いわき湯本温泉に「さはこの湯」という公衆浴場がある.いわき市観光公社が管理運営する温泉保養所であるが,入浴料大人150円という破格の値段で温泉に入ることができる.営業時間は午前8時から午後10時(入場は午後9時)まで,休憩を行いたい人は710円を払えば休憩室が利用できる.温泉成分は,「硫黄水」であり,慢性皮膚病・やけど・動脈硬化等に効能がある.
なにしろ,安く入浴できるので,非常に混雑する.浴場は,決して広いとは言えないので,さるが群がって湯につかっているのと同じで,人間が所狭しと,湯につかっているさまは,ちょいと滑稽である.石鹸はあるがシャンプーはない.もちろんタオルも持参である(小物は売店で売っている).駐車場も狭くて台数が少なく,運良く開いていればいいが,開いていないときは辛抱強くどこかがあくまで道路で待っているしかない.入浴後に「木村牛乳」を飲むのは必須である.
FMいわき(SEA・WAVE)のお昼の時間に,「こちら小学生放送局」という番組をやっている.いわき市内の各小学校がかわるがわる放送を行っていくのであるが,必ず最初に学校の校歌が流れる.その中で,泉小学校の校歌はすばらしい.なにがかって,ハモるのである.「いずみ,いずみ,いずみ,いずみ・・・」,この部分でメジャー域とマイナー域のパートナーが二手に分かれてはもっているのである.学校の校歌でハモるなんて聞いたことがない.とても美しいこの校歌,実際に歌うときには,「君は高いほう,あなたは低いほう」,というように班分けしているのだろうか?出席番号の奇数が高いほう,偶数が低いほう,といった具合に班分けしているのかもしれない.
小名浜港の隣にマリンタワーなどが建つ公園がある.小名浜港からトンネルを抜け,坂をぐんぐんあがると,緑の芝生の公園が広々と広がる.ロンドンなどで見られる日本離れした素晴らしい公園である.世田谷区の砧公園に似ている.日本の公園というと,長方形の敷地内に,ベンチやブランコ,ジャングルジムなどを配し,いかにも箱庭的な公園といったものが多いが,この三崎公園は,どかーんと広々とした芝生のみが広がり,その中でキャッチボールをしたり,寝そべったり,かけっこをしたり,と思い思いの行動がとれる.ビルが建ち家が密集する都市部では,こういった公園が最も求められるオープンスペースであり,憩いの場になる真の姿の公園であるように思う.
三崎公園は,夜になると,カップルが密集することでも有名で,暴走族や不良のたまり場としても名をはせている.正月の「初日の出暴走」では,茨城の「族」達が,三崎公園を目指して突っ走ってくるというから,三崎公園もまんざら捨てたもんじゃぁない.
僕の場合,いわきでは路線バスに乗る機会は滅多にないが,平(たいら)で飲み会があると,居住地・小名浜まで帰るのに,タクシーだと深夜割増で5000円,運転代行でも4000円は取られる.そこで,たまには1次会で切り上げて最終バスで小名浜まで帰ってこようと思った.いわき駅前21時35分発が小名浜までの最終バスである.20人位の乗客を乗せて,鹿島街道を南へ向けて走っていく.
常交の整理券にはバーコードが入っている.何故かと思いきや,運賃を払うときに,整理券を専用の黄色い投入口に入れると,自分の運賃が表示されるようになっていた.進んでいる.初めて常交の路線バスに乗った人は気づかずに,整理券を運賃と一緒に運賃投入口に入れてしまうだろう.
東警察署を過ぎたあたりから,どんどん乗客が降りていき,小名浜のメインストリートを過ぎると車内は僕だけに.僕の下車する停留所の手前にて運転手さんが突然話しかけてきた.
「このバスは暴走族だよ.」
と,わけのわからないことをしゃべっている. 「はぁ?」 再び聞き返すと,
「普通の自動車でもここから平まで27分かかるんだよ.バスは乗客を乗せたり下ろしたりしているんだよ.それなのにバスのダイヤは30分で小名浜まで来るようになっている.スピードを上げていたのがわかるだろう.腕まくりしてぶっとばしてきたよ.このバスは暴走族だ.」
そして,料金を払って降りようとしたとき,
「人生楽しく行きようね.気を付けて.」
と一言.個性的な常交の運転手であった.運賃は630円である.
五浦美術館はいわき市の施設ではなく,お隣茨城県北茨城市に存在する.しかし,国道6号を走り勿来の関を越えると,そこはすぐ北茨城市であり,県境を感じさせるような峠もない.気がつくと茨城県に入っていく感じである.したがって,いわき市民も気軽に訪れる施設であろう.
正式には「茨城県天心記念五浦美術館」であり,岡倉天心や五浦の作家たちの業績を紹介し,企画展などによる展示も行われ,芸術文化活動の拠点として平成9年にオープンした県立美術館である.入館料は,なんと180円.激安である.しかも,美術情報ライブラリーという美術に関する専門図書を閲覧できるスペースがあり,美術に興味のある人にとっては,素晴らしい施設である.建物は近代建築の素材であるコンクリートを打ちっ放しにしつつ,木目調の化粧版によって和の柔らかさを醸し出す落ち着いたものとなっている.館内からは太平洋が一望できる.いわき地方の芸術文化の向上に,五浦美術館は非常に役立つ施設である.
日本人たるもの,たまには足を伸ばして「ざぶーん」とお風呂に入りたいものである.いわき市には湯本温泉という有名な温泉があるが,結構あちこちに日帰り大浴場が存在する.そんな,大浴場を個人的に比較してみました.
| 場 所 |
泉 質 |
サ ウ ナ |
露 天 風 呂 |
タ オ ル |
シ ャ ン プ ー |
飲 食 施 設 |
木 村 ビ ン 牛 乳 |
料金 |
コメント | |
| さはこの湯 | 湯本温泉 | 硫黄 | × | × | × | × | × | ○ | 150 | 安いこともあって非常に混雑する温泉である.浴槽も大きくないので,芋洗い状態での入浴となる.黄色い石鹸のみが置いてある. |
| 国民年金センター 「いわき」 |
三崎公園 | 塩化 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 500 | 三崎公園にある施設で,日帰り入浴は午後4時までとなる.浴場から海が望める.1階で新聞が読める. |
| 神白温泉 民宿「国元屋」 |
上神白 | 酸っぱい | × | × | × | ? | × | × | 500 | 飲むと胃腸によいという泉質で,療養のため長期にわたり泊まる客が多い.浴槽も普通のお風呂である.日帰り入浴は午後8時まで. |
| 小名浜スプリングス ホテル |
下川 (大剣) |
塩化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1000 | ゴルフ場が併設されたリゾートホテル.プレー終了時間以外は空いており,浴槽も非常に大きい.照島や太平洋の大海原が一望でき,露天風呂は太平洋の絶壁の上にある.ロビーで英字新聞も読める. |
| 蟹洗温泉 「太平洋健康センター」 |
四ツ倉 | 弱 アルカリ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2100 | 太平洋に面した健康センター.大海原を目の前にして入る大浴場は,爽快で気持ちがいい.いわき市各地へ送迎バスが走っている. |
| いわき健康センター | 小浜町 | 温泉なし 漢方湯 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 2100 | 健康センターである.漢方風呂があり,しばらく入っていると弱い部分(特にあそこ)がひりひりしてくる. |
| 道の駅「ならは」 Jビレッジ湯遊ならは |
楢葉町 | 塩化 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 500 | 道の駅にある温泉.ジャグジー風呂が充実しており,サウナもついて500円は安い.タオルセット付きだと800円となる. |
| 天心の湯 | 北茨城市 五浦 |
塩化 |
△ | ○ | × | ○ | ○ | × | 1000 (平日・夜間 割引有) |
露天風呂の「白泥湯」が珍しい.北茨城でとれる粘土質の泥を混ぜたもので,肌がすべすべになるという.中はそれほど広くはない. |
|
飲食施設とは,軽食のとれるレストランのことである. |
||||||||||
小名浜の岡小名,鹿島街道沿いに「吉牛(吉野屋の牛丼)」がオープンした.いわき市では,かつて倒産する前の吉野屋が平駅前にオープンしていたが,倒産によって閉鎖.その後,吉野屋は復活したものの,いわき市内にはオープンしていなかった.いわき市民にとっては待望のオープンなのである.そんあこともあってか,オープン初日より大行列.店内では食べられないので,弁当を買って駐車場で食べる事態も・・.なおかつ,並250円セールと重なって,駐車場に白テントの臨時弁当売場ができて行列ができるという盛況ぶりであり,いかにいわき市民は「吉牛」に飢えていたかが伺える.
吉野屋というと,おやじや若者の男性客ばかりで,女性が入りづらいという雰囲気があるが,ここの店はボックス席があることもあって,家族連れや女子高生,OLといったいままでの吉野屋の客層とはちょいと違う感じを受ける.小名浜の喫茶店での話題は,もっぱら吉牛の話題で持ちきりで,「店は大混雑だっぺよ.行ってみたか」などといった会話が取り交わされている.
いわき市民は,郡山などの吉牛のある地域に住む人たちとの会話で,
「吉牛の朝定(朝定食のこと)が食いてぇーなー.」
などといった会話がはじまると,悔しい思いをしていたのであるが,これからは,胸をはって,
「そうだよなー.」
と,相づちを打つことができる.どういうわけか,吉野屋の牛丼は無性に食いたくなるときがある.僕も大変嬉しい限りである.
いわきは高速バスが発達しているところであり,各インターチェンジに乗用車用の無料駐車場を設けて,パーク・アンド・ライドを日本でも先駆けて導入したところでもある.値段が安いこともさることながら,そのような利便性のよさが功を奏して,いつも盛況満席といったところである.特に,いわき東京線については,2001年4月1日より更に3増便されて21往復体制となった.(2003年5月からは,さらに3往復増便の24往復体制となり,30分おきの時間帯が増えた.)
いわき駅始発が午前5時となり,いわき駅最終が20時となった.さらに,東京駅発の始発が7時30分となり,最終が22時(いわき駅到着はなんと午前1時となる)という便ができた.給料日後(月末)の週末や連休の最終日には,1便2台運行の増便体制にもかかわらず,東京駅発のバスが「本日すべて満席ですので電車で帰って下さい」などと言われるときがあったが,今回の改正で,東京駅発15時30分から21時までは30分間隔の発車となり,特に午後7時以降の利便性が格段に向上した.それから,綾瀬駅から東京駅までのルートが首都高経由から一般道経由に変更された.
さて,いわき東京線は,JRバス関東,東武鉄道,常磐交通の3社で運行されている.これは駅ターミナルの乗り入れ権利があって,東京駅はJRバス,綾瀬駅は東武バス,いわき駅は常磐交通となっているため,お互いのバス会社を運行させて駅前ターミナルからの発車を実現させている.綾瀬駅の停車は,首都高の混雑を避けるために都心手前の駅で乗客を下車させるために停車するのである.
この3社,どれに乗っても同じだろう,と思いきや,若干の違いがある.
バスが一番綺麗なのは東武鉄道である.次に常磐交通であり,JRは電車もそうであるがバスもちょっと汚い車両が回ってくることもある.特にJRバスの場合,各方面手広く路線を持っているので,どこかのお古が回ってきたりするのではないか.しかし,悪いことばかりでもなく,かつて夜行で使われていたフットレスト(足置き場と足のふくらはぎをのせる台)がついていることもあり,ちょっと得した気分になる.最近は新型バスも導入されるようになってきた.
一番安全運転なのはJRバスである.逆に吹っ飛ばすのが常磐交通.首都高の常交の走りっぷりは追い越し車線を走っていき,つくばセンター行きや水戸行きなどの高速バスを抜かしていく.
いわき市の魚を決定しようと,市民からの公募を行ったところ,「メヒカリ」と決まった.漁協組合からは漁獲高の大きな「カツオ」にしたいという思惑があったが,最終的には市民に親しまれているメヒカリとなり,一安心といったところである.カツオは土佐高知などで既に有名であり,今さらカツオを「いわきの魚」にしたところで,独自性やアイデンティティーは何ら感じることのできないものである.メヒカリは長持ちしない魚なので,会津などでは食することがあまりない.いわきに来た人にはメヒカリを薦めているが,皆珍しいと言って唐揚げなどを食べていく.魚そのものの値段はそれほど高価なものではない.
メヒカリとは,漢字で書くと「目光」,正式には「あおめえそ」,硬骨魚綱 はだかいわし目 あおめえそ科の魚である.英名は「green eyes」,その名の通り,青緑色に光る大きな目が特徴のシシャモのような小さな魚である.底引き網で漁獲され,特に9月から4月にかけて多くとれる.底引き網の休業期間である7・8月には水揚げがない.唐揚げ,干物,天ぷらなどで食べられ,珍品として刺身で味わうこともできる.刺身は,船から直送されるごく一部の飲み屋などで食べることができる.
大黒屋デパートが破産した.大黒屋についてはNo.13の項でも述べているが,いわきの老舗百貨店であった.今年は創業100周年を迎える記念すべき年だった.福島民友などでは号外が出され,コンビニのレジには号外がおかれるほど,いわき市民にとっては衝撃的な出来事であった.なにしろ大黒屋デパートは,福島県浜通り地方の唯一のデパートと呼べる百貨店だったのである.負債額は大黒屋と関連企業の大黒屋ストアーなどをあわせて約90億円,要因として,①大手資本による大型スーパーの相次ぐ出店での競争激化(バイパス沿いにたてられる大型店舗によるもの.中心市街地の衰退の元凶でもある),②デフレによる単価ダウン(中間の卸売りを通さないことで価格ダウンを果たしたユニクロが最たるもの),③各地デパート倒産を背景にした問屋との取引条件の変更(そごうの倒産を背景に,問屋業界も厳しい条件を突きつけてくるようになったのか),④金融機関の引き締め(いわゆる「貸し渋り」である)などによるもの,としている.
自主再建を断念した破産宣告(民事再生法などの自主再建ではないのである)ということで,平成13年5月22日よりシャッターは開かず,「大黒様の宝くじ」として有名な宝くじ売り場も閉鎖されてしまった.「せめて,宝くじ売り場だけは続けて・・・」といった声も多く聞かれるが,倒産したデパートの宝くじ売り場に果たしてどれだけの人が購入しに来るだろうか,といった疑問の声も聞かれる.
地域経済に与える影響は大きいと言われており,いわき市役所では商工労政課内に市内の取引企業に対する融資相談窓口と従業員雇用のための相談窓口を設置した.パートを含む296人は解雇されるという.
実は,大黒屋デパートの経営が芳しくないという噂はちらほら聞かれていた.いわき商工会議所の会頭でもある馬目社長の任期が平成13年10月まであり,任期が終わったところで倒産か!などと言った冗談交じりの囁きもなかったわけではなかったが,こんなに早く倒産するとは思っていなかったに違いない.大黒屋デパートは,バーバリーやシャネルなどが入る,いわき地方の消費文化レベルを引き上げた功績は大きなものであったと思われる.
暑い熱い夏がやってきた.天気予報で福島県の気温を見ると,必ずいわき市の夏の気温は,郡山や福島,会津若松と比べて3~5度程度低くなっている.夏暑くて冬寒い山々に囲まれた内陸型気候の中通り(郡山や福島)や会津地方の人々からは,「いわきは海に近くて夏は涼しくていいよな~」,などと言われる.しかし,いわき市全てが涼しいというのは誤りだと思う.というのも,いわきの気象庁の測候所は海の近くの小名浜にあり,いわきの気温や天気は,すべて小名浜が基準となっているのである.小名浜は確かに海からの涼しい風が吹いてきて,気温が低い.この小名浜のみの気温が,いわき全体の気温として,NHKを初め,TV各局で放送されているのはちょっと正確さにかけているように思う.いわきの中心地・平(たいら)は内陸に位置しているので,小名浜よりも2~3度は気温が高いといわれており,いわきに住んでいる人も,「天気予報は小名浜の気温だから,平はもっと暑いよ」と誰もが思っている.決していわきは涼しくない! ちなみに僕は,目の前に漁港の広がる小名浜港の前に住んでいるので,涼しいいわきを充分すぎるほど享受しております.
草野心平はいわき市出身の詩人であり,いわき市小川町にこの記念館がある.夏井川上流の小玉ダム近くの自然に囲まれた地域にあって,館内からは大きな透明なガラス窓越しに,阿武隈の山を望むことができる.常設展示室の構成も独特で,草野心平の肉声による詩の朗読を聞くことができるとともに,モニュメントが配されて展示空間そのものを楽しめるような作りとなっている.カフェレストラン「テン」では,手作りのこった料理を味わうことができ,食事だけでも訪れてみるのも良いところである.時々,草野心平と親交のあった人物などの企画展を開催しており,今年の夏は「中原中也展」を開催していた.「汚れっちまった悲しみに・・・.ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん」である.
(このページは2001年に掲載したものです)