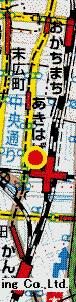東京駅・芝・麻布十番・白金台を結ぶ路線
黒10 目黒駅⇔東京駅南口(経由)一ノ橋・御成門 目黒営業所
路線keyword:増上寺の三解脱門,赤煉瓦駅舎,麻布十番,芝
威風堂々とした街並みの広がる東京駅南口の東京中央郵便局の隣から、バスは出発する。左手に赤煉瓦駅舎を見ながら右折し、続いてはとバスのりばが現れる。正面突き当たりは新宿副都心に移転した都庁の跡地であり、現在は国際的な総合文化情報施設である「東京国際フォーラム(国際会議場)」の建物がほぼ完成し、開業に向けて準備が進められている。
左手に東京国際フォーラムを眺めて、馬場先門交差点にて日比谷通りに左折する。直進すれば二重橋となる。右手には馬場先濠と皇居外苑の緑が眺められ、重厚な明治生命館等のビルディングが現れる。首都東京を思わせる威厳ある景観が続く。日比谷交差点を過ぎると、左手に帝国ホテル、右手に日比谷公園が現れる。
日比谷通りを南へ走り、御成門を過ぎると左手が港区役所となって、右手に芝公園の緑が現れる。そして右手には、徳川家康が徳川家の菩提寺とした増上寺の真っ赤な三解脱門が突然現れる。古川を芝園橋で渡ってバスは右折する。右手には東京タワーが望める。芝園橋から古川橋までは都06系統と同じルートを走る。
古川橋を出るとバスは直進せず、「く」の字型に経路をとって魚藍坂下の停留所に止まる。桜田通りに入って、終点まで東98系統と同じルートを走る。清正公前で目黒通りに右折し、白金台の界隈を走って、駅ビル「サンメグロ」が現れると、終点目黒駅に到着する。
平成12年12月、都営大江戸線・営団南北線の開通により廃止された。