 |
| 田季野は「わっぱ(輪箱)飯」の店として有名である.わっぱ飯は,尾瀬を有する檜枝岐村における山人の弁当の器として用いられてきた「曲げわっぱ(輪箱)」に,会津の食材を活かした料理を盛り込んだ創作料理で,1970(昭和45)年にオープンしている.わっぱ飯の他にも,会津の郷土料理が食べられ,会津に来たら一度は立ち寄りたいお店である.また,建物も歴史があり,築150から200年前に建てられたもので,会津西街道の旧家であったものを移築復元したものとなっている. |
 田季野の店構え |
  わっぱ飯 いくつか種類があるが,色々と入った五種輪箱がお薦め. |
 会津西街道にあった旧家を移築した店内 |
|
|
| 【公共交通案内】 ●路線バス ・ハイカラさん 若松駅→若松市役所前→鶴ヶ城→飯盛山→若松駅 若松駅からバス約20分 ・若松駅より西若松駅行,本郷行,高田行,芦の牧温泉行などで神明通り下車.徒歩5分. |
|
|











































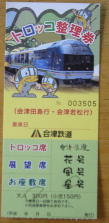


























































 昔
昔  今
今











![小石ヶ浜_Koishiga Beach[猪苗代湖!ぐるっと一周・浜紹介]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/DSC00038-2.jpg)




![中田浜_Nakada Beach[猪苗代湖!ぐるっと一周・浜紹介]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/DSC000281.jpg)




![崎川浜_Sakka Beach[猪苗代湖!ぐるっと一周・浜紹介]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/DSC00025-1.jpg)










