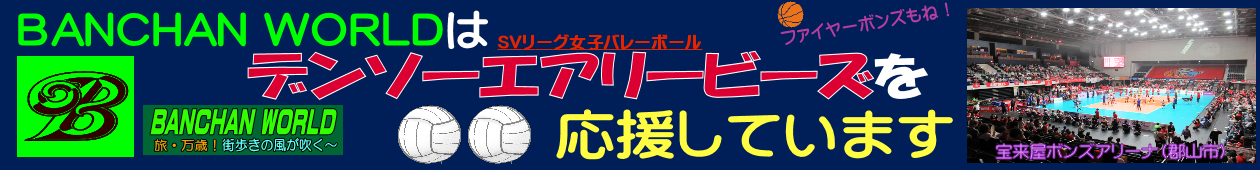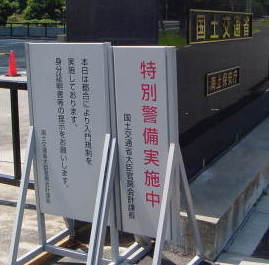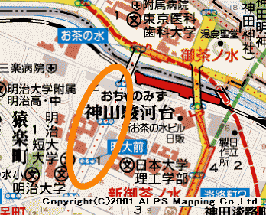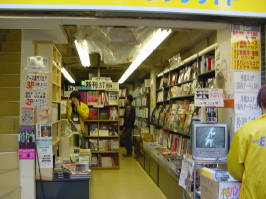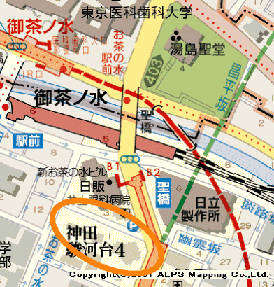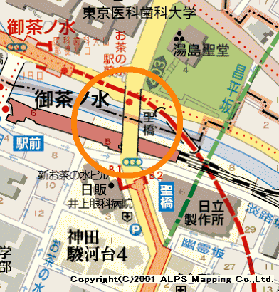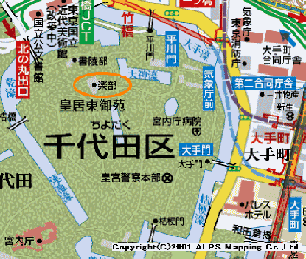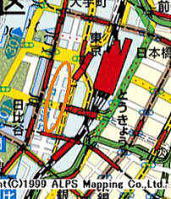Hill Top Hotel(The wedding version)
 文化人の香りがする山の上ホテル |
 |
| 山の上ホテルは多くの作家や文化人の方に親しまれているホテルで,文化人のホテルとも言われている.昭和12年に財団法人日本生活強によって建てられた建物であるが,第2次世界大戦の時にはまず日本海軍に接収され,戦後は米軍の陸軍婦人部の宿舎として使われた.建物の中にはいると(本館),昭和初期を思わせる重厚な雰囲気を肌で感じることができ,アール・デコを基調とした優雅な姿と眺望のよさから,「ヒルトップ」の愛称で呼ばれていたという.その後,昭和28年に米軍から返還されたときに,吉田俊男氏がホテルを受け継ぎ,丘の上ホテルではなく山の上ホテルと名付けたのだということである.(山の上ホテルホームページより) このクラシックな雰囲気の漂うホテルで知人の結婚式の披露宴が行わました.歴史と品のあるホテルで行われるセレモニーは,最高級のムードと品格の高さを感じることができるものでありました.その山の上ホテルを結婚式バージョンとしてお伝えします. |
 明治大学の脇にある小径を入ると,丘の上にホテルはある |
  クラシックな雰囲気のロビー待合室 |
 エントランス(入口)を入ったところ |
 当日は受付をさせていただきました |
  会場 |
 新郎新婦のお二人 (おめでたいことですが,プライバシー保護のため加工してあります) |
  語らい |
 シェフから料理についての説明がある 今日のメニューは「フランス料理」 |
 全てホテルの刻印が入っているフォーク |
 Jambon de Parme イタリアパルマ産生ハム ルッコラ添え |
  Composition de Fruit de Mer au Caviar 海の幸盛り合わせ キャビア添え |
 Consomme Brunoise コンソメスープ 野菜のブリュノア入り |
 Homard Frais a l’ Americaine 活オマール海老ポワレ アメリカンソース |
 生演奏が雰囲気を盛り立てます |
 St-jacque Saute au Safran 青森産帆立貝のソテー サフラン風味 |
 Sorbet au Citron Vert シトロンベールのソルベ |
 Filet de Boeuf Roti Sauce Poivre Noir 牛フィレ肉のロースト ブラックペッパーソース |
  Melon Rafraichir / Cafe 静岡産マスクメロン コーヒー ケーキカットのケーキ |
 ワイングラスも刻印入り |