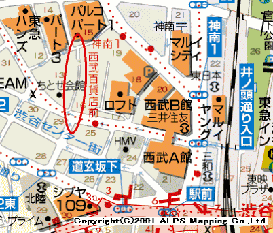ホテルグランパシフィックメリディアンを背景に 芝生が広がる潮風公園 |
 |
| 昔の東京都の区分地図を見てみると,現在のお台場は「13号地」と記されているだけの何もない茶色の埋め立て地の表記になっているが,潮風公園の部分はすでに緑色に塗られており「13号地公園」となっていた.かつての13号地の風景からは想像もつかないほど近未来的な都市に変貌したお台場であるが,公園の隣にある「船の科学館」とこの公園はお台場の老舗の施設と言ってよく,昭和49(1974)年の開園である.その後,臨海副都心・お台場の整備に伴って,平成4~8年に再整備され現在の潮風公園となった.かつては,品川駅と門前仲町駅を海底トンネル経由で結ぶ都営バスが走っていたが,当時は「海上公園」というバス停があって船の科学館へのアクセスを行っていた.草ぼうぼうの殺風景な埋め立て地だった風景がかすかに頭の中に残っている. 昔話はさておき,潮風公園はお台場の主要施設からは少し離れた東京港寄りにあるため,お台場の商業施設に来た人にとっては,この公園にわざわざ行こうと思って歩いてこなければ,気がつかない存在であろう.公園内には広い芝生や水遊びの出来る水のせせらぎ,バーべーキューコーナーなどがあり,家族連れでのんびりと休日を過ごすにはもってこいの場所である.また,風景が贅沢で,近代的なホテルやレインボーブリッジ,開放感ある東京港,そして羽田空港に離着陸する飛行機を眺めながら,非日常空間を体験するのも楽しいものである.
|