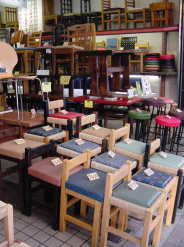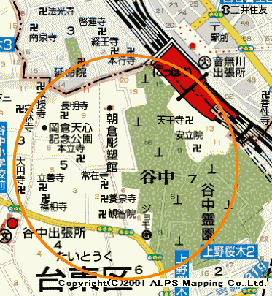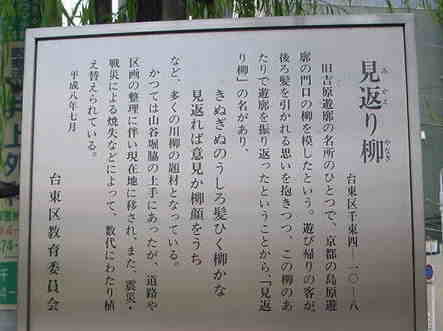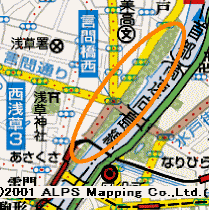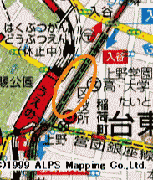白山通り・春日通りの補完的な役割を果たす千川通りを走る路線
上60 池袋駅東口⇔上野公園(経由)大塚駅・文京区役所 大塚営業所
路線keyword:元祖山の手住宅地,文京区役所,千川通り,東京大学,上野広小路,不忍池
かつては茶60系統として、池袋駅東口・御茶ノ水駅間の運行だったが、御茶ノ水駅行ではなく上野公園行に変更された路線である。池袋駅東口・大塚駅間は朝夕のみの運行であり、それ以外の時間は大塚駅の発着となっている。
上野公園バス停は不忍池南側・水上音楽堂に位置し、バスターミナルが存在しないので、上野公園付近ではループ状にルートを設定してバスを運行させている。上野公園を発車すると、中央通りに入り、アブアブや上野松坂屋のデパートを眺め、上野広小路の繁華街をぐるりと周回する。
右手に再び不忍池が現れ、バスは不忍通りを北上する。地下鉄千代田線根津駅までは、
上58系統と同じルートを走る。
根津駅にてバスは左折する。この辺りを歩いている学生はほとんどが東大生である。バスは坂を上り、弥生となって東京大学を両手に眺め、本郷通りを横切って元祖山の手住宅地である古い街並みを進んでいく。
白山通りに入るとバスは南へ進む。バスは文京区役所に寄るように迂回したルートを走り、春日町交差点で右折し、文京区役所前を通ると再びバスは右折して、進路を北に向ける。後ろを振り返ると、東京ドームの巨大な白い屋根がビルの谷間に埋もれて見ることができる。
バスは2車線の千川通りを北上する。この通りは春日通りと白山通りの中間に位置し、沿線は小石川界隈の静寂で落ち着いた古い街並みが多く残る地域である。大塚までは緩やかな上り坂が続き、山の手台地の趣を感じ取ることができる。
右手奥には小石川植物園が存在する。不忍通りを横切って、しばらく行くと都電の走る大塚駅前となる。
大塚駅に寄ると、バスは180度方向を転換し、通りは違うが再び南に進路をとる。
大塚-池袋 未乗