(このページは2007年に掲載したものです)
No.20 クリスマスイルミネーション
クリスマスのシーズンがやってきた.福島では駅前とパセオ通りの2カ所でイルミネーションが点灯している.
福島駅前イルミネーションは,東口駅前広場を中心にツリーや花壇への約5万球の電飾となっており,2007年11月30日から1月6日の16:30~22:00まで行われる(その後,2月14日まで延長されることが決定).樹木への電飾はブルーを基調としており,幻想的な空間を演出している.そして,今年は市制施行100周年を記念していることもあり,大がかりにイルミネーションを行っているのがまちなかの「パセオ通り」である.例年は数本の電飾しかされていないが,今年は約50本のほぼ全ての街路樹に約10万球の電飾を施しており,ちょっとした話題となっている.パセオ通りの電飾は最近流行の白や青の電飾ではなく,昔ながらの暖かみのある電球色のイルミネーションであり,これだけ徹底的に電飾がならんでいると,見ていて気持ちがいい.クリスマスイブには,一方通行の車道にはこのイルミネーションを一目見ようと車が列をなしていた.12月14日から翌年2月14日のバレンタインデーまで点灯しており,もうしばらくは福島版光のページェントが楽しめる.パセオ通りのイルミネーションは17:00~23:00点灯.(2007,12)

No.19 カレイナニ早川氏の講演会(コラッセふくしま)
福島駅西口インキュベートルーム講演会として,映画フラガールのダンス教師・平山まどかのモデルとなったカレイナニ早川氏の講演会がコラッセふくしまで行われた.カレイナニ早川氏は,常磐ハワイアンセンター(現スパリゾートハワイアンズ)付属の常磐音楽舞踊学院最高顧問となっており,昭和39年のハワイアンセンター設立当時のフラダンス講師として,常磐炭坑で働く家族の少女達をダンサーに育て上げた人である.スパリゾートハワイアンズは,斜陽化していた石炭産業をなんとかしようと,炭坑から噴出していた温泉水を利用して東北に常夏のハワイを造ったリゾート施設で,全て炭坑で働いていた人々によって運営されていた.その施設内で行われるフラダンスショーにも,もちろん炭坑で暮らしていた少女達を起用していた.
講演は,まずフラガール映画の話から始まった.平山まどか先生が酔っぱらって登場するシーン,あのシーンには実際の育成生徒さんに対しても侮辱した脚本であるとクレームをしたそうだが,演出だと言うことでそのまま放映されることになったとのこと.女優さんのプロ意識はすごく,短期間のレッスンで驚くようなレベルに達していき,恐らく見えないところで努力していたのではないかとのこと.最後のシーンの涙は,映画とはいえダンスを習得していった女優さんたちの本当の涙だったということ.そして,ハワイアンセンター建設時代の苦労話,ハワイの話と続き,あっという間に時間が過ぎていった.(ちなみに,借金取りの話も脚本らしい)
「ダンスがいくら上手でも,礼儀や挨拶がだめでは,一流にはなれない.他人に対して謙虚に生きなければならない.」
そのため,育成の生徒さんに対して,ダンスの指導だけではなく,挨拶から箸の持ち方までマナーや礼儀についても厳しく教育していたとのこと.今では,その生徒さんも立派な家庭を持って充実した生活を送っているとのことであった.
講演最後には,なんとフラダンスを全員でレッスンすることになった.右と左にステップを踏み,お日様や波・椰子の木などを手で表現し,楽しい踊りのレッスンとなった.最後のレッスンの時のカレイナニ早川氏は,一番楽しそうに生き生きと話をされていた.予定時間をオーバーし,みんなでワンフレーズのフラダンスを踊って終了となった.本物を身につけている人の心の大きさ,余裕を垣間見ることができた.70歳を越えているのであるが,年齢を感じさせない.感性豊かで生き甲斐を持っている人は,いつまでたっても歳をとらないのかもしれない.私も,いつまでたっても感性豊かに生き生きと生きていきたいものである.(2007,11)
No.18 中合百貨店の北海道物産展
福島駅前にある老舗百貨店に中合がある.しかし,郊外型店舗のオープンや仙台への格安な高速バス運行によって,駅前の中心市街地は衰退の一途をたどり,中合百貨店もその影響を大きく受けている.中合百貨店の歴史は古く,1830年の太物行商が始まりである.そんな中合であるが,人気のある催事として「北海道物産展」が行われる.デパートの最上階にある催事場では,北海道で人気のお菓子や食材,カニが山盛りとなった弁当など,北海道に行かずとも北海道が味わえるので,いつも多くの人出でにぎわっている.先週,この催しが行われていたが,中合も人で混雑しており,最上階から下の階に移動するお客さんによって,デパート内も賑わっていた.中合は福島市でデパートと呼べる百貨店なので,頑張ってもらいたいところであるが,三越と提携している郡山のうすいなどと比べてしまうと,ディスプレイや雰囲気・品揃えなど,どうしても時代に取り残されているようなところを感じたが,現在は新たな取り組みを行って頑張っている.福島市では中合の紙袋を下げた人を多く見るので,中合のステータスは健在である.(2007,11)
No.17 珈琲グルメ(喫茶店)
福島駅前アーケード内のビル2階にムードのよい喫茶店がある.その名は「珈琲グルメ」.1979(昭和54)年にオープンした自家製焙煎の喫茶店である.店内の席は多くの女性たちで埋まっており,休日などは入り口で待たないと席につけないことが多い.カウンター席やテーブル席の他に,中央には十数名が座れる大きなテーブルがあって,少人数のテーブル席が空いていないときは,中央の大テーブルに相席で案内される.飲み物とケーキやデザートがついたセットの人気が高く,久しぶりにあった女性友達同士,つきることなく,そして途絶えることなくおしゃべりが続いていく.また,自分の好きなカップを選んで珈琲や紅茶などを飲むことができ,食べ物だけではなく,器も楽しみながら歓談をすることができる.店の空間もクラシカルで落ち着いておりムードも良い.そしてさらに,店員さんはイケメンの(!?)男性が多く,これもリピータの女性をとりこにしているのではないだろうか.駅前の中心市街地の衰退が叫ばれているが,本物を提供するお店には,人は繰り返しやってくるのであり,街全体として人々が望んでいる魅力ある商業空間を呼び込むことができれば,福島市だって賑わいは取り戻せるに違いない.(2007,11)
No.16 磐梯吾妻スカイライン
紅葉の季節がやってきた.磐梯吾妻スカイラインは紅葉の名所としても知られる有料道路で,高湯温泉から浄土平を通って土湯温泉までを結んでおり,国土交通省が制定した日本の道100選にも選ばれている.この有料道路をドライブしていると,作家の井上靖氏が名付けた吾妻八景(白樺の峰・つばくろ谷・天狗の庭・浄土平・双竜の辻・湖見峠・天風境・国見台)が次々と広がり,雄大な吾妻連邦の景観を満喫することが出来る.
通行料金は普通車1,570円である.道路地図や観光ガイドブックだけを眺めてこの値段を知ってしまうと,「ちょっと割高だな,有料道路はやめて一般道(国道115号)を走るか」などと思ってしまうかもしれない.しかし,まだ一度もこの有料道路を走ったことがないのなら,だまされたと思って走ってみることをお薦めする.空に突き抜けるように道が続き,崖のすれすれをスリリングに走り抜け,信夫山がぽっかり浮かぶ福島市街を一望し,硫黄の臭いが立ちこめて「火山性ガス注意,車を駐停車しないでください」の看板が現れると,緑だった山肌が一変して樹木の植わらない荒涼とした浄土平のダイナミックな風景が目の前に広がり,浄土平では湿原を散策して(湿原といっても荒れている.これだけ自動車や人が入り込んでいれば当然かもしれない),下りにさしかかると今度は磐梯山の屹立とした頂と猪苗代湖が眼下(磐梯山の頂は眼下というよりは水平といった感じである)に広がって,会津盆地がかすかに望める.次々と変化して過ぎ去っていく風景に感動を覚えるに違いない.
浄土平の標高は約1600mであり,福島市の標高が約65mであるので,福島市からやってくると実に1500mも車で登ってきたことになる.スカイラインまでの道のりには温泉街もあって日帰り入浴が可能なので,温泉とドライブをセットにした小旅行が堪能できる.開通は1959(昭和34)年である.今の時代だったら,大自然の中をダイナミックに貫くこのような道路は,環境意識への高まりもあって造れないと思う.ちなみに,浄土平の駐車場は有料で,吾妻小富士へのハイキング登山やレストランなどの施設を利用しようとする場合,さらに普通車410円が必要となる.4月下旬から11月中旬まで通行可で,冬期は積雪のため通行止め.(2007,10)
No.15 阿武急の日フリー乗車券
毎月第1日曜日は「阿武急の日」となっている.この日に限って乗り降り自由のフリー乗車券を大人600円(子供半額)で販売しており,福島-槻木間を乗り通すと通常片道940円であることを考えると,大変お得なフリー乗車券となっている.阿武急とは,第三セクターである阿武隈急行株式会社が運行している鉄道で,福島-槻木間の54.9kmを運行している.かつての槻木-丸森間を結んでいた国鉄丸森線を引き継いだもので,その後1988(昭和63)年に現在のように電化されて福島県側まで延伸開通した.阿武急は,阿武隈川に沿って走っていくので,富野駅を出発すると,左手に阿武隈川が見え始め,兜駅からはいままでの盆地の風景から一変し,渓谷の中を阿武隈川とともに併走していくようになる.あぶくま駅からは,阿武隈川船下りの乗船場も近い.
このフリー乗車券を発売する「阿武急の日」にあわせて,沿線自治体のイベントが催されることも多く,2007年10月の第1日曜日には,「伊達家ふるさとウォーキング(高子駅)」,「マイレールコンサート」,「角田ずんだまつり」などが開催されていた.特に,フリーウォーキングについては,年間スケジュールをたてて毎月10km程度のコースが設定されており,スタンプカードも発行されている.阿武急の日の車内にはリュックを背負った人(年配の方が多い)が多く乗車して賑やかになっている.槻木駅では,仙台駅方面のJR線との接続もよいので,追加で400円を支払えば仙台駅まで乗っていくことも可能である.精算は仙台駅で行うこととなる.仙台まで行くときに単調な景色に飽きていたら,たまには阿武急で阿武隈川の渓谷を見ながら行くのも悪くはない.(2007,10)
No.14 2種類ある高速バス「あぶくま号」(東京への高速バス)
福島から新宿(東京)までを結んでいる高速バスがあぶくま号である(片道大人4,800円,往復8,600円,ネット割引・早割あり).あぶくま号は,郡山や須賀川を経由して東京の新宿駅までを結んでおり,福島はその出発地となっている.あぶくま号は1日12往復運行されているが,福島から発着するのは1日6往復のみで,残りは郡山始発となっている.なにしろ,福島駅から新宿駅まで乗車すると所要時間が5時間以上かかるため,あぶくま号の利用者は郡山駅や須賀川・西郷からが多くを占めている.ホテルと新幹線がセットになったJRの旅行商品「TYO」を利用すれば,値段は倍以上するがホテルもついて約2時間で東京駅まで到着してしまい,また週末2日間だけ有効の「東京週末フリー切符(前日まで購入・大人14,500円・子供3,000円)」を買えば首都圏JRが乗降可能なフリー切符もついてくるので,時間の有効利用や疲労度を考えると,多少高くても福島から東京までは新幹線を選ぶ傾向にある.
福島からの高速バスには2種類の経路がある.ひとつは,福島駅を出ると福島西インターから高速道路に入り,本宮インターで降りて郡山駅に直行するタイプと,福島駅から国道4号を走って蓬莱・二本松市役所に立ち寄って,二本松インターから高速道路に入って郡山駅に向かう鈍行タイプの2種類である.新宿までの所要時間は,直行タイプで約5時間10分,鈍行タイプで約5時間35分となっている.なにしろ,須賀川・郡山・二本松と福島県内をほとんど一般道で縦断するので,国道4号線の蓬莱から坂を下るときに左の車窓に福島市街の街並みが見えたときは,「あれが福島の灯だ!やっと福島に到着した!」などと感慨深いものがこみ上げてくる.2006年12月からは福島北警察署裏あたりに無料駐車場を備えた福島高速バスターミナルを設置し,車利用によるパークアンドバスライドの実現を図っている.福島までやってくる高速バスはこの福島高速バスターミナルが起終点となっている.ただ,「福島高速バスターミナル」などと聞くと,冷房付きの待合室が完備された立派な施設を想像してしまうが,現地は待合室などはなくバス停がぽつんと立って広大な敷地(駐車場)が広がっているのみである.(2007,09)
No.13 飯坂温泉
さらにもうひとつ飯坂温泉も.福島駅から地方私鉄の福島交通飯坂線(地元では「いいでん」と呼ばれている)に乗って約20分走ると,終点飯坂温泉駅となる.摺上川の両岸に大小旅館が建ち並んでおり,約60軒の施設が存在している.大型のホテルや旅館,飲み屋もあって,東北でも有数の大規模な温泉街であったが,日本人の旅行形態の変化によって団体客が減少し,他の大規模温泉街と同様,現在は大変苦況に立たされている.温泉街に入ると廃業した旅館が多く目に付き,温泉街全体が沈降しているのがひしひしと伝わってくる.
共同浴場は9つあって,大人1人200円で入ることができるが,そのうちのひとつは松尾芭蕉も浸かったとされる鯖湖(さばこ)の湯も含まれている.共同浴場にはシャワーなどはない.泉質は単純泉で無色透明である.毎年10月の第1土曜日を中心とした3日間開催される「飯坂けんか祭り」は,日本3大ケンカ祭りのひとつと言われており,大きな山車が街中を練り歩いて飯坂八幡神社への宮入りを行ったあと,山車同士が勇壮にぶつかり合う場面は,見ていて迫力があり大いに盛り上がる.是非,飯坂へ.(2007,09)
No.12 土湯温泉
つづいて土湯温泉のご紹介.福島市と猪苗代町を結ぶ国道115号線沿いに土湯温泉はある.荒川の上流に位置する温泉街で,街の真ん中に渓流が流れている.泉質は単純泉がメインとなっているが,施設によっては炭酸水素塩泉や硫黄泉が含まれているところもある.源泉は約70カ所あるという.土湯温泉はこけしの里としても有名で,約160年前から伝統工芸が受け継がれている.温泉街にはこけしを製作する工程を実演している「土湯見聞録館」と呼ばれる施設があったり,ちょっと立ち寄るカフェがあったり,温泉たまごを販売する店があったり,無料の足湯スポットが4カ所あったりと,もともとコンパクトな温泉街は観光客がぶらっと楽しみながら歩けるように努力がなされている.土湯温泉は源泉が150℃前後と高温であり,温度調整のために加水をしているところが多いが,温泉につかると体がポカポカと温まってくる.強烈な湯あたりの心配もいらず,程よい心地よさの温泉である.各旅館では日帰り入浴をやっていて,観光協会の脇には日帰り入浴をやっている施設の情報が掲示されており,さらに観光協会では2人で1200円になる割引の日帰り入浴券を販売しているので,地図とともに入手するとよい.通常は日帰り入浴料は1人700円となっている(温泉施設によっては安いところもある).(2007,09)
No.11 高湯温泉
福島市周辺には車でちょっと走らせれば温泉が数多くある.そのひとつに高湯温泉がある.福島市から浄土平へ向かう有料道路・磐梯吾妻スカイラインの料金所ゲートのすぐ手前に約10軒ほどの温泉宿泊施設があり,坂道をぐんぐんあがった標高750mのところに位置している.特徴は,なんといっても「硫黄泉」の成分であるということ.正式な泉質名は,酸性・含硫黄-アルミニウム・カルシウム硫酸塩泉質(低張性-酸性-高温泉)であり,温度は42~51℃となっている.硫黄の成分含有では日本で有数の温泉で,効能が高いといわれている.源泉は10カ所ほどあるという.
白く濁った温泉に浸かると,体の芯から温まって,体に成分が効いている感じがする.ただし,少しでも多く成分を効かせようと思って,温泉成分を洗い流さずに浴場をあとにすることが多いかもしれないが,この高湯の硫黄泉は成分が非常に濃く加水加温をしていないので,最初は長い時間浸からずに成分を水道のお湯で洗い流して出ることを勧める.僕も欲を張って洗い流さずに出たら湯あたりを起こしてしまい,その後家に戻ってから倦怠感やだるさが出てきて,その晩はふとんに横になる羽目になってしまった.
高湯には組合で運営管理している共同浴場「あったか湯」が平成15年にオープンしており,大人250円で入浴することができる.駐車場からは源泉の配湯(分湯)状況が見れるようになっている.最近は「源泉掛け流し」という言葉が流行っているが,あったか湯のパンフレットには「自家自噴源泉完全放流掛け流し方式(加水加温無し)」と記載されているので,完全な源泉掛け流しということになる(ちなみに,加水していても一部循環させていても源泉を流していれば源泉掛け流しには該当する).なお,あったか湯は洗い場は少なくて石けんやタオルなどはついていない.広い浴場を希望する場合は,入浴料は高くなるが周辺ホテルや旅館の日帰り入浴を利用するとよい.くどいようだが,くれぐれも湯あたりにはご注意を!(2007,09)
No.10 共通駐車サービス券システム(中心市街地)
福島駅前の中心市街地では,買い物金額に応じて発行している駐車券について,約44の駐車場で共通して利用できる駐車サービス券を発行するシステムを導入している.駐車券を発行する加盟店舗は約274店舗(2007(平成19)年3月末現在).(株)福島まちづくりセンターが介在して,駐車場契約者からサービス券を回収し,加盟店舗にサービス券を発券するシステムとなっており,中心部のすべての大型店で加盟していて,車で中心市街地にやってくるのには大変便利なシステムである.共通システムがないと,商店の契約駐車場がそれぞれ決まっていて,はしごして買い物しても駐車券が利用できるところが限られてしまい,結局駐車場料金を払わなければならなくなることが多い.
加盟している店舗や駐車券には,下記のステッカーが記載されている.基本的に30分単位の発行であり,加盟店によって発券枚数は違っているが,中合やエスパル(駅ビル)などの大型店では1時間単位の発券を行っており(3000円以上で1時間,5000円以上で2時間が多い),中合デパートでは休日に限っては1500円以上の買い物で2時間無料の休日共通駐車券(休日しか使用できない)を発行している.これら全ての駐車券には有効期限があって,発行日より3ヶ月間となっている.
中心市街地でも結構品物が揃うので,極力駅前にきてぶらぶら歩いて買い物をするようにしている.お盆前の休日にはパセオ通りで花市をやっていて,お墓参り用の花(ユリ,リンドウ,ホオズキ,ふまんじゅう(食べ物)なんていうのもあった)やササなどを売っていたので思わず買ってしまった.また,会津のふるさとの盆提灯が古くなっていたので購入しようと思っていたのであるが,街中を歩いていたらサンチェ・イゲタでいいものがあったので,そこで購入した(この「いげた」の店は細長い店の中を小径として地下から半階構造の中2階方式でぐるぐると3階まで巡れるようになっていて,小物などの生活雑貨からカーテンまで品揃えがあって面白い).中心市街地の店の方は,商品のことを詳しく知っていて,いろいろと丁寧にじっくり教えてくれるように感じる.合理的な生産流通を行っているホームセンターやチェーン店のバイト店員とはちょっと違う.ちなみに,私が福島の中心市街地であったらいいと思っている店は家電量販店である.せめてヨドバシカメラのような店が駅前にあればいいのにな,と思う.消耗品であるMDやDVD,プリンタのインクや用紙なども,車で行かなければ購入できないようなので.(2007,08)
No.9 ぐう゛ぇ~,暑いぞ福島市は!
福島市の夏は「あつい」と聞いてはいたが,噂は本物,本当に暑い熱い日が続いている.日中の気温も午後になると35度近くにまで上がり,夜になっても気温は下がらず寝苦しい日が続く(25度前後).盆地特有の気候で,夏暑く,冬寒いといった傾向である.郡山市や会津若松市でも日中は気温が高くなるのであるが,福島市と違うのは標高が高い(標高200m程度)ため,夜になると20度弱くらいまで気温が下がって寝苦しさは若干和らぐ.夜の暑さは福島市の方がひどいのである.ちなみに福島市の標高は約66mとのこと.もう,クーラーが欠かせなく,夜寝るときも扇風機はかけっぱなしで,汗だくだくで寝ている.それでも,東京の夜の暑さに比べれば気温が低いと思われ,夜でも26~8度で推移するコンクリートジャングルの東京よりはまだましか,と思って自分を納得させている.この暑さが,全国第2位の出荷量を誇る「モモ」の栽培に適しているとのことであり,果物王国福島市を築いているのである(モモはうまい!).でも,早く秋が来ないかなぁ~.(2007,08)
No.8 コラッセふくしま
福島駅西口(新幹線側・中心市街地とは反対側)にある複合施設のビルが「コラッセふくしま」である.コラッセとは福島の方言で,こちらにお出でくださいという意味で,一般公募によって決められた名前である.公的機関の施設が入っており,住民票などが受け取れる市行政サービスセンターや,県パスポートセンター,県内各市町村の案内パンフレットが置いてある情報ステーションなどもある.日曜日も住民票やパスポートが受け取れるのでありがたい.
1階の観光物産館では,県内各地の名産やおみやげなどの物産を販売しており,ここにくれば県内の物産はある程度手に入れることができ,観光情報センターもある.お酒だってよりどりそろえてある.2階には市産業交流プラザがあって,福島市内にある企業の工場で製作されているものが紹介されている.そして,現在市政100周年の企画展示として,福島市の100年を振り返る写真展が開催されていて,これがとても興味深くて面白い.養蚕業で栄えた福島市であるが,明治・大正・昭和にかけて時代とともに写真で紹介されおり,市中心部の変遷や,掛田(霊山)まで路面電車が走っていた頃の写真,弁天山から松齢橋と市街地を撮影した写真,中合と山田百貨店と長崎屋と遠藤チェーンとコルニエツタヤと,まだまだ中心市街地が賑やかだった頃の写真など,企画展に終わらせず,常設展示として永遠に展示してもらいたい内容であった.
12階の最上階には創作和食料理のレストラン「Ki-ichigo・きいちご」がある.結婚式場のエルティが運営しているもので,山に囲まれた福島市街の盆地の眺望を眺めながら,ランチやディナーを楽しむことができる.12階にはレストラン以外にも,テーブルや椅子の置いてある無料展望室もあるので,高いところから福島を眺めるには絶好のポイントである.
この他にも,各種会議室やミニ図書館,中小企業を支援する経営プラザや商工会議所などがテナントとして入っており,駅前にある公的機関として便利な施設である.ちょっと余談であるが,このように市街地中心部に人を呼び戻す方策として,駅前に公的機関の窓口を持ってくる事例は増えているが,岩手県の盛岡駅前にある「アイーナ」では,県立図書館や運転免許センター,県民活動交流センター,パスポートセンター,県立大学のサテライト教室,大ホールなど,大規模で主要な規模の施設を一つの大きなビルに入れていて,規模の点では岩手県盛岡の方が上であると感じた.(2007,08)
No.7 かわまたシルクピア(川俣町)
川俣町は福島市から国道114号線で東南方面へ約22kmいったところにある町で,阿武隈高地の北部に位置する丘陵地帯である.古くから「絹の里」として栄えてきたところで,養蚕業や糸紡ぎ,機織りの技術は平安時代から伝えられているとされている.そんな川俣町の絹織物産業を展示する施設が,国道114号線沿いの「道の駅川俣」に併設されている「かわまたシルクピア」である.施設は3つの建物からなっており,絹織物産業についての文献や常設・企画展示展を行っている「おりもの展示館」,機織りや染色が実際に体験できる「からりこ館」,そして川俣町の物産を販売している「かわまた銘品館シルクピア」となっている.展示資料館は入館料150円とられるが,物産館(銘品館)は無料で入ることができ,桑の葉のソフトクリームや,特産品である川俣シャモ,絹製品などを販売している.実際展示してある絹製品を触ってみると,肌触りが全然違い,ポリエステルなどの生地と比較する展示もあって,いかに絹が肌触りがいいかを実感することもできる.(2007,07)
No.6 福島市内100円バス運行
これも市政施行100周年事業の記念イベントの1つとして行われたものである.2007年7月1日(日)に限り,福島市内を発着する路線バスは,どの区間まで乗っても1回100円で乗れるというもので,高速バスと自治体バスを除いた福島市内を発着する路線バス(福島交通・JRバス東北)が対象となっており,福島市を発着している路線であれば,福島市外まで乗車しても100円で乗車できるようになっている.せっかくの機会なので,川俣町の道の駅にある「かわまたシルクピア」に路線バスで行ってみた.
福島駅から川俣まではJRバス東北がバスを運行している.かつては川俣まで松川駅から国鉄川俣線が走っていたが1972(昭和47)年に廃止,その後の代替交通機関として松川・川俣間をJRバス(当時は国鉄バス)が運行していたが,これも今はJRバスが撤退し,自治体バスとして別会社が運行している.そんな関係からか,川俣地区はJRバスが走っている地域なのであるが,福島駅から川俣までのJRバスは,かつては浪江駅まで運行されていた福浪線の一部で,2004(平成16)年4月に問屋前・浪江駅間が廃止され,短縮した現在の形で運行されているものである.そんなJRバスに揺られ,川俣まで往復してきた.下車するときに,路線バスに関するアンケートハガキを運転手さんからもらった.
地方都市で公共交通に人を乗せるためには,現在のバス運賃では高すぎる.家族全員で休日にバスなどを利用して中心部まで買い物にいくとなると,その交通費がバカにならなくなり,駐車場代とガソリン代を払って自家用車で行った方がよくなってしまうのである.根本的に,自動車をやめて公共交通への利用促進を図るのであれば,公共交通を利用した方が経済的に安くなるようにしなければ利用者は増えるはずもなく,土日には今回のような「どこまで乗っても1回100円」,「大人最高運賃200円まで」,「大人半額」,「バスを利用したら購入製品の配送費用は半額」などといった思い切った施策をやらないと,バス利用への転換は図れない.環境負荷への低減も図れるのであるから,公共交通への補助制度をもっと導入してもよいように感じる.ちなみに,100円循環バスはすでに福島市内で導入されている.(2007,07)
No.5 ふるさと100周年・祝賀山車フェスティバル
今年(2007年)の福島市は,市制施行100周年の記念行事が目白押しである.2007年6月30日の夜に,市内全域からの山車を中心部に集結して練り歩く「祝賀山車フェスティバル」が開催された.福島市政施行100周年記念事業のひとつで,合計38台の山車(だし)が集結した.山車とは祭礼の時に飾り物をして引き出す車のことで,もともとは「出し物」の意で,神の依代として突き出した飾りに由来するのだという.国道13号線を全面的に通行止めにして祭りが行われ,市内各町内の山車が国道13号線に集結して,大きなかけ声と太鼓の囃子とともに練り歩く様子は,大いに盛り上がるものであった.
各町内の山車は色々な形,そしてお囃子のリズムがあって面白い.街路樹の樹木に当たらないように,山車の先端の部分をいちいち折りたたむのは,見ていて大変そうであった.山車の提灯の灯りも,発電機を積んで電球にしているものや,本物のロウソクを灯しているものなどあって,ロウソクを灯しているものは,ゆらゆらと光りが揺れるので風情が感じられるものである.旧長崎屋前の交差点では,最後に飯坂温泉の3台の山車による飯坂ケンカ祭り(岸和田のだんじり祭りとともに日本三大ケンカ祭りのひとつとされており,毎年10月第1土曜日に開催されている)のぶつかり合いも再現され,迫力ある山車の押し合いが見られた(でも,本物のケンカ祭りの時の方が,もっと山車がぶつかり合って盛り上がりは大きいと思われる.今回のはセレモニーである).
まだ梅雨が開けていないが,これからやってくる暑い夏に向けて,夏祭りの前夜祭的な感じがするイベントであった.余談だが,福島の夏は相当暑いと聞いているので覚悟をしているが・・・.祭りの模様はこちらへ.(2007,07)
No.4 仙台が近い(仙台行きの高速バス)
1日47往復,15分~20分おきに出ているのが仙台行きの高速バスである.片道900円であるが,10枚綴り回数券を使うと片道750円,往復1500円(2枚綴り回数券では往復1600円)で仙台まで行けてしまうのである.時間は約70分.週末になると買い物客で高速バスはほぼ満席,補助椅子を利用することもしばしばあって,平日でもビジネス利用客がおり,利用客が多い高速バスである.こうなってくると,福島市はすでに仙台圏内といった感じで,仙台に行く方がなにかと便利な地域である.仙台空港も,仙台駅から福島寄りの場所(名取市)にあり,近年の空港アクセス鉄道の開通もあって,福島空港を利用するよりも,仙台空港を利用した方が便利なくらいである.
これだけ仙台へのアクセスがよくなると,打撃を受けるのは福島市内の商店街である.ご多分に漏れず,福島市でも駅前などの中心市街地の衰退は激しく,屋台村を設置したり,イベントや祭りをまちなかで開催したりと,中心街へいかに足を運んでいただくかといった視点での取り組みがされている.花見山のシーズンには,まちなかでのイベントも開催して,駅からのシャトルバスの案内放送でPRしたりといった努力もしている.でも,品揃えの豊富さや欲しい商品が手に入るといった仙台の持っている魅力は,大きなものがある.なるべく,日用品など福島で手に入るものは,福島で購入するように心がけている.(2007,07)
No.3 アンナガーデン(聖アンナ教会)
国道115号線を土湯方面に走らせていき,ちょっと道を左に曲がって門をくぐると,小さなショップが建ち並ぶ夢のような空間が現れる.聖アンナ教会を中心として個性的なお店が並んでいるスポットが「アンナガーデン」である.吾妻連峰の山麓に位置しているので,緑が豊かであり,園内は坂を巧みに利用して個性的な建物が色々と建ち並んでおり,アイスクリーム屋,雑貨屋,パン屋,みちのく福島路ビール,英国アンティーク家具の店,うつわの店,喫茶店,駄菓子屋,ピザ屋,ソバ屋など,ぐるっと歩いていると結構面白い.
聖アンナ教会は,英国ブリストル聖ミカエル教会の格式を受け継いでいる教会で,伝統的な英国スタイルをそのまま復元した建築で,ステンドグラスは聖ミカエル教会からそのまま移設したものだとか.森の中のガーデンウエディングとして,結婚式も行うことができる.また,ここは高台に位置していることから,福島市内でも有数の夜景スポットである.家族連れ,カップルでどうぞ.営業時間は店によってまちまちであるが,大抵午後6時前後で閉店となっている.ちなみに,アンナガーデンの正門は午後9時で閉まる.入園料はなし.(2007,07)
No.2 福島県立図書館
住宅の広がる森合に県立図書館がある.正面に信夫山が迫る敷地内には,広々として開放的なスペースに建物が建っており,左側が県立美術館,右側が県立図書館となっている.1984年に現在の場所に移転しており,蔵書数は約70万冊である.県内で最も参考資料が充実している図書館であり,調べものがあったりするときには,県立図書館に足を運べば一通りの参考図書や様々な百科辞典を見ることができる.雑誌コーナーや分野ごとの一般図書も置かれており,一人10冊まで借りていくことも出来るし,県立図書館のホームページからは,蔵書図書の検索ができるようになっており,在庫があるか貸し出し中になっているか,さらに会員手続きをとれば貸し出し図書の予約までインターネットでできるようになっている.このように,資料館などの公共施設が充実しているのも県庁所在地の魅力であり,早速福島市に関連する地名辞典のコピーを行ってきたところである.
ちなみに,図書館と美術館の中間に喫茶&レストランがある.公共施設の店なので「それなり(1杯400円の天ぷらそば,500円のカレーライスなど・・・)の」メニューかと思いきや,ランチセットで1200円~1500円,ワンプレートランチで1000円程度といった本格的な料理を出す店であったので,味見は次回してみることにした.(2007,07)
No.1 ようこそ,花も「み」もある福島へ
福島市は今年,市政施行100周年を迎えている.「ようこそ,花もみもあるふくしまへ」は,福島駅の新幹線ホームやコンコースにピンクの垂れ幕が下がっているキャッチフレーズである.福島市は,1907(明治40)年4月1日に誕生した.県内では会津若松市に次いで2番目の市政施行であり,当時の人口は31,835人で面積は8.8km2であった.現在の福島市は,人口289,395人(H19.6.1現在),面積は746.4km2,市中心部には阿武隈川が悠々と流れ,信夫山(しのぶやま)がインパクトとしてそびえている.福島市を歩いてみてここ一週間程度の印象は,ファミリーが生活する場として非常に居心地のよい空間が広がっており,県庁所在地であるということもあってか,郡山のような殺伐とした商業地の都会というよりは,ゆとりのある落ち着いた住み心地のよい地域である印象を持った.これから,福島の見聞録をシリーズで掲載します.お楽しみに・・・.(2007,06)
(このページは2007年に掲載したものです)












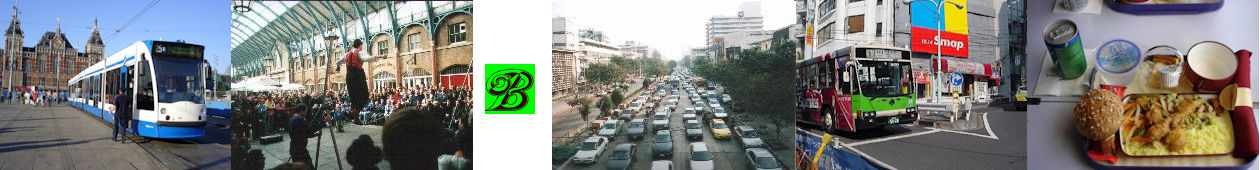
































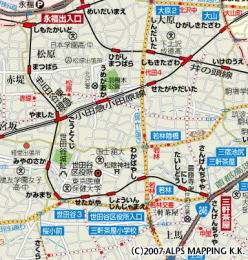
























































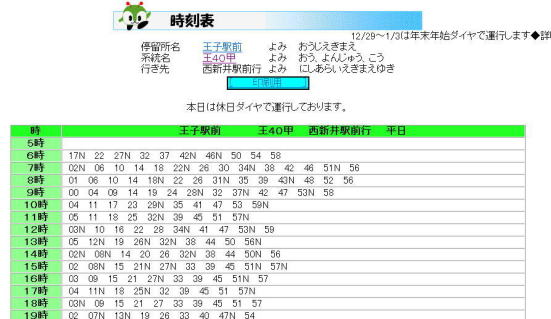




![福島見聞録【#1-#20】[一括掲載]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2011/03/paseo.jpg)























 ?
?












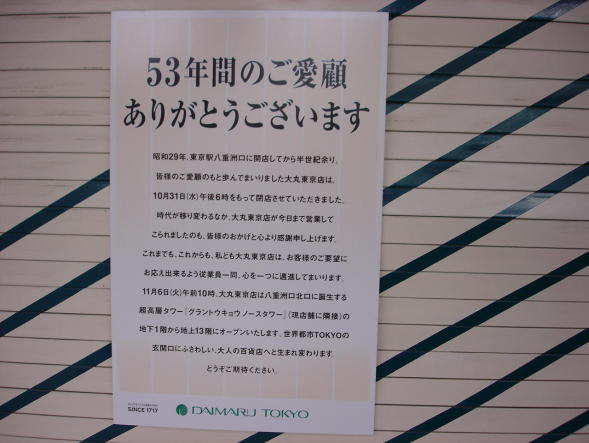


























































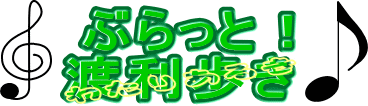



![エリア1[ぶらっと!渡利歩き]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/watari-map1s.jpg)












![エリア2[ぶらっと!渡利歩き]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/watari-map2s.jpg)
















![エリア3[ぶらっと!渡利歩き]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/watari-map3s.jpg)


















![エリア4[ぶらっと!渡利歩き]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/watari-map4s.jpg)





![エリア5[ぶらっと!渡利歩き]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/watari-map5s.jpg)


![エリア6[ぶらっと!渡利歩き]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/watari-map6s.jpg)










































![スタートまで[阿武隈川カヌー駅伝大会物語#1]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/DSC00097.jpg)



















![スタート→県境手前[阿武隈川カヌー駅伝大会物語#2]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/image911.jpg)



















