|
★ベルコリーヌ南大沢 1989(H1)年入居開始
★ライブ長池 1990(H2)入居開始
開発の行われる前の多摩NTは、畑や山が広がるのどかな丘陵地であり、このような街に大変身するとは、誰も想像していなかっただろう。その当時の写真や様子は、多摩ヴァンサンカンの展示室にて公開されている。タヌキやキツネがでそうな、雑木林であった。
参考文献 |
東京の街を写真と共にコラム形式で紹介. 東京は日本の顔であるとともに世界へ向けた窓口です.世界でも有数の大都市ですが,その中にも色々な街の表情があり,ひとつひとつ見ていくととても興味深いものがあります.そんな東京を紹介します.
|
★ベルコリーヌ南大沢 1989(H1)年入居開始
★ライブ長池 1990(H2)入居開始
開発の行われる前の多摩NTは、畑や山が広がるのどかな丘陵地であり、このような街に大変身するとは、誰も想像していなかっただろう。その当時の写真や様子は、多摩ヴァンサンカンの展示室にて公開されている。タヌキやキツネがでそうな、雑木林であった。
参考文献 |
|
1980年代前半 住環境の向上を図るため、多摩NTにタウンハウス(低層集合住宅)が建設された。多摩NTで最初にタウンハウスが建てられたのは諏訪地区(1979年)であり、続いて4年後に鶴牧地区で建設された。また、入居者がメニューの中から自分で設計するフリースペースを含んだ、メニュー方式による中層住宅も登場した。 ★タウンハウス諏訪 1979(S54)年入居開始 ★タウンハウス鶴牧 1982(S57)年入居開始 ★グリーンメゾン鶴牧 1983(S58)年入居開始
1980年代後半 この時代になると、アイデンティティー(個性・その人らしさ)を重視した街づくりが現れるようになってきた。プラスワン住宅と呼ばれる、通りに面して開かれたもう一つの部屋(フリースペース)を持つ住宅が登場し、キャラクタープランと呼ばれる、個性的な間取りが考え出されるようになった。また、マスターアーキテクト制を導入して、街全体を調和のあるデザインに設計された開発も登場した。 ★プロムナード多摩中央(プラスワン住宅) 1987(S62)年入居開始 ★ファインヒルいなぎ 1988(S63)年入居開始
参考文献 |

(出典:「多摩ニュータウン」パンフレット)
|
多摩ニュータウン(以下多摩NT)は東京都南部の多摩丘陵に位置し、標高150m前後、多摩市を中心に稲城市、八王子市、町田市に及ぶ東西14km、南北2~4kmの大規模な住宅開発地域である。京王相模原線を利用することにより、新宿から約35分で結ばれており、大都市東京のニュータウンとして、大阪の千里ニュータウンとともに、大都市の住宅供給を行ってきた開発である。 1960年代、日本の高度経済成長によって東京圏は都市化が急速に広がっていき、大量の勤労者が流入していった。それに伴って、住宅宅地需要が増加していき、中心市街地の地価の高騰によって、郊外である多摩地域でも無秩序な開発(スプロール化)が進行していった。このことから、居住環境の良い宅地・住宅を大量に供給することを目的として、1965(昭和40)年、「新住宅市街地開発事業都市計画」が決定、計画人口約30万人、総面積約2980haの多摩NT開発が行われることになった。
多摩NTの宅地開発は、施行者が土地を全面買収して宅地造成などを整備する事業(新住宅市街地開発事業という)と、所有されている土地を換地という手続きによって区画形質の変更を行って宅地としての利用を増進する事業(土地区画整理事業という)によって行われている(道路や下水道などの整備は関連公共施設整備事業によって行われている)が、多摩NTでは前者の土地を全面買収することをメインとして宅地造成をしており、歩車分離を徹底させた(ラドバーン方式)道路構成やバランスのとれた建物や公園の配置など、開発設計思想の反映された個性と魅力のある面的な住宅開発がされている。 新住宅市街地開発事業の施行者は、都市基盤整備公団(前住宅・都市整備公団)、東京都住宅供給公社、東京都によって行われている。 1970年代前半 多摩NTで最初に入居開始された地区が諏訪・永山地区であり、その翌年に入居開始されたのが和田・愛宕東寺地区である。「安く良質な住宅を、早く大量に供給する」という時代であり、箱形の中層住宅(5階建て)が平行に建設され、ポイントには高層住宅(14階建て)も建設された。 ★諏訪・永山団地 1971(S46)年入居開始
1970年代後半 ★貝取・豊ヶ丘団地 1976(S51)年入居開始
公団住宅の入口は開放的で入りやすい。それは、居住者以外の人も入りやすいということであり、そういう構造上のこともあってか、公団の団地というのは、壁への落書きやエレベーターボタンのいたずら(ライターでプラスチックのボタンを溶かしてしまう)が多いように思う。
新住宅市街地開発事業で整備された区域内では、中学校区を基本的な単位として、幹線道路を境界に「住区」と呼ばれるブロックに分けられている。
参考文献 |
The fish market in Tsukiji (inside market)
 築地市場正門 築地市場正門 |
 |
| 「築地の魚河岸」は有名である。それは、築地に東洋一の取扱量を誇る中央卸売市場があるからである。現在の築地の魚河岸(築地では青果も取り扱っている)は、関東大震災後に江戸時代より日本橋にあった魚市場を海軍兵学校跡地に移転したことに始まる。中央卸売市場の中を「場内」と呼ぶが、場内では小売りは行わずに原則として仲卸業者へのみの販売となる。小売りは「場外」と呼ばれる晴海通り沿いの市場で行っている。
築地に来たら、絶対に場内へ入ってみるべきである。この中に一歩足を踏み入れると、ここが日本なのか!と驚くほど威勢と活気と躍動感に満ちあふれており、気分が高揚してくる。この場内の風景を眺めていると、つくづく日本もアジア人だなと感じずにはいられない。とにかく、けたたましくて騒々しい。東京のエネルギーを十分すぎるほど肌で感じることができる場所である。 この築地市場は都市計画市場として位置づけられているが、場内の老朽化や手狭な敷地を解消するために、平成24年に豊洲への移転話が決定しており、この計画に反対運動も起きている。築地の魚河岸が過去の話として語られるときが、もうすぐそこまでやってきているのである。また、移転先の豊洲の埋め立て地において、土壌にベンゼンやヒ素などの有害物質が検出され、安全性の面からも移転反対の議論が沸き起こっている。 ちなみに、場内へは誰でも入ることができ、外国人観光客の姿も目にすることができる。一般者が見学するには、一段落する午前9時過ぎがちょうどいい時間であろう。が、ぼやぼやしていると場内を走っているリアカーやターレット車と呼ばれる三輪自動車にひき殺されそうになるので注意すること。すきがあればどんどん割り込んでくるし、待っているだけではいつまで経っても通路を横断することはできない。ぼけっと立っていると「ちょっとどいてー」と大声をかけられることになる。邪魔をしないように・・・。 動画コーナー 場内の様子1 (交差点の喧噪) 交通整理員が役目を果たしているのか・・・?不明. 場内の様子2 (交差点の喧噪)
場内の様子3 (建物内の喧噪)
|
The fish market in Tsukiji (outside market)
 |
| 「築地の魚河岸」は有名である。それは、築地に東洋一の取扱量を誇る中央卸売市場があるからである。中央卸売市場の中を「場内」と呼ぶが、場内では小売りは行わずに仲卸業者へのみの販売となる。個人客は、その市場の隣(中央卸売市場の晴海通り寄り、築地4丁目交差点に向かった側に広がっている)にある「場外」と呼ばれる市場で購入することになる。魚はもちろん、包丁屋、かつお節屋、卵焼き屋、漬け物屋など、さまざまな小売店が並んでおり、アジアチックな市場を形成している。
年末は,人でごった返し,大混雑となる.身動きがとれない. |
End-of-the-year illuminations (at Marunouchi)
 |
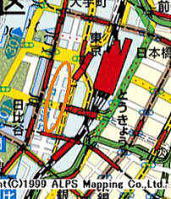 |
| この「東京ミレナリオ」は、12月24日から1月1日まで開催されていた光の彫刻である。 主催は、東京2000年祭実行委員会(会長 : 稲葉興作 (東京商工会議所 会頭)、名誉会長: 石原慎太郎 (東京都知事)) と東京ミレナリオ実行委員会(会長 : 植松敏(東京商工会議所 専務理事)、名誉顧問 : 木村茂 (千代田区長))との共同で開催されたものである。
|
The ‘special dining-room’ and a ‘elevator’ at Nihonbashi TAKASHIMAYA
 |
| 日本橋にある高島屋。重厚な建物の中に入ると、高級感あふれる大人のデパートといった感じがひしひしと伝わってくる。ジーパンでお買い物がしづらい雰囲気である。休みの日になると(夫が働いている平日の昼にグループで来る人が多いという)、マダムたちがお目当ての高級ブランドを求めてお買い物をし、さらに4階にある「特別食堂」で昼食をとるのがパターンとなっている。 日本橋高島屋には、6階に「お好み食堂」というのがあって、こちらは普通の大衆的な値段(といっても最低でも1000円前後はするだろう)の食事が味わえる。一方で、4階に「特別食堂」などという昭和初期の戦後を思わせるような陳腐的なネーミング(それがかえって良い)の食堂がある。なにが特別かって、メニューが特別なのである。安くても3500円程度の懐石弁当であり、8000円のコースまであるブルジョワジーの食堂である。 照明の落とされた入り口を通ると、クロークに鞄やコートを預け、人数を係りの人間に伝える。机と椅子が並べられている待合室でメニューを見ながら名前が呼ばれるのを待ち、独特のかけ声で名前が呼ばれると席へと案内される。洋食の帝国ホテル、和風割烹の三宮、うなぎの野田岩の3店が入っているが、同じフロアーでそれぞれの料理を注文することができる。まわりを見渡すと、お金持ちそうなマダムたち、ご夫婦、ご家族連れと、みんなみんな上品に見えるから不思議である。おすすめ料理として、うなぎのかさね重(3900円)というのがあり、上段に蒲焼き(天然物であろう)、下段に白焼き(炭火で焼いただけのもの。わさびと醤油で食べる)が入っている膳がある。茶托のついたお茶が3杯も交換された。一度おためしあれ。
もうひとつ、老舗の日本橋高島屋には面白いものがある。それは、かなり年代物の「エレベーター」である。エレベーターの扉は、外側と内側に2枚あるのであるが、内側の扉が真鍮の檻のような格子でできており、じゃらじゃらと音を立てて扉(と言えるのだろうか)を閉めるのである。かつては、日本橋三越や池袋三越にもあったが、メンテナンスが大変であるとのことで、三越では透明なガラス張りの近代的なエレベーターに変えられてしまった。そういった点で、高島屋はえらい! もうちょっと前までは、違った種類の古いエレベーターがあったように思うが、そちらの方はなくなってしまったようである。回数を表示する部分がランプではなく、時計の針のような矢印で表示していた。これらのエレベーターは、世界で最初にエレベーターを発明した「OTIS オーチス」社製のものである。運転はエレベーターガールによって行われ、ハンドルを倒すと扉が閉まり、左に回すと上へ、右に回すと下へ動き出す。ハンドルをあげると次の階で停止するようになっている。
それでは、みなさま、ごきげんよう。 |
 六本木駅前 |
 |
| やはり六本木は夜の街である。もう正午近いというのに、街の雰囲気はまだ「明け方」と言った感じである。六本木には外国人が多く出没するが、大使館関係の人などのお金持ちの外国人が多いように思う。また、テレビ局の多く存在する赤坂等の都心と芸能人の多く住む目黒・世田谷区の中間地点に位置する六本木は、必然的に芸能人も多く出没するスポットである。
|
 |
 |
| 「麻布十番」と聞くと六本木から鳥居坂を下ったところにあるため、芸能人御用達の飲み屋が並んでいて、敷居の高い街に思えるが、江戸時代から続く、下町情緒の残る商店街である。
麻布十番という名の由来にはいくつかの説がある。 1.延宝3(1675)年に江戸幕府が近くを流れる古川の改修工事を行った時、この地点を河口から10番目の工区とし表示の杭が後年まで残り地名になった 地元では「十番」という呼び名が俗名として使われていたが、地番としては残っていなかった。昭和37年に「麻布十番○丁目」などという町名が復活したのである。
麻布十番の面白いところは、一本路地裏にいったところに、ちょっとした小さなお店(飲食店)が存在していることである。マンションの階段を上っていって4階のドアをあけると、個人で経営している多国籍料理店になっていたり、と歩いて見つけるのもまた楽しい。 |
Musashi-Koyama shopping center
 |
 |
| 東急目黒線武蔵小山駅前から中原街道まで、約750m(都内最長)にも渡って続くアーケード街がある。武蔵小山商店街・パルムである。たびたびテレビでも紹介されている商店街だが、ここに来ると身の回りのものは何でもそろってしまい、ただ歩くだけでも楽しい商店街である。昨今、大型店の出店により、駅前の小さな近隣商店街は苦境にさらされているところが多い中、ここは商店主や組合の努力が功を奏し奮闘している商店街である。 足を踏み入れてみると、商店主の方々の「売ってやろう」というやる気が感じられ、店先に出て呼び込みや店頭販売を行い、商店街の活気を盛り上げている。お互いが刺激しあって、商店街全体を盛り上げている感じがする。その地域を生かすも殺すも、そこに生活して活動している人々の努力の結果なのである。
武蔵小山商店街は目黒区との区界に近い品川区小山・荏原に存在している。目黒区といえば芸能人が多く住む気品の高い住宅地を連想するが、目蒲線(現目黒線・多摩川線)、池上線沿線は、下町的な風情の残る地域となっており、ここ武蔵小山商店街も歩いていると下町的な雰囲気を堪能できる街である。
|
Ameya Yokocho (at Ueno Okachimachi)
 JR御徒町駅前のアメ横入口 |
 |
| 「アメ横」を知らない人はいないだろう。大晦日になると必ずといっていいほど、TV中継がされる商店街である。正式にはアメヤ横丁というが、戦後アメリカのものを売っていたことからこの名がついたという。なにしろ、このアメ横は普通の商店街を超越していて、アジア人としての日本を意識せずにはいられなくなる。混沌としたカオス状態なのである。魚屋のとなりに洋服屋があり、乾物屋のとなりでゴルフのクラブを売っている・・・。このアンバランスさと混沌とした状態が、いかにも「アジア」的でエキゾチックなのである。そして、この混沌とした風景に接したとき、なぜかホッとするのは、僕だけではないだろう。やはり、我々はアジアの中の日本人なのである。
アメ横で買い物をするとき注意することがひとつある。それは、「本物を見極める目を養うこと」である。なにしろ値段が安いので、ついつい手を出したくなってしまうが、なかには縫製が甘かったり、鮮度の落ちたカニだったり、バッタものに出くわすことがある。ただ、元々値が安いのを承知で買っているのだから、それはそれとして、買い物を楽しむのがアメ横である。
|
 |
 |
| ルビー通り、ダイヤモンド通り、ひすい通り、サファイヤ通り・・・、女性であれば目が輝いてしまうような名前が通りに付けられている。この辺りは、貴金属・宝石の問屋が集まるところであり、別名「ジュエリータウン」と呼ばれている。結婚が決まって指輪を贈るとき、この街で指輪を購入し、近くの韓国人街でキムチを買って、アメ横で夕食のおかずを買って帰るのも悪くはないのでは。
|
The Tokyo harbor ferry terminal
 |
|
東京港から出港するフェリーは、東京ビッグサイト南側に位置するこの有明フェリー埠頭から出航する。那智勝浦・高知、徳島・新門司とを結ぶ航路が存在するが、かつては北海道の苫小牧、釧路航路も存在していた。現在、北海道へフェリーで向かいたい場合、茨城県の大洗港から室蘭、苫小牧まで向かうことができる。
|
Asakusa Kaminari-mon and Nakamise, Koen-rokku
(The town where the Edo culture of old Japan remains)
 |
| 今の浅草は、外国からの観光客が必ず立ち寄る国際観光地となった趣があり、古き良き東京、江戸情緒を残す街として、賑わっている。昭和初期や戦後時代には、日本の流行発信地として、現在の渋谷・新宿に匹敵するような大繁華街を形成していたが、東京の繁華街は西へ西へと移動していき、斜陽化する浅草をなんとか復活させようと、数々の祭りを催したり、新しいタイプのホテルやビルを建てたりし、往年の繁華街の復権に力を入れている。
浅草公園六区の「六区」とは、明治15(1882)年より始まった浅草公園の築造・整備(全6区画に区分して整備)における区画番号のことである。その中でも第6区画は興行街として整備され、そのまま「浅草公園六区」という名称が東京の娯楽の代名詞のようになったのである。バス停の名称に「浅草公園六区」という名が今でも残されていることに拍手を送りたい。映画館は明治40(1907)年頃から登場し、現在も残る浅草六区の映画街が形成された。
|
Tokyo International Airport (Haneda Airport)
 |
| 羽田空港は、正式には「東京国際空港」という。成田空港は「新東京国際空港」。1978(昭和53)年に成田が開港するまでは、羽田が東京の国際空港も担っていた。 現在の羽田空港は、空港機能の増強と航空機騒音問題を解決するために沖合に移転拡張して大きさを過去の3倍にした24時間空港であり、新旅客ターミナルは1993(平成5)年にビッグバードの愛称でオープンした。年間の離着陸処理能力は約23万回であり、滑走路は新A滑走路(3000m)、新B滑走路(2500m)、新C滑走路(3000m)の3本である。さらに、沖合に桟橋方式の海上空港を建設するよう、東京都が運輸省に要望を行ったところである。首都圏第3空港などの議論が行われているが、東京都心からのアクセスを考えれば、羽田に勝るところはない。
|
Baseball Tokyo Giants team championship parade(in Ginza Nihonbashi)
|
2000年秋、6年ぶりの日本一、長嶋監督率いる巨人軍の優勝パレードが、大手町から日本橋・京橋・銀座まで走り抜けた。約34万人の人出となったが、何の混乱もなく無事終了した。
|
 |
 |
| 白バイの赤ランプがピカピカ光り、一見すると交番のような面構え、ここは警察博物館である。何も悪いことはしていないのに、入るのを躊躇ってしまうのは、僕だけではあるまい。あまりお金がかかっていないような展示の内容であるが、制服の変遷や、警察の歴史、運転シュミレーター、各都道府県警のエンブレム、実物の辞令、鑑識調査の道具、警察手帳などの道具が展示されている。中でも目を引くのが、いままでの殉職者の写真と、その時に着ていた血痕のついた制服、ナイフで切り裂かれた制服(どちらも本物)が展示されており、警察官という任務のシビアな面も感じることができる。わざわざ足を運ぶほどの展示ではないが、銀座に買い物に行ったとき時間が余っているのなら、ちょっと寄ってみるのも悪くはない。中央通り沿い、京橋の首都高速の高架橋下近くに存在する。
|
Harumi Futo (passenger liner wharf)
 |
| 東京の海の玄関にふさわしい建物をと、昭和63年9月より着工し4年の歳月をかけ建設されたのが、晴海客船ターミナルです。近年のクルーズ人口の増加と客船の大型化に対応した先端の技術と安全性、そして斬新なデザインが与えられ、東京港開港50周年となる平成3年5月に完成しました。---
と、パンフレットには書いてある。つまり、2万トン級の豪華客船、にっぽん丸やふじ丸、飛鳥などといった大型客船を係留するための埠頭であり、世界各国の豪華客船や軍船を見ることができる。館内には、今月の入港船一覧表(時刻)が貼ってあるので、お目当ての船があれば、見学することもできるだろう。苫小牧や四国・九州方面へのフェリーは、この埠頭からの出航ではなく、有明にあるフェリー埠頭ターミナルより出航する。晴海埠頭は、あくまでもクルーズ船などの豪華客船が主である。建物は東京都の施設である。
|
Scenery from the Uguisudani station

|
JR鶯谷駅のホームから撮影した風景である。こう堂々と人目につくところにホテル街があるのは珍しい。普通は、人目につかない繁華街の奥の方に、忽然ときらびやかに姿を現すのがラブホテルであろう。夜になると、山手線や京浜東北線の車窓から怪しいネオンを拝見することができる。
|
Den-enchofu (overly high-class residential street)
 |
|
田園調布、誰もが一度は住んでみたいと思う憧れの高級住宅街である。田園調布は1923年(大正12年)に田園都市株式会社(現在の東急電鉄)の民間ディベロッパーによって開発されたところである。
ちなみに田調は、世田谷区ではなく大田区である。 |
| アジア最大の歓楽街である新宿。夜の新宿を点景でお伝えします。
|
Toden Arakawa Line (only streetcar in Tokyo)
 明治通りを走る都電 新幹線MAXの下をくぐる |
| かつては縦横無尽に都内を走っていた都電であるが、モータリーゼーションの波には打ち勝つことができず、昭和42年~47年までの間に、この荒川線を残して全廃してしまった。この荒川線も廃止の予定であったが、専用軌道が多く代替交通機関がないこと、地元からの強い要望があったことにより、存続することになった。当時は、赤羽-王子-三ノ輪間と荒川車庫前-王子-早稲田間の2系統あったものを、赤羽-王子間を廃止して、1本化したもので、この時に荒川線という名が生まれた。
三ノ輪橋停留所は商店街に埋もれるように行き止まりとなっている場所である。この何とも言えない雰囲気が最高である。都電を降りると下町の商店街が目の前に広がり、小さいチンチン電車は街の中にすっかり溶け込んでいる。関東の駅百選に選定された。
都電が道路の上を走るのは、王子駅前-飛鳥山間と小台-宮ノ前間のみである。小台-宮ノ前間は、道路拡張が進み、もうじき道路中央に専用軌道が完成する見通しである。都電の車体には入口にステップがないので、ホームを設けなければならないが、段差がないので車椅子でも楽に乗ることができる。
都電の運賃は大人160円である。乗るときに160円を運賃箱に入れる前乗り先払いとなる。しかし、朝のラッシュ時には運転手一人では多くの乗客をさばききれないため、朝の王子駅前では、車内にある運賃箱をホームに置いて臨時改札を行っている。
この区間は、飛鳥山と音無川に挟まれているため、専用軌道になる見込みはない。明治通りの6車線の急坂を、車におされながらそろりそろりと走っていく。雨が降ると車輪が空転し、上らなくなってしまうことがある。そんなときは砂をまいて走っていく。 4のつく日には巣鴨とげぬき地蔵の縁日となり、最寄の庚申塚停留所は大混雑する。都電はお年寄りにもやさしい乗り物で、地下鉄のように階段もなくすんなりと乗れるし、手軽に気軽に乗ることができる。世界的にこのようなライトレールの路面電車が見直されているのは、地球にやさしく、人にやさしい乗り物だからである。 線路の脇に勝手口がある、こんな家がたくさんある。この踏切には遮断機も警報機もついていない。まわりが静かなので、電車がやってくると、線路を伝って「カタンコトン、カタンコトン、カタンコトン…」と段々音が大きくなってきて、電車が近づいてきていることを知る。
下町ばかりを走っているように感じられる都電であるが、早稲田付近ではビルの林立する中をとことこ走っていく。サンシャイン60をバックに都電は快走する。
チンチン電車とは、発車するときに「チンチン」と鐘がなることに由来する。もともとこのベルは、車掌さんが運転手さんに「乗降が終わって発車してもいいですよ」という合図を、紐を引っ張って鳴らしていたもので、車掌がいなくなってワンマン化された現在、あっても無くてもいいベルなのであるが、自動の電動ベルを車内に取りつけて、いまでも「チンチン」と鳴らして走っている。自動化してまでもこのベルを残そうと決断した当時の担当者(都の交通局か)にはユーモアと生きることに対するゆとりがあるように感じる。 |
Pedestrian paradise (driveway only for pedestrians)
 秋葉原電気街の歩行者天国(中央通り) |
|
子供の頃、車を通行止めにして車道の上を歩行者が歩ける歩行者天国を見て、なんてすごいことができるのだろうか、と感慨にふけった記憶がある。これこそ中心市街地活性化の一番の切り札であり、もっともっと導入されるべき施策である。
|
The open space in front at the Akihabara station
(the Kanda vegetable and fruit market former site)
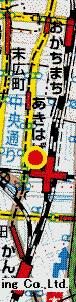 |
 |
| JR京浜東北線や山手線の車窓から見た覚えのある光景だろう。ここにはかつて、神田青果市場(現在は大田市場に移転)があったところで、その跡地には、広大な駐車場と広場がつくられた。その広場では、時々イベントなどを開催しているのだが、それ以外の日には、スケボーを練習する若者やスリーオンスリーをやる若者など、どこからともなく若者が集まって汗を流している。 考えてみると、東京の都心部では、このように自由にできる平たい空間はなくなってしまっている。この光景は、都会の中のヒトこまとして、非常に印象に残るものである。 また、ここに集まってくる若者達は、見られることを意識しているのかもしれない。大勢のギャラリーはいないのであるが、電車からは丸見えだし、通行人からもよく見える。あまり下手くそな人は恥ずかしくて、ここでは遊べないかもしれない。 なお,現在は再開発工事が始まり,広場はなくなって立体駐車場となっている.
|
Housing redevelopment (in Minamisenju Shioiri)
 上部の細い道路がかつての街路 |
 |
南千住汐入(しおいり)、ここはかつて隅田川の中州だったところで、昔ながらの東京の風景を色濃く残す街だったところである。「東京23区物語」泉麻人著の中でも語られているとおり、この街は迷路のように細い路地が曲がりくねり、昭和30年代の東京の風景を色濃く残す地域であったところである。「あった」と過去形になっているのは、この隣に草ぼうぼうの日紡の工場跡地があったのだが、その跡地とともに再開発が行われ、現在では高層住宅が建ち並ぶ住宅団地が形成された。街の様子が一変したのである。住宅地再開発の事例として、「東京考察」に取り上げた。


再開発された街並み
取り壊される家。この家に住んでいた人々は、隣の高層住宅に移り住んだのであろうが、長年住んだ自分の家が取り壊されるのは、見ていてつらいであろう。

取り壊される家 防災の日の訓練にも使われた
かつての汐入の風景。1991(H3)年に訪れた時の風景。




京都都市計画事業白髭西地区 第二種市街地再開発事業
この事業は、震災対策の一環として防災拠点の整備を図るとともに、地域特性を考慮した生活環境の改善及び経済基盤の強化を図ることを目的としています。
計画内容は、混在した住・商・工を計画的に再配置し、安全でうるおいのある住環境を目指すとともに、隅田川と一体となった総合公園や近隣公園を整備します。また、災害時の避難路をなる都市計画道路をはじめ、各種の生活道路や学校・保育所・コミュニティー施設等の公益施設を整備し、水と緑の豊かな安心して住めるまちづくりを行います。
工事現場に掲げてあった看板の文面。
The department store closing sale at ‘Yurakucho SOGO’
 入口は1カ所のみ スピーカーで案内する社員 |
| 経営破綻により閉鎖が続くそごう店舗。有楽町で逢いましょうでも有名な、庶民派デパートの老舗「有楽町そごう」も閉鎖が決定され、2000年9月3日から17日まで、閉店売り尽くしセールが開催されることになった。10万円の商品が1万円台になったり、1万円の商品が500円になったりと、破格のバーゲンセールであり、また、マスコミでも取り上げられたこともあり、初日の今日は2時間待ちの大混雑となった。 有楽町は、銀座数寄屋橋に有楽町マリオンが出現してから、人の流れが一層マリオン・銀座方面へと流れるようになった。銀座の復権とも言われ、線路を挟んで銀座の反対側に位置するそごうは苦戦を強いられていたと思う。さらに追い打ちをかけたのが、都庁の新宿移転。やはり商業施設の成功は、人の流れをどのように読むか、また、呼び込むか、これに尽きる。 中に入るのはやめて、そとの行列の模様をお伝えします。閉店は24日だということです。
東京国際フォーラム(元都庁跡)の中庭だけの行列かと思いきや、そのまま地下鉄入口の階段に列は続き、地下鉄コンコースをぐるーっと大回りする大行列であった。これでは2時間待ちである。
JR有楽町駅には「そごう口」という出口がある。そごうが閉店してしまうと、名称が変わるのだろうか。
|
Marunouchi (Otemachi) and Imperial Palace Plaza
 国道1号と丸ノ内 |
 |
| 丸ノ内の景観と皇居前広場の空間は、非常に好きな場所のひとつである。皇居前広場にいると、こんなに空が抜けるような開放的な空間が都心にあったのか、と改めて驚愕する。そして、その広場から丸ノ内のビル群を眺めると、「さすが日本、ここまで成長したのだなー」、という感慨深いものが皇居を背にしながらこみ上げてくる。 丸ノ内のオフィス街は、江戸時代には譜代大名の屋敷地であったところを、三菱地所の岩崎弥之助に払い下げて、民間資本によって一大ビジネスゾーンが建設されたのが始まりである。日本の近代都市計画において都市設計思想の感じられる最初の開発ではないだろうか。現在では超高層ビルが建てられるようになったが、かつての旧建築基準法では建物の絶対高さ31mの規制があり、なおかつ美観地区の規制もかかっているため、ビルの高さが一致した看板広告の見られないすっきりした街並みが形成されている。重厚な安定感のある景観である。ただ、ネガティブな意見として、夜になると誰も人が歩かない地域になってしまい、人間らしさの感じられない街である、といった意見もある。 そして、その隣の皇居前広場には、ここが都心なのかと疑うほどの、広い広い空間が果てしなく広がっている。ここを歩いている観光客は外国人観光客が多くみられ、韓国などのアジア各国からの観光客も多い。
|
 銀座4丁目交差点 和光の時計台 |
| 夜の銀座。ネオンが輝き、本当に日本は不景気なのか、と思わせるほどの明るさである。銀座は、渋谷・新宿の喧騒とは違って、どことなく落ち着きのある街であり、高級感ある大人のムードを味わえる街である。
左側車線は客待ちするタクシーが並んでいる。後ろを走るバスの行先表示板が赤色になっているのは最終バスを意味する。ちなみに都営バスでは、最終の1本前のバスは緑色のランプを光らせて走る。
夜11時を過ぎているが、人通りが絶えない。終電に間に合うように、人々は駅へ向かう。
大都市の工事は、交通量の減る夜間に行われることが多い。ここでも下水道工事が行われていた。カメラを持った外国人観光客の姿も目立ち、この工事の模様をビデオに収める人もいた。
パントマイム。
高級クラブの並ぶ、銀座6・7丁目界隈。ママさんがお客さんを見送るため、下に降りてくる。
おまけ…
|
The DOJUNKAI apartment at Edogawa
 |
同潤会アパートのことを取り上げたところ、反響が多かった。
現存する同潤会アパートは、「三ノ輪」「上野下」「清砂通」「大塚女子」、そして今回紹介する「江戸川」、前述の「青山」のみである。なにしろ、老朽化が激しく、雨漏りはするわ、ガスや水道の配管は腐敗してるわ、電気のアンペアは10A、風呂なし、などという条件が重なって、どのアパートでも建て替えの話が持ち上がっている。2001年11月の江戸東京博物館(両国)では、建築-都市の企画展を計画しているようで、その中で実物大の同潤会アパートの部屋を再現する予定だという。 そしてついに,ようやく建て替えの話しがまとまり,11階建てのマンションになることが決定した.またひとつ,鉄筋コンクリート住宅の歴史的遺産がなくなることになる.是非,建て替えの前に一般公開していただけないか,切に願うものである.
|
Scenery of ‘San-ya’ (a day laborer’s town)
 |
| 山谷(さんや)。日本の高度経済成長における国土建設、そして現在も発展を続ける東京。この発展を本当に支えていたのは、ここに暮らす人々なのではないだろうか。
1泊2000円代の簡易宿泊所が軒を連ねている。朝5~6時には手配師がやってきて,その日の仕事が決まる.
やはり人生の楽しみは「酒」。スタンド飲み屋があちこちにある。山谷地区交番では、人々を刺激しないよう私服によって勤務している。
地域ぐるみでの環境美化に努めているのだが…。横断歩道は関係なし…。
|