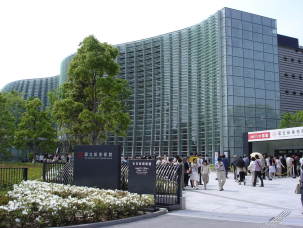No.40
年齢 = 30-39歳
性別 = 女性
件名 = がんばってください
メッセージ = はじめまして。
他県へ嫁いだ者です。偶然ここのHPを見つけて、なかなか実家へ帰れないものでとても懐かしく見ました。古い時代の写真も「そうだ、そうだった」としみじみ見ました。新しい店も増えたようで知りませんでした。今度帰省するときには寄ってみようと思います。更新がんばってください。楽しみにしています。
【お返事】
アクセスありがとうございます.実家はどこなのでしょう? いろいろな地域を掲載していますので,福島県なのか,東京なのか,はたまた外国だったりして・・・? 今後ともアクセスよろしくお願いします.(2007,09,10)
No.39
年齢 = 50-59歳
性別 = 男
地域 = 福島県
件名 = ブラボー脱帽です。
メッセージ = これはヒットします。
絵柄がきれいで言葉も自然体で癖がなく読みやすいです。 お気に入りに登録します。
【お返事】
アクセスありがとうございます.これからも自然体でいきたいと思います.アクセスよろしくお願いいたいます.(2007,04,11)
No.38
年齢 = 50-59歳
性別 = 女性
地域 = 福島県
件名 = 残念!
メッセージ = 偶然見つけて 楽しく読ませて頂いてました。
「郡山見聞録」!とても残念ですが今まで ありがとうございました。
【お返事】
郡山を離れることになりました.いままでアクセスありがとうございます.福島市へ引っ越ししたのですが,ホームページは引き続き更新を続けていきます.今度は,福島市の新たな情報発信として,ご期待ください.(2007,06,30)
No.37
性別 = 女性
年齢 = 30-39歳
お気に入り = ブログ「とでも、とでも。」 郡山見聞録 東京考察
メッセージ = はじめまして。
偶然このサイトを見つけてから日参しています。
特に郡山見聞録は私も関心のある記事が多く、興味深く読ませていただいてます。
最初にこのサイトを見た時には感動したくらいです(笑)
デザインをいまいちとしたのは、郡山見聞録のページについてです。
どうしても青地に白の文字が読みにくく、いつも文字を反転させて読んでます。
あと、その記事がいつ書いたものか日付が入っていたら、後から読み返した時にもその情報がいつ頃のものかわかって便利かなと思います。
これからもご負担にならない程度に、続けていってほしいなと願います。
影ながら応援してます!
【お返事】
アクセスありがとうございます.背景と文字の色の件ですが,以前にも,他のページで色の組み合わせが見づらいとのご意見をいただいたことが度々ありまして,直している経緯がございます.大変嬉しいご指摘で,いわき見聞録や東京考察なども実は,色のコントラスト(背景と文字の色合い)がきつすぎてチカチカして見づらいとのご意見で,ソフトな色に直しています.そこで,郡山見聞録も色合いをちょっと変更してみました.また,日付については,これからの記事には最後に括弧書きで記載していきたいと思います.これからも,色々なネタを更新していきますので,アクセス宜しくお願いします.(2007,04,03)
【お返事へのお返事】
ご丁寧なお返事を頂き、ありがとうございます。確かに東京考察のページは文字が読みやすいと思ってました。ソフトなコントラストのほうが読みやすいのですね。日付の件も早速のご対応ありがとうございました。
本当に良質な情報がつまった素敵なホームページだと思います。文章も主観的すぎず、かといって完全な客観でもなく、とても読みやすいです。郡山にとどまらず世界エリアに至るまで、こんなページを作れる方は、
バイタリティのあふれた方なんだろうなと想像しています(笑)郡山にもこんな方がいらっしゃると思ったら嬉しくなってしまい、元来筆無精なのにメールをしてしまいました。
これからも身近な話題から世界エリアの記事まで、気長に楽しみにしてます。お身体に気をつけてご負担にならない程度に、更新していって下さいね。それでは。。。
【お返事へのお返事へのお返事】
こちらこそ,さらなるご丁寧なお返事ありがとうございます.暖かいお言葉,今後の更新の励みになります!(2007,04,07)
No.36
年齢 = 40-49歳
性別 = 女性
地域 = 兵庫県
件名 = ありがとうございました。
メッセージ = ある、劇団を観に上京するのですが、何度か東京には行っています。
今回は、交通機関の関係で、銀座に宿泊するのですが、はっきり言ってここはうといです。チャンスセンターに行こう!とか思っていて、でも、何処かわからずこのHPで知ることが出来ました。
私も、旅行が大好きで、でも、最近はあまりいけません。上京したら、観劇が主になるのですが、出来る限り、うろつきたい、です。参考になりました、有難うございました。
【お返事】
ホームページがお役に立ててうれしく思います.東京も,歩いてみると色々な表情があるので,様々なところを歩いてみると面白いものですね.今後ともアクセスよろしくお願いします.(2006,12,03)
No.35
年齢 = 40-49歳
性別 = 男性
地域 = 福島県
件名 = おじゃまします。サンバの○○です。
メッセージ = こんばんは、○○です。
たまに△△△で会いますね!会えばいつも同じネタ(酒、旅、音楽)で盛り上がりますよね!(笑)
あまりPCメールは使った事がない私ですが、サイト内の浅草や表参道の写真で懐かしく思いお邪魔してしまいました。
しかも銀座線表参道駅の出入り口の写真なんか見ると(もうたまらん!)昔その辺りにあるライブハウスでバカ騒ぎしていた時が思い出されてメッチャ、テンション上がります。なんかバンちゃんアリガトウ~、って感じですよ!マジで!
変なメールですいませ~ん。
【お返事】
お久しぶりです!! アクセスありがとうございます.いわきにいたときが懐かしいですね.人にはそれぞれ心に残る思い出の場所があります.なつかしの場所の写真に出会うと,その当時の楽しかったこと,苦しかったことなどが蘇り,自分の人生を振り返ってしまうことがありますよね.また,いわき(△△△)で酒を飲んで楽しい話ができる日を楽しみにしています.(2006,11,26)
No.34
性別 = 男性
年齢 = 50-59歳
地域 = 北海道
お気に入り = イギリス散策 訪欧ヨーロッパ アムステルダム・ブリュッセル
メッセージ = 私も以前にオランダ~ベルギー~ルクセンブルグ~ドイツの旅に行った事がありますが、その時はタリスはありませんでした。今度機会があればフランスからタリスの旅を楽しみたいと思っています。私の海外旅行HPは半分独学のHTML記述で最近のテクニックは使っていませんので貴殿のHPの完成度の高さに感動しつつ、私が旅行した時のことを思い起こしています。
【お返事】
アクセスありがとうございます.我がHPを褒めて頂き,改めて感謝いたします.ヨーロッパの鉄道の旅も旅情をそそるもので,有意義な時間を過ごすことが出来ました.でも,一番感動したのは,アムステルダムの自由な雰囲気の空気と,街中を走っているトラム(路面電車)の鐘の音でした.教会の鐘の音と,トラムの鐘の音,これだけスマートでサスティナブルな空間を経験したことがありません!(2006,10,06)
No.33
性別 = 女性
年齢 = 20-29歳
地域 = 福島県
お気に入り = ブログ「とでも、とでも。」 郡山見聞録
メッセージ = 始めまして。
郡山の情報を探しているときにこちらを知り、郡山見聞録がアップされるのを楽しみに拝見するようになりました。
生まれも育ちも郡山の私ですが、身近な知らない情報がいっぱいでとても興味深いです。
これからも更新がんばってください。
【お返事】
アクセスありがとうございます.街を歩いていて,「あっ,これはネタになるな!」と思ったときは,なるべく書き込もうと思っているのです.が,その時はそう思っても,家に帰ってくると面倒くさくなってしまうことが多いんですよね,実際のところ・・・.でも,休みの日に時間を見つけて,思い出しながら更新するように頑張っています.今後ともよろしくお願いします.(2006,07,29)
No.32
年齢 = 50-59歳
性別 = 男性
地域 = 東京都
件名 = 赤坂 金龍
メッセージ = 当店記載有難うございます。
日本の文化を継承していきたく頑張ってまいりましたが、この度金龍を閉店致しました。
しかし、日本の伝統的数寄屋建築の近代化に努め,近代数寄屋を開拓した建築家吉田五十八先生の息のかかった芸術的建築物を壊すには忍びなく、最後に芸大出身の前田正博先生 百田輝先生 川松弘美先生など若手人気陶芸陶芸家12名の展覧会を6月23日より6月30日まで、金龍にて開催致したく考えております。
この機会に出来るだけ沢山の方々に近代陶芸の美と新興数奇屋の美をお楽しみ頂ければ、幸いと考えております。
是非よろしくお願いいたします。
【お返事】
アクセスありがとうございます.赤坂は意外と行く機会がなかったのですが,現在大学のときの知人が赤坂で働いていて,酒を飲む機会があったので,そのときに撮影したものが東京考察の「夜の赤坂」のページとなっております.黒塗りの車がズラズラ止まっている地区があり,よくみると「金龍」という店があったので掲載させていただきました.政界でもよく使われていたと伺っております.せっかくの日本文化なのに残念です.建物そのものの壊されてしまうのですね.なかなか一般人は中に入れる機会がないので,是非,6月末の展覧会には行ってみて,今度は「数寄屋建築の日本料亭・金龍」とのタイトルで,東京考察の1ページを作成したいと希望しています.日本文化と東京の文化を伝えるのもこのサイトの使命ですので.(2006,05,28)
No.31
年齢 = 30-39歳
性別 = 男性
地域 = 福島県
件名 = はじめまして
メッセージ = こんにちは、猪苗代、長浜で検索した所貴兄のHPに出会いました。私は北塩原生まれの北塩原育ち、現在も猪苗代近辺をテリトリーとする者です。1969年生まれの喜多方高校出身、現在近郊のとある企業に勤務しております。幼少の頃より釣りが大好きでついウン年前までは裏磐梯でのバス釣りに奮闘しておりました。最近は子供のスポ少、地元消防等で忙しく竿を握っておりません。
最近では子供を連れて猪苗代で水遊び(ジェット)が最高の楽しみとなっております。
趣味は電気工学・・・?最近電験2種を目指し日々精進中。
それでは失礼致します。
【お返事】
アクセスありがとうございます.北塩原は裏磐梯のあるところ,大変,自然の美しいところですね.私の知り合いも,国民休暇村のホテル内で仕事をしております.今年の夏は,裏磐梯に猪苗代湖に会津の自然を満喫したいな,とも思っております.今後とも,アクセスよろしくお願い致します.(2006,05,21)
No.30
性別 = 女性
年齢 = 30-39歳
地域 = 埼玉県
お気に入り = 東京考察
メッセージ = 1992~1999年、有楽町駅近くのガード下で働いていました。いつ行ってもあのままであると思っていた、有楽町のおかめの通りが無くなっていたなんて。とてもショックです。慌てて再開発について調べていましたら、こちらを見つけました。懐かしいあの通りやお店が写真に残されていてとても嬉しかったです。「東京考察」、とてもいいです!出来ましたら、取材された(写真を撮られた)年・月をページに情報として加えて下さいますようお願い申し上げます。是非リンクさせていただきます。これからゆっくりHP見させていただきます。
【お返事】
そうなんです.有楽町駅前は今,様変わりに向けて工事中です.大きな杭打機やクレーンが入って工事が進んでいることと思います.取材した日ですが,ページの一番上の右端にCopyrightに続いて数字が入っているかと思いますが,それがページ作成年月を表しています.例えば,「Copyright (C) 2006,10」の場合,2006年10月にそのページが作成されたこととなりますので,撮影年月もその近辺ということになります.(本来のコピーライトの様式では「月」までは入れないようですが・・・)
リンクは自由となっておりますので,今後ともアクセスよろしくお願いします.(2006,04,11)
No.29
年齢 = 40-49歳
性別 = 男性
地域 = 埼玉県
件名 = 感動致しました。
メッセージ = 今日は、初めてメールを送らさせて頂く●●で御座います。たまたま、小菅(東京拘置所)の事を調べておりましたら、貴殿のH.Pに行き当たりました。大変面白い、参考になるH.Pで勉強になりました。小生、生まれは南麻布の愛育病院で、病院の真ん前にすんで下りました(現在は一族所有のマンションに建て替え/GMハウス)。父がサラリーマンだった為、転勤につぐ転勤で、いつしか「都落ち」をして現在は煎餅で有名な草加に住んで下ります。毎朝通勤電車の中から小菅拘置所の「雄志」を見ながら会社へ参ります。東京(埼玉)に住んでいながら意外と東京の事を知らないので、楽しく拝見させて頂き感謝に堪えません。今後も素晴らしいレポートをお願い申し上げます。お体にご留意の上、ご活躍下さいませ。以上、御礼まで。
【お返事】
アクセスありがとうございます.愛育病院には思い出があります.大学生の頃,図書館に本を納入する会社でバイトをしていたのですが,有栖川公園内にある都立中央図書館で作業をすることがあって,昼休みになると隣りにある愛育病院1階の食堂に行ってご飯を食べていました!外国人居住者のための輸入食材を多く売っているNationalスーパーもお気に入りでした.素晴らしい環境の地域で育ったのですね.僕もあの外国大使館の建ち並ぶ高級住宅街に住んでみたいと夢見ていました.(2006,03,16)
No.28
性別 = 女性
年齢 = -19歳
地域 = 愛媛県
お気に入り = 東京考察
メッセージ = 私は東京が舞台の小説を書いています。もちろんアマですが。
ですが私は東京都在住ではないので、本当に東京の事を知りません。だからこのサイトが本当に役に立っているんです。本当にありがとうございます。
これからも参考にさせていただきます。これからも、どんどんいろんな事を教えてくださいね。
楽しみにしています。
【お返事】
東京以外の方にも喜んで頂けて,大変嬉しく思います.東京は新陳代謝のスピードが速いので,どんどんと街の風景が変わっているように感じます.そんな日本の首都・東京をこれからも追い続けていきたいと思っています.今後ともアクセスよろしくお願いします.(2006,02,06)
No.27
性別 = 男性
年齢 = 20-29歳
地域 = 福島県
メッセージ = サイトの感想を見て牛豊に行ったのですが、最悪でした。
肉はまあまあですが、タレや注文した石焼きユッケビビンバの味付けが最悪でした。
値段は妥当だとは思いますけども、満足感で考えてもコスト高です。
ベニマルとかで売っている外国産牛をまともなタレで食べた方がおいしいと思います。
【お返事】
「最悪」でしたか.それは残念でした.まぁ,食べ物の嗜好には主観と個人差があるのでなんとも言えませんが,牛豊はGOODだったというメールをいただくこともあります! チェーン店の焼肉屋の肉よりは断然よかったと思いますね.ただ,僕もお腹が空いていたので,ちょっと褒めすぎて期待を持たせすぎましたかね(反省!) 福島県産の肉と野菜を使っている「地産地消」の取り組みについては,地域の独自性を出すという意味合いからも,福島のPRもできるので感心する取り組みです.(2006,1,16)
No.26
性別 = 男性
年齢 = 20-29歳
地域 = 福島県
お気に入り = 郡山見聞録 東京考察 いわき見聞録 福島高速バス 並木西ノ内
メッセージ = はじめまして。
私は郡山の桑野に住まいがあり、仕事で週3回いわきへ向かっています。
自分の住む街や仕事の街の情報が掲載されるのは、新たな発見や嬉しさもあり、非常にありがたいです。日々お忙しいとは思いますが、これからもHPの更新を楽しみにしております。
【お返事】
はじめまして.アクセスありがとうございます.郡山見聞録は,地元の方々からもメールいただきますが,郡山出身で他県で生活している方からもメールを頂くコーナーです.まだまだ載せたいネタが眠っていますので,更新お楽しみに・・・.(2005,11,20)
No.25
性別 = 男性
年齢 = 50-59歳
地域 = 神奈川県
アクセス経路 = 阪神タイガースショップと入力すると東京では京王百貨店7階にあると教えてくれたのがここ
お気に入り = 東京考察
メッセージ = お気に入りのページといってもまだ東京考察しか見ていないので… だけど一発で気に入りました。私がHP立ち上げたらこれだろなと。成城学園の何のコメントもない住宅地の写真の羅列で人となりが想像つきました。私も10数年前から5万分の1地図をもって、あてもなく東京中をさ迷い歩くのを趣味にしておりまして。アーこうやって写真を撮っとけばと。これから他のサイトも楽しみに見させていただきます。それでは、小田急で都内へと…
【お返事】
アクセスありがとうございます.阪神タイガースショップの東京の売り場って,検索をかけると意外と載っていないものなんですね.「成城学園の何のコメントもない写真の羅列」・・・.他のページでは写真ごとに1行程度のコメントをつけているのですが,あのページはコメントのしようがなくて,静寂な高級住宅街の点景だけを羅列してみました! このHPを開設して5年が経過しており,ちょっとずつ更新を続けています.今後ともよろしくお願いします. (2005,09,24)
No.24
性別 = 男性
年齢 = 20-29歳
地域 = 北海道
お気に入り = いわき見聞録 アクアマリン 小名浜港 小名浜観光 永崎海岸 いわきおどり 郡山見聞録
メッセージ = 小名浜や郡山の身近な情報が満載で、最後まで読んでしまいました^^
また遊びに来ますので更新頑張って下さいね★
都市計画の情報などもあれば嬉しいです。
【お返事】
アクセスありがとうございます.小名浜には3年ほど住んでおりましたが,美味しい刺身と大きな海を見たくなってたまに行っています.なかなか福島県で都市計画の情報は少なくて,トピックスとして取り上げるほどのものがないのが実情!?のような感じですが,今後ともアクセスよろしくお願いします. (2005,09,23)
No.23
性別 = 女性
年齢 = 20-29歳
地域 = 埼玉県
お気に入り = 東京考察
メッセージ = 都市社会学を学んでいる自分にとってはとても参考になるHPです!特に豊洲の記事が良いなと思いました。
【お返事】
アクセスありがとうございます.「豊洲」はじきに生まれ変わって街開きが行われると思います.あの殺伐としたゴーストタウンの様相は,もう味わうことができないでしょう.埋め立て地特有の殺伐とした風景が唯一残っていた埠頭だったと思います.かつてのお台場(13号埋立地と呼ばれていた)もそうだったように. (2005,06,13)
No.22
性別 = 男性
年齢 = 20-29歳
地域 = North America
お気に入り = 福島高速バス 福島航空 郡山見聞録
メッセージ = 現在はアメリカ在住ですが、生まれも育ちも郡山市です。このサイトで郡山の最近の出来事を知っています。文章も大変面白く、裏話的なことまで載っていてかなり役に立っています。これからも頑張ってください。あっ、酪王牛乳のカフェオレ飲んだことありますか?あれが福島県限定だと知ったのはつい最近です。でも、カフェオレと言えば誰が何と言おうと酪王です。
【お返事】
アクセスありがとうございます.今はアメリカ在住ですか.福島県の方が世界で活躍されているのを見ると感動してしまいます! 酪王牛乳ですか.まだ飲んだことがありませんね.こんどカフェオレなるものを飲んでみたいと思います.郡山見聞録は,郡山在住の方にとっても評判のいい!?コーナーで,いつも「まだ更新しないの?」「最近,全然更新していないね~」などと言われてから更新をしている次第です.今後とも,アクセスよろしくお願いします.(2005,05,29)
No.21
年齢 = 50-59歳
地域 = 東京都
メッセージ = 東京考察No.78の神谷町に於いて虎ノ門の中心は神谷町となっていましたが、虎ノ門の中心は虎ノ門1丁目です。現在の神谷町駅付近は以前、港区芝神谷町という地名でした。ちなみに昔は小さな商店ばかりの町でビジネス街になったのは25年位まえからです。私は神谷町で生まれ50年住んでいました。虎ノ門5丁目は幾つもの小さな町の集まりです。虎ノ門1丁目は昔からビルが沢山ありました。
【お返事】
貴重なご意見ありがとうございます.なるほどそうだったんですね.僕は今の神谷町の姿しかしりませんので,てっきり神谷町駅周辺が中心かと思ってしまいました.やっぱり地名というのは,過去の街の状況を如実に表していますね.1丁目が一番栄えていたことが,虎ノ門の場合も当てはまります.ページを若干修正させていただきました.今後とも,アクセスよろしくお願いします. (2005,04,17)




























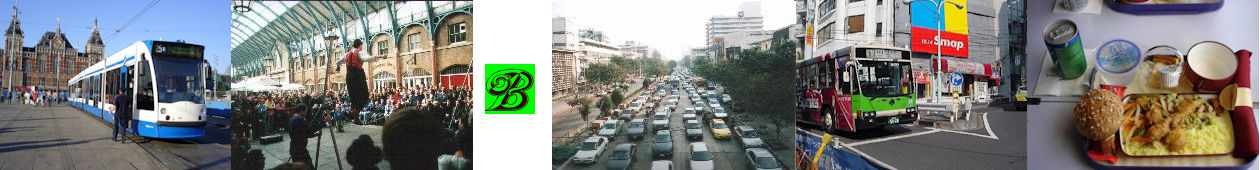
![2日目スタート→ゴール[阿武隈川カヌー駅伝大会物語#4]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/DSC00250.jpg)












































































































































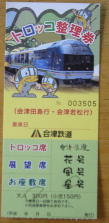





















































































































































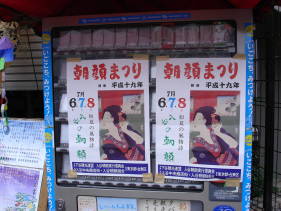




















![祝賀山車フェスティバル[福島市制施行100周年記念事業]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/DSC00067.jpg)