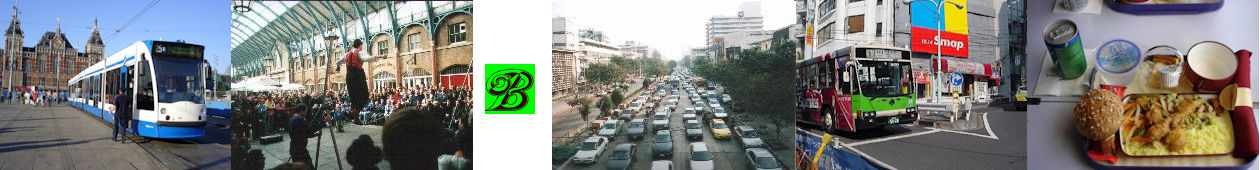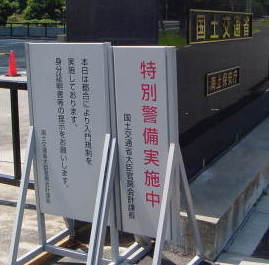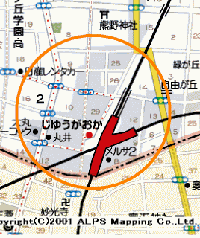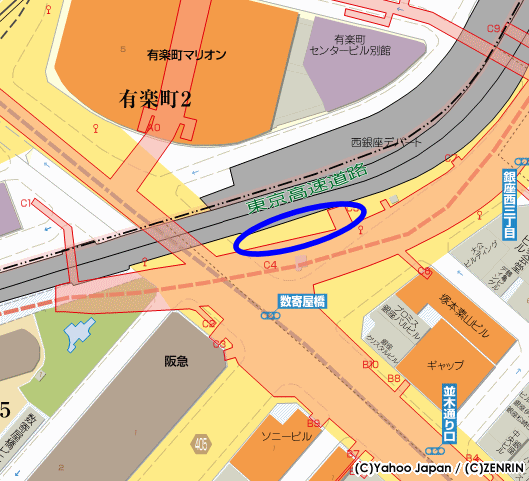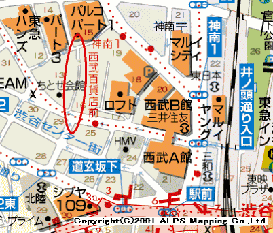Hotel OKURA Tokyo (At Toranomon)
 ホテルーオークラ東京本館正面 |
 |
| ホテルオークラ東京は,1962(昭和37)年に開業した超一流のホテルである.ホテル御三家のひとつであり,外国からの要人や皇室をおもてなしするなど,日本を代表する超一流ホテルとして君臨している(ホテル御三家:帝国ホテル・ホテルニューオータニ・ホテルオークラ).しかし,昨今の外資系ホテルによる東京のホテル競争が激化していることにより,このホテルオークラも苦戦を強いられており,今年3月にはグランドコンフォートフロアー(リラクゼーションを目的としたリラックスフロアー)をオープンさせるなど,ホテル競争に打ち勝つための戦略を打っている. 次々と開業する外資系ホテルは目新しいこともあって(ちなみに外資系ホテルの「新御三家」としては,パークハイアット東京(新宿)・ウェスティンホテル東京(恵比寿)・フォーシーズンズホテル椿山荘が挙げられている),そちらにお客が流れるということが起きているのであろうが,ホテルオークラ東京のホテルマンの接客態度や和を取り入れたサービスは最高級の定評があり,ホテルオークラ東京の良さが損なわれることはないように願わずにはいられない. ホテルオークラの名前は,戦前の5大財閥(三井・三菱・住友・安田・大倉)のひとつであった大倉財閥の二代目大倉喜七郎氏の名前にちなんでいる.大倉喜七郎氏は日本における国際的超一流ホテルの必要性を渋沢栄一氏らとともに唱えて大正14年に旧帝国ホテルの支配人に就任している人物であるが,終戦を過ぎて東京オリンピックを控えた頃,国際ホテル建設の構想を練り,欧米の合理性と日本古来の伝統美,この2つの調和を基本構想として野田岩次郎氏とともに大倉邸跡に建てられたホテルが,このホテルオークラなのである.(ホテルパンフレットより参照) ホテルオークラのデザインはイチョウの葉っぱを用いているが,これは東洋にしか育成しない銀杏の,葉の姿が美しく,また不老長寿や防火の象徴であることから,各種の食器やインテリア・備品類にデザイン化して用いられている. |
 玄関ではベルボーイがドアを開けてくれ,荷物を運んでくれる. |
   一歩足を踏み入れると静寂なロビーが待ち受けている. このロビーの雰囲気がたまらないというファンも多い. |
| 帝国ホテルやニューオータニと違って,ホテルの場所がアメリカ大使館やスペイン大使館に挟まれたところに立地し,周辺の警備が物々しいこともあって,不用意にぶらっと立ち寄る客が少ないためにこの静寂さが保たれているように思う.ロビーでフロントを探していると,すぐにベルボーイが近くにやってきて「何かお探しでしょうか?」,と自然な笑顔で聞いてきた.「お客様に聞かれる前に行動する」というのがモットーである.さすがは,ホテルオークラである. |
  左が本館のフロント.右が別館のフロント. どちらでもチェックイン・アウトができる. |
 本館と別館は通路で結ばれている. チェックインを済ませて,ベルボーイが荷物を持って部屋まで案内してくれる. |
 各階のエレベーターロビー ソファーと灰皿が備えられている |
 客室の廊下(別館) 向かいの部屋の人と顔合わせがないように, 部屋の扉は互い違いに配されている. |
 スタンダードのツインルーム |
  枕には「鶴」と「亀」の和紙の折り紙が置かれていた. ホテルオークラは,「和」のくつろぎと「洋」の利便性を少しでもお客様に提供したいと 常日頃より考えているとのこと. 外国人には新鮮に映るだろうし,日本人にとっては改めて日本文化を振り返ることができる. |
 全室に専用FAXがつけられている. ブロードバンド対応のインターネット接続ができるように端末も配線されている. |
  洗面台とトイレ ウォシュレット付きで,便座に座ると音消し用の水が自動的に便器の中に流される優れもの |
 シャワールームとの仕切カーテンには「Hotel Okura」の刺繍入り |
 ドアノブには,周辺のジョギングコースの案内が下がっている 外国人客にはジョギングをする人が多いとか. |
 ワインのルームサービスを頼んでみた. 電話では,「○○様,ルームサービスでございます」と名字による受け答えが返ってきた. 凡人にはこれだけでも感動もの! |
 朝には希望の朝刊が届けられる. |
 ルームサービスのメニュー 朝食は,一番安くて2,835円から. フレッシュジュースが1,050円也. 和定食は3,675円. |
 何とも落ち着く静寂なロビー |
 雪見障子が使われている. |
 端午の節句でカブトが置かれていた. |
 エレベーターを案内する女性は「着物」である. |
 ロビー中二階には[Writting Space]なるものがある. |
 ショッピングゾーンも独特の雰囲気 ここは帝国ホテルと同じ雰囲気である. |
  外国人のための英語ガイドパンフレットも置かれている. (もちろん日本語のガイドも置かれている) |
| なお,最近は熾烈なホテル競争に対抗するため,手頃な宿泊プランを設定して,通常料金よりも安く泊まれるようになっている.特に,インターネットで予約すると半額近い値段で泊まれることもあるので,インターネットを利用した宿泊をお薦めする. |